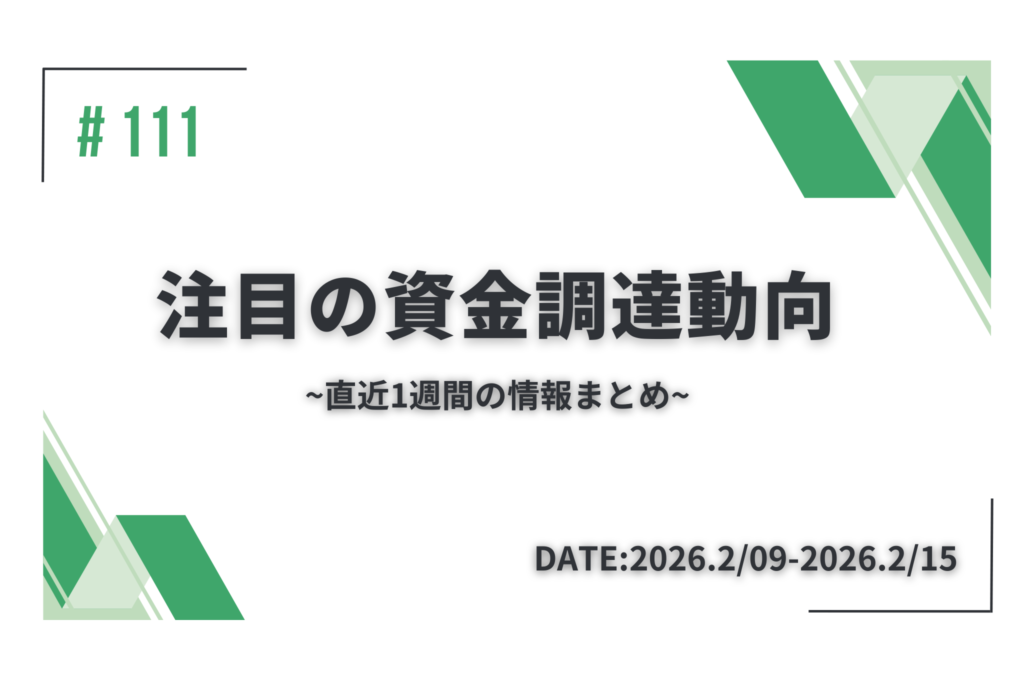【#320】プラントベースフードで日本を元気に!「おいしい」を重視し、日常に溶け込む食料をつくる|代表取締役 中村 明生(株式会社ディッシュウィル)

株式会社ディッシュウィル 代表取締役 中村 明生
株式会社ディッシュウィルは、プラントベースフードを製造・販売している会社です。大豆を中心に、 カシューナッツなども用いて商品を作っています。13年に渡るコンサルタント時代の経験やご縁を活かし、日本の食品会社の希望となるべく躍進を続ける代表取締役の中村明生氏に、事業や今後の展望などをお伺いしました。
「垂直統合」で「おいしい」プラントベースフードを
事業の内容をお聞かせください
我々は、プラントベースフードの製造を垂直統合で提供する会社です。これは世界でみても稀有なビジネスモデルで、植物工場での大豆の育成から大豆タンパク原料の製造、最終的な商品の生産までを6人ほどの少人数で実行しています。
垂直統合のメリットは、大豆自給率の高くない日本で、安定的かつ環境に悪影響を与えずにプラントベースフードを製造できる点です。
日本の大豆はとても良質で香りが豊かなため、納豆や豆腐にするとおいしいといわれます。ところが、肉や魚をつくりたいプラントベースでは豊かな香りがかえって邪魔になってしまうのです。そこで海外の大豆を仕入れたいところですが、今の日本は厳しい輸入環境に置かれています。
現在の大豆の世界的産地はブラジルです。そしてブラジルには、日本がODA開発で生産技術を教えた過去があります。
本当は技術を教えて生産された大豆を買い取るつもりでしたが、現状では、9割以上が中国に買い占められています。ブラジルは、大豆の需要が高いのであればと生産量を増やすためアマゾンの森林を伐採して大豆畑を増やしました。
アマゾンは「地球の肺」とも呼ばれる、二酸化炭素を吸って酸素を排出する地帯ですが、森林伐採が未だにつづいていることにより、地球の肺は二酸化炭素量を排出する土地に様変わりしてしまいました。
プラントベースフードのニーズが拡大しても、その原料を生産する工程が温暖化に繋がってしまっては本末転倒だと考えたところから弊社のビジネスモデルは生まれました。

なぜ少人数で垂直統合が実現できているのでしょうか?
私の前職はコンサルタントです。部長職として13年間さまざまな食品関連企業に携わっていました。そこでのアライアンス戦略が、「自分たちでできないことは外部の資本を使う」方法です。
例えば、植物工場での穀物の育成については外部の上場企業に出資していただき、かつ業務委託契約や業務提携を結ぶことで共同で事業に取り組んでいます。
スタートアップの我々が人的リソースを割かずとも、何万人規模の従業員を抱える上場企業の総合力でビジネスを成立させることが出来ました。
また食品の生産では、私の前職でのご縁も活かしています。前職で私がコンサルティングしていた会社のうちの1社が、とある町のブランド牛を調理していた会社だったのですが、私の起業後にブランド牛の生産自体を事業として廃業してしまい、その食品工場の加工場所が空いてしまいました。
その会社とは長いお付き合いがあったため、人的リソースはその会社の従業員を活用し、我々で原価計算を行った結果をもとに共同してOEMの自社工場を運営することにしました。
これは、先方の社長との信頼関係なくしては実現し得ない方法です。
事業を始めた経緯を教えてください
コンサルタント時代から、食品企業はもっと世界に出るべきだと感じていましたが、当時の私は立場的に、理論を考えて提案し、実践を促すことしかできませんでした。
2代目や3代目、なかには13代目まで長く続いている食品企業の方々に「海外に出ましょう」と進言したところで、「今でも安定的な売り上げがあるのに、コストをかけてなぜわざわざそのような挑戦をするのか」と懐疑的に捉えられてしまうことがありました。
そこで、「ならばもう、自分でやってしまおう」と思い、自分が生産者サイドに立って動ける会社を作ることにしました。
「世界に出やすく、 自分にも知見があって、最終的に拡大できそうな市場」と考えると、食品関連のなかでも新しい市場であったプラントベースフードが適していました。
これまでお付き合いしてきた食品関係者の方々とも事業で重複しないため、応援していただきやすい上、その市場で我々が1番になれれば、日本の食品会社の希望にもなると思いました。

事業で大事にしていることはありますか?
弊社が注力しているのは、「味」です。400名ほどを対象にアンケートを実施したところ、95%を超える方から「おいしかった」との評価をいただきました。
一般的なプラントベースフードの場合、「大豆のにおいがしておいしくない」といった声が多く聞かれます。そこで我々は、「食品としておいしいものをつくる」ことにしました。
商品開発では、100〜300回の試作を行います。その結果、これまでプラントベースフードに否定的だった方からも、弊社のものであれば食べたいといっていただけるようになりました。
いくら身体に良く、地球環境に優しくても、味が良くなければ食べるのは苦痛でしょう。フードロスを防ぐ観点からも、やはりまずは「おいしい」ことを大切にしたいと考えています。
そのために弊社では、センサーではなく人の味覚による味づくりを行っています。以前味覚センサーを試した際に、数字が同じでもおいしく感じるものと、そうでないものがあったので、弊社では研究者が本物の食品と食べ比べながら、感覚を頼りに試作を重ねています。
どのような商品が人気ですか?
いまはプラントベースのスイーツが人気で、主にホテル業界で採用されています。
弊社とお取引きいただいているホテルの多くは、現在インバウンドの影響で海外富裕層の利用が急増しているそうです。一方で、日本の働き手不足の関係から、ホテルのシェフの数は減っています。そこで重宝されているのが、弊社のプラントベーススイーツです。
ホテル業界全体が、自社で作るよりもすでに完成しているおいしいものを仕入れるという考え方にシフトしていると実感しています。

良い成果をあげたいなら、ホワイト企業であるべし
仕事におけるこだわりを教えてください。
重要視しているのは、ホワイト企業であることです。現に、弊社はとてもフレキシブルな体制を整えています。例えば、何時に出社しても、退社しても構いません。極論、2時間だけ働いて帰ってもいいのです。
さらに弊社では、基本的に互いを役職ではなく、「〇〇(苗字)さん」と呼び合います。これは、全員がそれぞれの役割をこなしていることを尊重する気持ちの表れです。自身の役割を全うした結果、社内最年少である24歳の社員が、社長の私に「しっかりしてください」と指摘することもあります。
会社はよく船に例えられますが、私自身も「自分は船長として指示出しをしているだけ」だと考えています。船が難破しそうなときは、船長であろうが船員であろうが関係なく、全員で水を外にかき出すでしょう。
会社も同様に全員の関係性はフラットなので、そんな仲間たちを時間で縛るのはやめようという思いに至りました。
フレックス勤務を実践してみると、やはり自分が働こうと決めた時間に集中して働けるため、モチベーションが上がります。サボろうと思えばサボれる環境ですが、今のところ全員意欲的に働いてくれており、弊社にとっては非常に生産的で効率の良い働き方だと感じています。
早くから起業を希望していましたか?
前職は、「企業家輩出機関」を謳っているような会社でした。私自身も、大学3年生頃から将来企業家になることを見据えて、「企業家を多く輩出しているコンサルティング系会社」に絞った就職活動を行っていました。
コンサルタントを目指したきっかけは、学生時代のアルバイト経験です。高校1年生から始めたコンビニエンスストアのアルバイトで、自分でいうのも変ですが、とても仕事ができ、一緒に働くメンバーを鼓舞する才能があることに気づきました。
当時はコンビニエンスストアのアルバイトだけで月50万円稼げていましたし、接客ランキングのようなイベントや、業務改善案を競うコンテストなどでも常に1位でした。利益率の最も高いドリンク部門を任せてもらったときには、部門の売り上げを前年対比300%まで上げました。
これらの経験から自分の力をさらに試したい、その先の起業は常にぼんやりと頭にありました。
起業から今までの最大の壁を教えてください
やはり、資金調達です。スタートアップを経営する多くの方が基本的には人生で初めての資金調達を行います。初めてサッカーやバスケットボールをやるときのように、「やりながら覚える」ことがほとんどで、ここはいまだに苦戦しています。
資金調達というものは不思議なもので、成功するときは案外スムーズに話が進みます。失敗したときのほうが、実は多くの手がかかっています。
失敗から学んだことは、対等に交渉することの重要性です。お金が欲しいから資金調達を行うわけですが、だからといって下からお願いするようなスタンスだと、案外うまくいきません。
なぜなら、先方もビジネスとして出資を判断するからです。対等な関係を築いた上で、利害が一致するイメージを共有することが大切だと思います。

優秀な従業員たちに負けたくない!
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
弊社の従業員は基本的に私が採用していますが、全員もれなく、非常に優秀です。そして、彼らに負けたくない気持ちが私のモチベーションになっています。
会社は、トップの器以上は大きくなれないといわれています。従業員がどんなに頑張っても、トップの器が小さければだめだと考えると、「もっと彼らのために頑張らなければ」と思えます。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
プラントベースフードと聞くと「健康に気を遣う方のもの」とイメージするかもしれませんが、我々が弊社の商品を届けたいのは、「普通の方」です。宗教や価値観によらず、日常のなかでおいしいものを食べる際の選択肢のひとつになればと考えています。
我々は、プラントベースフードを決して特別なものではなく、日常に溶け込めるものとして世界に広めていきたいです。文化やアニメなどと並んで海外から高く評価される「食」の技術でブランドベースフードのマーケットを作ることが、我々の最終目標です。
また、食料危機の面からも、ブランドベースフードを日常食として認知拡大する必要性があると感じています。日本で暮らしていると食料危機を身近に感じにくいかもしれませんが、世界では今日食べるものもない人が8億人もいるといわれています。
こうした危機感から、海外ではすでにプラントベースフードや昆虫食といった食料危機に対する取り組みが広がり始めています。日本でも、弊社の事業を通して認知を拡大していきたいです。
また、我々が最終的に作りたいのは、食料ハブです。弊社の設備を置くと、そこで大豆が育ってプラントベースフードが出荷される、そういった食料ハブを世界中に作りたいです。
そして個人的な目標として、日本を今より元気にしたいと考えています。実は、前職の新卒時代に自分が掲げたスローガンがまさにこれでした。
お金を稼ぐことで豊かになることも大切だとは思いますが、私はそういったことよりも、自分の行動が誰かのヒントになったり、 共感してもらえたりするようなことを目指しています。

起業するならよく考え抜くこと!
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
若いうちの企業は大賛成です。しかし、20代後半での起業はやめた方がいいと思います。大学を卒業してすぐの起業なら、失敗してもおそらく次があるでしょう。
しかし、27、28歳で失敗したときには、「もう一度起業しなければ」「ある程度の役職でなければ」といったプライドが再起の邪魔をすると思っています。
ただ、若いうちであっても、自分の姿勢をしっかりと見極めた上で起業したほうがよいでしょう。今、時流は公的資金を投入してスタートアップを増やすところにありますが、その結果、世界を変えるとは思えない、自分の懐を温める程度の事業で起業する方も多く見られるようになりました。
今はそれでよくても、果たして10年後はどうでしょうか。これを27、28歳で始めて5年後に失敗した場合、再就職や再起業の際にプライドが邪魔をして、結果的にモチベーションが低下してしまうと考えられます。
起業には、つらいことや厳しいことがたくさんあります。自分が向いているかもしっかりと考え抜いてから実行することが大切です。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:中村明生 氏
新卒で東証一部の上場コンサル企業に入社するもリーマンショックによる倒産を経験。偶然配属された食品関連のグループ会社でMBO、9期連続の赤字事業の黒字化に1年で成功し当時最年少の部長となる。食品生産者向けのコンサルティング事業を立ち上げ、日本全国の様々な食品事業者の支援を10年行う。その後スタートアップのCOOを経て、現職。
企業情報
|
法人名 |
株式会社ディッシュウィル |
|
HP |
|
|
設立 |
2022年7月7日 |
|
事業内容 |
農業、食品加工、食品OEM受託、コンサルティング業等 |
関連記事