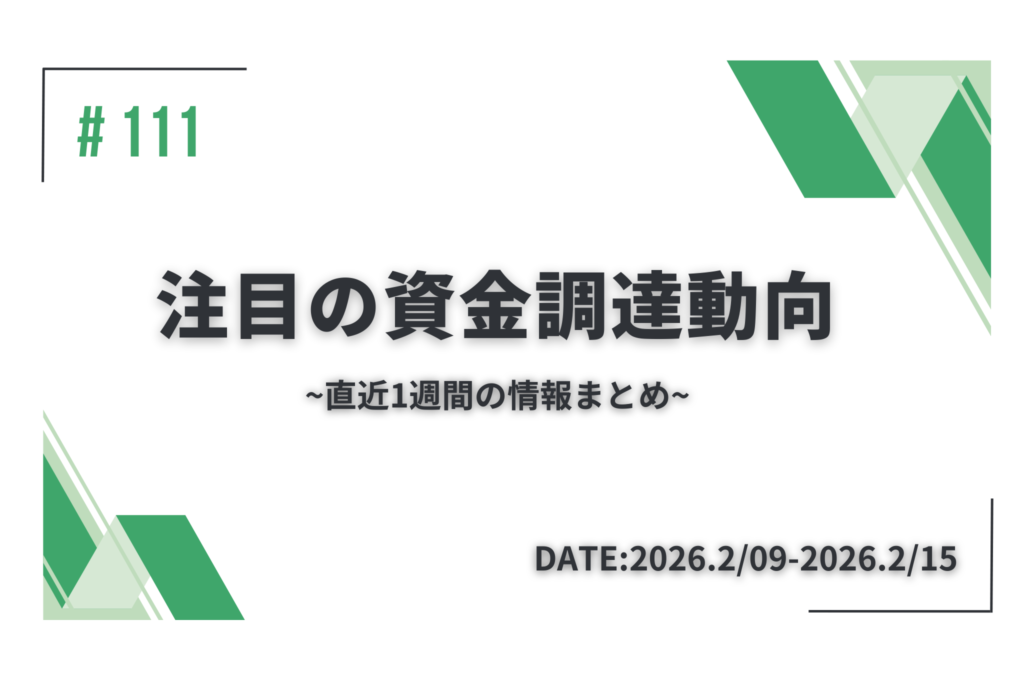株式会社博水 専務取締役 江越 雄大
株式会社博水は、創業明治36年、福岡で5代続く練り物メーカーです。特色は日本では希少となった、地元魚市場から仕入れた鮮魚を使う伝統的な製法を守り続けていること。魚を使った麺「BOKOMEN」や「ギョロチキ」という魚と鶏を合わせた商品など、練り物の概念を変える革新的な商品開発も行っています。高い衛生基準で学校給食や飲食店向けの商品提供、アメリカへの輸出、そして魚のフードロス削減という社会課題への取り組みを通じて、日本の練り物文化の継承と海外展開を目指しています。専務取締役の江越雄大氏に、事業内容や今後の展望なども含めて詳しくお聞きしました。
伝統的な製法を守り抜く老舗の練り物メーカー
事業の内容をお聞かせください
弊社は主に魚のすり身を使ったさつま揚げやかまぼこなどの魚肉練り製品の製造と販売を行っています。
当社の特徴は、昔ながらの製法を守っていることです。現在、日本の練り物の9割以上は海外から輸入した冷凍の原料から作られています。しかし、私たちは地元の魚市場から鮮魚を仕入れ、それを加工して製品にするといった伝統的な方法を守っています。この昔ながらの製法や味を残せる会社は、今の日本ではほとんどありません。
冷凍すり身の技術自体は日本で開発されたものですが、コスト面から海外生産が主流になり、味の特色や地域性が失われてきました。その背景の中で、私たちは地場の魚を地場で加工・消費するという伝統を大切にしています。
加工は最初に手作業で頭と内臓を取り除き、その後専用の機械で魚肉を取り出します。この機械も今では製造する会社が少なくなっているので、しっかりメンテナンスしながら使い続けていけているのも当社の強みです。
販売は9割がBtoBで、東京の豊洲市場にも商品を出荷し、そこから飲食店が買い付けることが多いです。企業向けには加熱前のすり身状態で500グラムや1キロ単位で販売し、一般向けには加工したさつま揚げやイカシュウマイ、かまぼこを販売し、ふるさと納税も取り扱っています。
また海外展開も行っており、現在はアメリカに力を入れています。当社は創業122年ですが、これから先の100年を考えると、日本の人口減少を見据えて海外市場に目を向ける必要があると感じています。アメリカへの輸出は2012年頃に父が始めたもので、主に日系スーパーの十数店舗ほどに商品を提供しています。

事業を通じ、どのように社会貢献したいと考えていますか?
練り物が今後爆発的に売れるかと言われると、正直難しいと思います。もちろん新しい市場を作るなど可能性を追求して動いてはいますが、簡単ではないでしょう。
そうなると、他の価値を生み出していく必要があります。そこで私たちが取り組んでいるのが社会課題への挑戦です。具体的には、魚のフードロス削減に貢献できると考えています。この部分で社会的価値を見出していきたいです。
また、当社は地域に根ざし長年商売をしてきたため、地域内での認知度が高いです。お客様は40代以上の方が中心で、地域の人々が集まる場所になりつつあります。正式なコミュニティスペースではないものの、地域企業としての役割も今後作っていけるのではと思っています。
それに加え「地域の推し企業になる」とよく話をしています。アイドルを「推す」といった行為が、推している人たちの活力になるように、推す対象は企業にもなり得ると思います。地域の人たちに応援してもらえる企業を目指していきたいです。
事業を継承した経緯をお伺いできますか?
練り物屋の5代目として、子どもの頃から跡を継ぐことを意識していました。しかし実際には、大学卒業後も家業を継ぐつもりはありませんでした。練り物にあまり興味がなく「食品工場は汚い、臭い、きつい」といったイメージがあり、継ぐ気になれませんでした。この気持ちと現実のギャップは入社後も続き、親との衝突の原因にもなりました。
事業継承を決意したのは比較的最近です。コロナ禍がきっかけで、BtoB中心の事業が大打撃を受けた為、自分たちでお客様を獲得するための取り組みを始めました。そこでお客様と直接接する中で、喜んでもらえる姿を見て、練り物の可能性を感じるようになったのです。
練り物は「手段」であり、それでお客さんが喜んでくれるなら良いといった価値観に変わったことで、本格的に事業を継ぐと決意しました。

食の安全へのこだわりと、循環を生み出すコミュニケーション
仕事におけるこだわりを教えてください。
食品を扱う上で、何より重視しているのは衛生面です。当社はHACCP認証を取得していますが、私たちの規模の会社では珍しいです。アメリカへ輸出をしている背景もありますが、食品衛生の基準を厳格に守ることは私が特にこだわっている点です。
この認証は必須ではありませんが、持っていることで安心感が生まれ、大企業との取引でも評価されます。また、学校給食の仕事も増えており、現在福岡市内の20数校の小学校に納品しています。
実際に自分で配達に行って、給食調理員の方々と「今日はどのように使うんですか」などコミュニケーションをとることもあります。給食スタッフさんから「子どもたちが喜ぶんだよね」と言ってもらえるのはとても嬉しいです。
また、給食に会社名は表示されませんが、子どもたちが美味しさを両親に伝え、それをきっかけに親子で店舗に来てくれるといった良い循環が生まれています。こういった食を通じたつながりを大切にしたいと考えています。
今までの最大の壁を教えてください
最大の壁はコロナウイルスの拡大です。会社がなくなるかもと本気で心配しました。仕事がない時は、Uber Eatsの配達員をしていました。
これには目的があって、飲食店を回ることで、コロナ禍での実際の状況を把握し、どのような場面で当社の商品が活用できるかを見極めながら、活動していました。
転機になったのは、学校給食の仕事です。「ブリのカマを商品にして何かできませんか」といった相談を受けました。売上的にも大きな案件だったので、この仕事のおかげで厳しい時期を乗り越えられました。

日本の練り物を海外に浸透させる
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
1番はお客様の声です。特にコロナ禍の時には、本当にお客様に支えていただいたと感じています。
当時「練り物の価値って何だろう」と考えていました。正直、練り物がなくても困らない世の中ですし、個人的には肉の方が好きでした。
ですが、お客様から「あなたの会社の商品を食べて練り物の概念が変わりました」「子どもが普段魚を食べてくれないけど、練り物だったらたくさん食べてくれます」「食卓のメニューが1つ増えました」など、そういう声をたくさんいただいて、初めて自分の仕事や練り物そのものに価値を感じることができたのです。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
練り物の文化を後世に残し、日本の練り物を世界に広めていきたいです。
海外に行っても、日本の練り物はあまり見かけません。日本の最大手の会社が海外で製造して輸出しているケースや、中国製の安い製品が入っていたりする状況です。
一方で、カニカマは世界中で食べられています。これは元々日本が作った商品なので、それを考えると練り物には可能性があると感じており、日本の練り物文化を海外に広めていきたいと思っています。
その一環として、会社の2階を使って、練り物体験教室を始める予定です。これは親子向けの食育の一環になると考えています。練り物が実際に魚からできていることや、どうやって美味しく食べられるかということを、体験を通して伝えていきたいと考えています。
あと、個人的な話になりますが、私は筋トレが趣味で、会社内にトレーニングスペースを設けています。これには2つの目的があります。1つ目は私自身がボディメイクの大会に出場して「練り物を食べてこの体を作りました」とPRし、「フィッシュプロテイン」と呼ばれる練り物の栄養価値を実証することです。
もう1つの狙いは、この活動が将来の採用にも繋がると考えています。パーソナルトレーナー業界が飽和状態になる中で、そういった方々を雇用して、うちでパーソナルトレーナーもしてもらいながら練り物を作ってもらうといった、新しい雇用形態の創出を目指しています。

継承よりも業界を知ることが先
事業継承しようとしている方へのアドバイスをお願いします
一度、同じ分野や業界の大きな企業で経験を積むことをお勧めします。私自身、印刷会社で1年半ほど働いた経験がありますが、畑違いの仕事だったこともあり、十分な学びを得られませんでした。
そこで同じ分野や業界で仕事の流れや、どのような業務が行われているかを知ることが重要だと思いました。知識を身につけた上で事業継承に臨むと、その可能性をより早く大きく伸ばしていけるのではないでしょうか。
また、事業継承を経験した人たちの話を聞くことも大切です。最近では事業継承を国が支援する動きがあり、そういった人たちと関わりやすい環境が整ってきています。積極的に人に会うことで、選択肢が広がっていくでしょう。
魚のフードロスを活かす商品開発、共に取り組むパートナー募集
弊社ではこれまで、ブリのアラやコノシロなど、市場での評価が低く流通しづらい魚種や、廃棄されがちな部位を活用し、美味しく食べやすい練り製品として商品化してきました。鮮魚から製造する技術を持つ私たちだからこそ、フードロスとなる魚を、形を変え、味を変え、より食べやすい魚食として価値に変えることが可能です。
水揚げ過多による価格崩壊や、規格外・未利用魚の処分にお困りの漁業関係者様、アラや中骨に可食部位が残るにも関わらず活用できていない水産加工会社様、未利用資源を軸にした商品をお探しの販売会社様など。ぜひ、私たちと共に“もったいない魚”を価値に変える取り組みを始めませんか?ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先 MAIL : info@hakusui-foods.com TEL : 092-551-4426
本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:江越 雄大氏
2012年立命館大学卒業後、海外留学を経て印刷会社に入社。
2015年に家業である122年続く魚肉練り製品製造販売を行う株式会社博水に入社。製造、営業、商品開発、店舗販促、自社ECの立ち上げなどを行う。日本伝統の食品のひとつである練り製品を後世に繋ぎ世界に広めるため、地元の学校給食から海外輸出まで販売。
中小企業庁主催の第5回アトツギ甲子園ファイナリスト、企業特別賞を受賞・
企業情報
|
法人名 |
株式会社博水 |
|
HP |
|
|
設立 |
1996年3月 |
|
事業内容 |
魚肉練り製品の製造・販売 |
関連記事
RANKING 注目記事ランキング
- 【#468】意見が政策につながる社会へ。市民参加型SNSと自治体向けAIで「デジタル民主主義」を推進|代表 伊藤あやめ/谷口野乃花(Polimill株式会社)起業家インタビューインタビュー

- 【#363】お金いらずで寄付ができるECサービス、世界を救う第一歩に|代表取締役 藤本 巴(株式会社ギバース)起業家インタビューインタビュー

- 【#544】保護犬・保護猫の命をつなぐ。福祉と仕組みづくりで、寄付に頼らず築く持続可能な社会|CEO / 代表取締役 伊東 大輝(株式会社ANELLA Group)起業家インタビューインタビュー

- 【#268】定年齢層向けイベントアプリ『シュミタイム』で、高齢者の社会的孤立を救う。|代表取締役CEO 樗澤 一樹(株式会社ジェイエルネス)起業家インタビューインタビュー

- 【#578】赤ちゃんの感情を可視化するAIアプリ『あわベビ』で、産後うつの課題を解決|代表取締役・CEO 中井 洸我(株式会社 クロスメディスン)起業家インタビューインタビュー