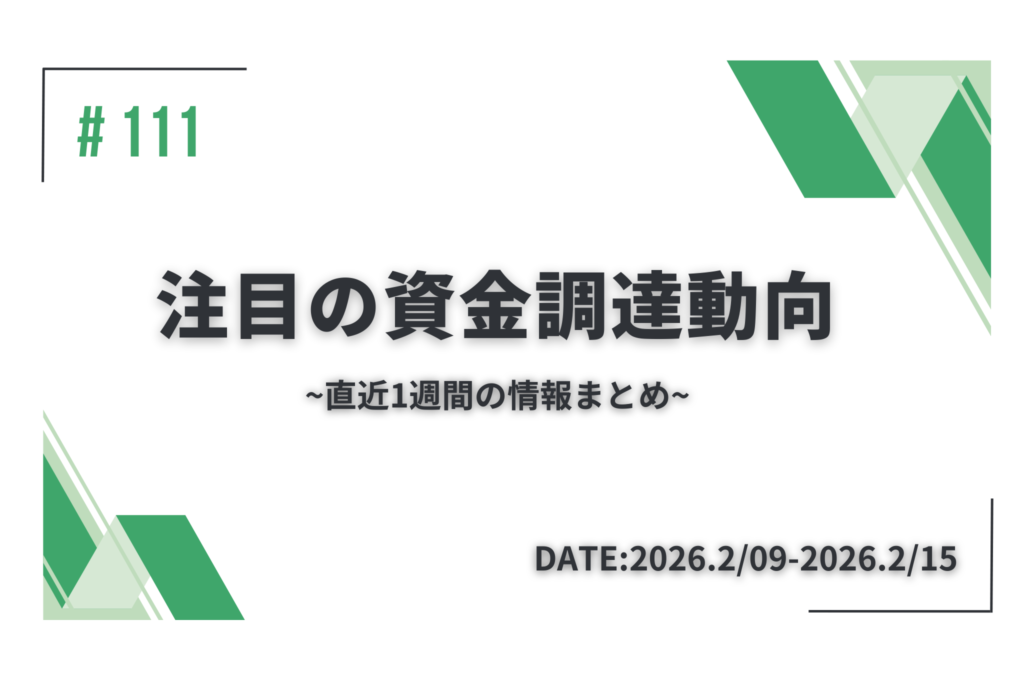ハイラブル株式会社 代表取締役CEO 水本 武志
ハイラブル株式会社は、対面やWeb会議の音声を定量分析し、可視化するサービスを提供しています。「音環境を見える化することで、より良いコミュニケーションの実現を目指す」と話す代表取締役CEOの水本武志氏に、音環境分析がもたらす可能性や今後の展望について、お話を伺いました。
音環境分析でコミュニケーションを豊かにする技術
事業の内容をお聞かせください
当社は音環境分析技術と議論分析技術を強みとして、対面会議やWEB会議などでの会話量をグラフで見える化するサービスを提供しています。人の会話分析と場所の音環境分析を用いて、コミュニケーションをより豊かにすることをミッションに掲げる会社です。
音声を取るのは、8個のマイクが内蔵されたたまご型の専用マイクです。専用マイク以外にも、オンライン会議のZoomやTeamsなどのリアルタイム分析にも対応するほか、録音データをアップロードすることで後からの分析もできます。
活用場面の一つは、学校の話し合いやグループディスカッションの授業です。そこで会話量を測定し、やり取りのパターンを可視化したデータを見ながら話し合いを振り返ることで、参加者が「次はもっと発言しよう」「この人に話を振ってみよう」 など、メタ認知を高めながらより良い議論を模索できます。
データを蓄積することで「国語の授業では積極的に話すが、算数では発言が減る」といった傾向や、「特定の生徒と一緒だと話しにくい」などの関係性も見えてきます。
これは企業研修にも活用されています。会議や面談の場で「本当に相手の話を聞けているか?」「会話のバランスは取れているか?」といった点を客観的に振り返り、スムーズなコミュニケーションへとつなげることができます。
その場所がどの程度活用されてるのかを示すのも、音環境分析の大きな役割です。オープンオフィスや談話スペースに複数のマイクを置き、空間内のどこで会話が発生しているのかをヒートマップのように可視化できます。このデータをオフィスのレイアウト改善や設計時の客観的な指標とするほか、展示会で来場者の動向やブースごとの盛り上がりを分析する際にも活用いただいています。
当社の技術を導入した企業さまからは、「データを基に会話のかたよりが見えるので、納得感のある改善ができる」といった声を多くいただいています。例えば、会議で新人の発話が極端に少ないことがわかり、周囲が意識的に発言を促すようになり、チームの活性化につながった事例もあります。
技術が使えるのは人間の会話だけではありません。生き物のコミュニケーションにも応用しています。
現在は日比谷公園にマイクを設置し、どんな種類の鳥がどこで鳴いているかといったデータを可視化しています(可視化ページへのリンクはこちら https://hibiya.hylable.com)。そのデータを見ながら鳥を探すイベントも行い、お子さまが自然に親しむ啓蒙(けいもう)活動にもなると感じています。聴覚障害者の方でも楽しめるバリアフリーなバードウォッチングや、自然環境の改善や生物多様性の把握といった新しい取り組みもできるのではと考えています。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
私は大学時代にカエルの合唱の研究をしており、カエルの鳴き声のパターンを数学的に解析・モデル化することに取り組んでいました。その後、企業の研究所で音の技術を活用した研究を続けた後、2016年に起業しました。
私の興味の出発点は、対話への純粋な好奇心です。カエルの合唱では、オスが交互に鳴くことで騒がしさの中でも秩序を保つ現象があり、きちんとした構造があることを知り、それなら人間の会話にも同様のパターンがあるのではないかと考えるようになりました。
調べていて面白かったのは、心理的安全性が高いチームでは発話の機会が均等になりパフォーマンスが向上する一方、短時間のディスカッションでは一人がリードして進めた方が成果が出やすいとの違いが観察できたときです。
起業については、博士課程への進学を決めた時が転機でした。コンピューター系の学生は修士過程を修了して就職するのが一般的ですが、その道から外れたことで「せっかくなら面白いことをやりたい」と思い、起業に興味を持つようになりました。
「たまご型デザイン」の意外な効果
仕事におけるこだわりを教えてください。
「誰もやっていないことをやる」ということを大切にしています。
会話分析では一般的に文字起こしやテキストでの記録が主流ですが、私たちはあえて音声認識には頼らず、発話の量やタイミング、会話のバランスなどを分析する独自のアプローチを取っています。これにより既存の音声認識市場とは異なる分野で価値を提供できると考えています。
会社経営において重視するのはチームワークです。自社の会議でもこのシステムを活用して発話量を均等に保つようにしており、例えば発話量の平均値から±2ポイント以内に収めることを目標にしたり、発話量が少ないメンバーには少なくとも最下位から脱出することを意識してもらったりしています。
話せない人だけが頑張るのではなく、チーム全員が協力して発言しやすい環境を作ることができ、結果的に円滑なコミュニケーションが生まれていると感じています。
起業から今までの最大の壁を教えてください
先ほど述べたように、当社は既存のサービスとは異なるアプローチを取っているため、最初は「発話量だけを記録するのではなく、会話の質も重要では?」といった指摘を受けることも多く、説明が難しい部分がありました。「テキストに頼らない会話分析の価値をどのように説明するか」 が大きな課題でした。
デバイス開発にも多くの試行錯誤がありました。当初はマイクとデータ記録装置が別々でしたが、設定の手間や機器の扱いが煩雑になるため、一体型のデバイスへと改良を重ねました。
音の反射を防ぐためにデバイスの形状をたまご型にしたことで、子どもが機器を投げたり乱暴に扱ったりしないという予想外の効果もありました。卵の形をしていると「割れるかもしれない」との心理的なイメージが働くようで、自然と優しく扱われるようになり、結果的に耐久性の向上にもつながっています。
次の課題としては、個々の行動や発言パターンの分析を長期的に蓄積することで、組織文化やチームの特徴を明確にすることが挙げられます。例えば、ある企業では「上司が来ると静かになる文化」なのか、それとも「上司が来ると活発に意見交換が行われる文化」なのかをデータで把握できるようになると、求職者が自分に合った企業文化を選ぶ際の指標になったり、チームの特性を改善するヒントになったりする可能性があると考えています。

体育の授業でも会話分析
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
新しい事実がわかることだと思います、これまで見えなかったコミュニケーションのパターンが明らかになり、「発話量や会話の構造をデータとして捉えられる」 点に大きな魅力を感じています。
特にうれしいのは、私たちの研究成果が他の研究者にも活用されていることです。大学の教授などが当社の技術を使い、自分たちでデータを集め、研究を進めて発表してくれました。単なるツールではなく、研究の媒介としての役割を果たしていることが、大きな達成感につながっています。
意外なことに、体育の授業で活用した例もあります。最近の体育の授業では話し合いも重視されており、例えば新潟のある小学校では、体育の授業の中でチームのフォーメーションや戦略を話し合う時間が設けられているといいます。運動が得意な子ばかりが発言するのではなく、観察力の高い子や、普段あまり話さない子にも意見を求めるといった使い方が印象的でした。データを見ながら、「この子は話す量は少ないけれど、実は最適な判断をしているかもしれない」とわかるのです。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
現在はオフィスや人が集まる場所の分析が半分、学校や研究向けが半分、といった状況です。計測ツールとして使ってもらい、どう活用できるかを見つけていくフェーズなので、とにかく試してもらい、その中でうまくいきそうな活用方法を探っています。
今後の展開として、生物の可視化も面白いと思っています。例えば、森や離島全体を可視化すると、その地域にしかいない固有種が見えてくるかもしれないし、一見ありふれた生物でも、このエリアにだけ異常に多いことが分かるかもしれません。そういう生物のデータを見ていくことにとても興味があります。

切り口変えれば、見え方が変わる
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
方向転換や路線変更などを意味する言葉に「ピボット」がありますが、まったく違うことをやるよりは、技術はそのままに使い方を変える方がいいと思います。
そうすれば技術の蓄積もできるし、新しい展開もしやすい。当社は同じ技術を人間にも使うし、動物にも使います。同じ技術にこだわり、さまざまな場面に展開していけば、技術系のベンチャーはうまくいくのではないでしょうか。
御社に興味がある人に一言お願いします
ベンチャーの文脈で言うと、スタートアップの採用に使うのも面白いと思います。カジュアル面談と社長面談では振る舞いが違うはずで、その違いをデータで見える化できれば、「社長の前では緊張して話せなかったけど、チームの中ではしっかりやれる」ことが明らかになるかもしれません。ベンチャーキャピタルが投資先の面談データを記録、分析するお手伝いもできると思います。興味のある方はぜひお声がけください。
▽お問い合わせはこちらから
https://www.hylable.com/contact/

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:水本 武志氏
2006年に大阪府立工業高等専門学校を卒業し、2013年に京都大学大学院 情報学研究科 知能情報学専攻 博士後期課程修了。 博士(情報学)。カエルの合唱とロボットの合奏に関する研究を行う。その間、学振特別研究員 DC2 採用、LAAS-CNRS (仏) 滞在。 2013年4月から(株)ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパンリサーチャー。 2016年11月より現職。
企業情報
|
法人名 |
ハイラブル株式会社 |
|
HP |
|
|
設立 |
2016年11月21日 |
|
事業内容 |
メディア信号処理やコミュニケーションに関する商品やサービスの 企画・製造・運用・販売・情報提供・コンサルティング等 |
関連記事