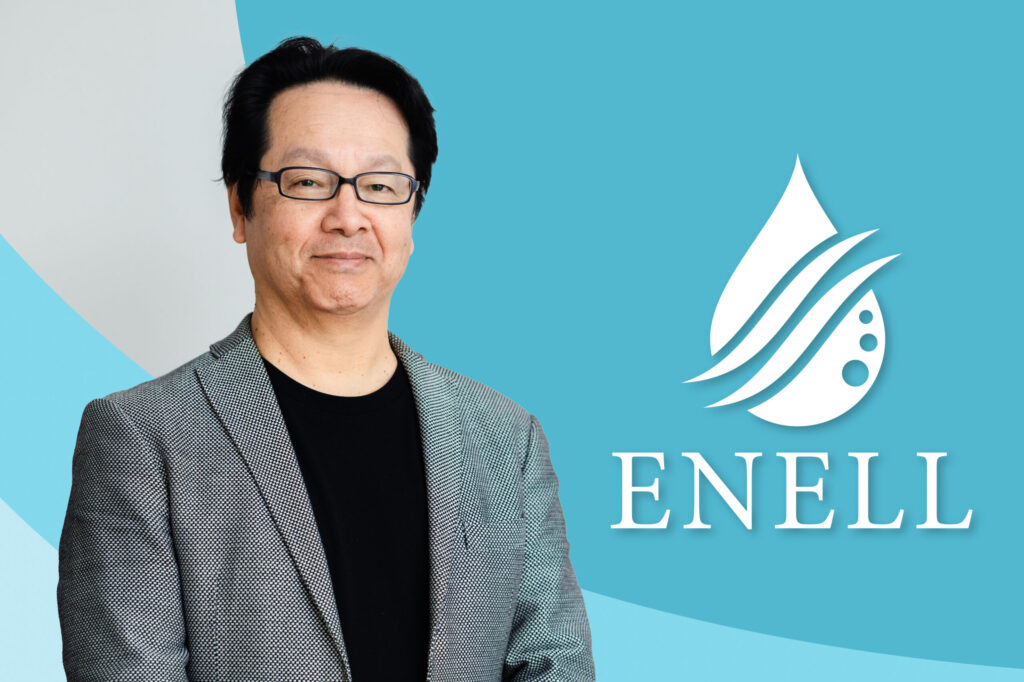【#398】プロンプト不要で直感的に操作できるAIプラットフォームが、生成AIを民主化する|代表取締役社長 木本 東賢(株式会社SUPERNOVA)

株式会社SUPERNOVA 代表取締役社長 木本 東賢
大人向けの学習漫画事業「Learning Toon」で創業した株式会社SUPERNOVAは、現在生成AIプラットフォームのサービスで業界の注目を集めています。同社のサービスの特徴は、プロンプトの知識がない人でも簡単に操作できる設計と、月額980円からという手頃な価格です。「初心者でも使える生成AIサービスであること」を重視したという代表取締役の木本東賢氏に、詳しい事業内容や新しいBtoBサービスについてお聞きしました。
生成AIを活用した学習漫画と、誰でも手軽に使えるAIプラットフォーム
事業の内容をお聞かせください
弊社は現在AIに関連した2つの事業を手がけています。
1つが創業時から続く、大人向けの学習漫画事業「Learning Toon」というサービスです。プロの漫画家と生成AIの力を掛け合わせたオペレーションで、クオリティとスピードにおいて群を抜いたサービスを提供しています。
具体的には、決算やお客様向けのプロモーションマンガ制作の受託と、企業の研修用資料としてのオリジナル漫画コンテンツの制作です。
よくハラスメント研修などではスライドを用いた研修やケーススタディがありますが、登場人物の心情描写に優れた漫画を資料とした方が、被害者側の心情理解が深まることもあり、研修満足度や理解度、行動変容も向上する傾向にあります。
この「Learning Toon」の事業は立ち上げから順調に黒字が続いており、そこから派生した現在のもう1つの主力事業、生成AIのプラットフォーム「Stella AI」が生まれました。
「Stella AI」は誰もがもっと簡単に、もっと便利に生成AIを使える世界を目指したプラットフォームです。従来のように面倒なプロンプトを入力せずとも、プラットフォーム内に内蔵されている豊富なテンプレートから用途に合ったものを選んで、生成AIを動かすことができます。
また現在は新しい生成AIの有料サービスが次々と登場していて、一体どれを契約すればいいのか選べない方も多いと思いますが、「Stella AI」なら月額980円から複数の生成AIモデルの機能を使うことができます。プロンプトが不要なだけでなく、コストの面でも使いやすさを追求した優れた製品となっています。
一般ユーザーの方の「Stella AI」の使い方で増えてきているのは、文章をドラッグして選択するとワンクリックで翻訳や要約ができる拡張機能「Stella Extension」です。ブラウザの場合、Webサイトを見ていて翻訳などが必要になったときに、その都度別にAIのツールを立ち上げる手間が省けます。
この「Stella AI」は現在BtoBのサービスも始まっており、新しくグループ機能を提供します。これによって業務で有効なテンプレートを全社で共有したり、社内のマニュアルをアップロードし、分からないことがあればAIに質問して回答を得られたりすることができる使い方ができます。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
前職では大手通信事業の企業に勤めており、そこで新規事業の社内コンテストを企画・運営する仕事を任されたことがきっかけだったと思います。
せっかく事業化ができそうになっても、そのタイミングで自身の部署に異動になったり、事業が子会社化されたりして、モチベーションの観点で結果的に何人かが離脱していく光景を見てきました。その状況が非常にもったいないと感じたため、事業のアイデアを持った人材がマイナー出資で会社から独立できる制度を作った経緯に至ります。
具体的には、会社からの出資は15%未満で後はVCなどから資金調達をするシステムです。起業家は最初は出向という形で、以前と同じように給与を受け取りながら事業立ち上げに取り組み、失敗しても会社に復帰できるセーフティーネットが用意されています。優しすぎると言われることも多いですが、そうでもしないと挑戦者が増えないのも事実です。
私自身、経営者になることなど元々はまったく考えておりませんでしたが、自ら作ったこの制度を活用して事業立ち上げに乗り出しました。制度はできたので、あとは成功事例を作ってワークさせていくのが次のミッションだと考えています。
最初は10個程度の事業案を検討していて、その中で子ども向けのニュースキュレーションメディアなどを考えていましたが、ユーザからの評価は低い状態でした。ただ、インタビューをする中で子ども達が学習漫画に夢中になっているところにヒントを得て、学習漫画の市場に目をつけたのです。
ちょうどその頃、生成AIのサービスが広まってきていました。そこで漫画制作のオペレーションをAIで効率化して、スピーディーにプロダクトを生み出せる「Learning Toon」が生まれました。
「Stella AI」は元々は「Learning Toon」の機能の一部として開発を始めたサービスです。
漫画のキャラクターと対話して学べたら楽しいだろうというのが、当初の構想でした。それが単体の生成AIサービスとしても事業化できる可能性が見えてき、そのタイミングで完全に独立を決めました。そして前職の会社に業務提携を持ちかけて、「Stella AI」としてサービス提供を開始しました。
「Learning Toon」や「Stella AI」を形にできたことも大きかったですが、元の職場で起業のハードルを最小限にした社内起業システムを作ったことも、自分としては意義のある仕事だったと思います。毎年かなりの応募があって、私含めすでに6組がスタートアップとして独立も果たしました。今後も多くの社内事業家がこの制度を利用して活躍してほしいです。
意識しているのは、初心者にも使いやすいサービス
仕事におけるこだわりを教えてください。
常に意識しているのは、初心者の人にも使いやすいサービスにすることです。生成AIについての知識やスキルレベルは人によってかなり異なり、誰もが満足するサービスを作るのは容易ではありませんが、我々がサービスを設計するときは初心者の方々を取り残さないように気をつけています。
その一方で、AIを使いこなしている人たちの満足度を高めるためにも、常に各モデルの最新機能をチェックして自社サービスに取り込んでいく努力も必要です。
a生成AIに関するニュースをすべてチェックし、後は実際に自分で手を動かして機能を使ってみることの繰り返しになります。有料版と無料版の違いなど、自分で使ってみなくては分からないことも多いのが生成AIであるため、そのような努力は今後も続けていかなくてはならないと考えています。

起業から今までの最大の壁を教えてください
一番大変だったのは、前職の大手通信事業の会社との業務提携を進めていた時期です。自社のプロダクトを作りながら業務提携の枠組みも考えなくてはならなくて、この頃はメンバー全員が本当にハードな働き方をしていました。
ただ、その後のサービス開始から運用のフェーズに移ったところでは、弊社はかなりスピード感を持って走ることができたと思います。事業化と資金調達、新しいサービスのスタートに伴って組織も拡大していくという、普通の企業であれば何年もかかる工程を短期間で成し遂げました。この頃は、組織としても大きく成長できた重要な時期だったと思います。
「次はきっとこんなことができる」というワクワク感
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
シンプルにこの仕事が面白い、というのが一番のモチベーションです。
このように生成AIに関わる事業をやっていると新しいことが知れて、さらに実際に自分の手を動かして使ってみることで、ニュースで得られる情報以上の気づきがあります。
自分自身ができることの幅も広がっていきますし、「こんなことができた」から「次はきっとこんなこともできるはず」という毎日を、従業員も皆楽しんでくれているのではないかと思っています。
現在弊社ではエンジニアやカスタマーサクセスを募集していますが、これらの職種も今後はAIを前提とした働き方になっていくでしょう。昨日までは正しかったことが、明日には間違いになっているかもしれません。そのような時代には、常に最前線でAIを使い続けて自分自身をアップデートしていくことが重要です。
弊社では当然ながらAIを使用した働き方が前提なため、そのような成長の環境は提供できると思います。ご興味を持たれたら、ぜひご応募ください。

今後やりたいことや展望をお聞かせください
AIを使えない人がAIを使えるようにすること、というのが弊社が企業として今目指しているところです。AIを使うことで何かができるようになる、そこから「もっとやってみたい」と思って次のアクションにつながる、そのような行動変容を促せる存在でありたいと考えています。
そのために、もっと色々な人にまずはAIを使ってもらわなくてはなりません。日本人の個人のAI利用率は9%というデータもありますが、他国では50%以上が当たり前のようにAIを使っている中で、このギャップはやがて国際競争力の違いとなって表れてくると思います。
全ての仕事がAIが前提となる世界で、価値観もすごいスピードで変わっていきます。そのようになると教育のあり方から変える必要がありますが、そもそも大人がAIを使っていないと危機感を持つことすらできないと考えています。
そのため、まずは1人でも多くの人にAIを使ってもらうことが大切で、弊社はその第一歩のために力を尽くしています。タップ数を1つでも減らすなど、ハードルを下げることで初めての生成体験をしてもらおうと今も試行錯誤を続けています。
常に新しいことを考えて、新しいことに触れて
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
起業を考えているのであれば、常に新しいことを考えて、新しいことに触れ続けることが大切だと思います。
「世界の動向が今どうなっているのか」を知っておかないと、自分の身の周りだけで課題感を持っていても、それ自体が世間とズレていることもあります。自分の周辺の世界で完結していると新しい情報が入手しづらいと思いますが、今の時代はインターネットもAIもあります。まずは主体的に情報を取りに行くところから始めてみてください。
私個人としても、新しいものを調べるだけでなく実際に体験して価値観を更新していくという作業は常に大切にして欲しいです。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:木本 東賢氏
1989年1月生まれ。2011年4月にドコモに入社。
料金戦略・料金プランの策定などに従事し、料金プラン「ギガホ」「ギガライト」や、2021年度グッドデザイン賞を受賞した「ahamo」の起案者。
事業のスピンアウトを可能とする「docomo STARTUP」を立ち上げ、生成AIを活用した学習マンガ事業「LearningToon」で、ドコモからスピンアウト。
スピンアウトから約半年後に生成AIプラットフォーム「Stella AI」を開始し、ドコモと業務提携を通じて生成AIの民主化を加速させる。
企業情報
|
法人名 |
株式会社SUPERNOVA |
|
HP |
|
|
設立 |
2024年1月11日 |
|
事業内容 |
|
関連記事
RANKING 注目記事ランキング
- 【#578】赤ちゃんの感情を可視化するAIアプリ『あわベビ』で、産後うつの課題を解決|代表取締役・CEO 中井 洸我(株式会社 クロスメディスン)起業家インタビューインタビュー

- 【#544】保護犬・保護猫の命をつなぐ。福祉と仕組みづくりで、寄付に頼らず築く持続可能な社会|CEO / 代表取締役 伊東 大輝(株式会社ANELLA Group)起業家インタビューインタビュー

- 【#268】定年齢層向けイベントアプリ『シュミタイム』で、高齢者の社会的孤立を救う。|代表取締役CEO 樗澤 一樹(株式会社ジェイエルネス)起業家インタビューインタビュー

- 【#468】意見が政策につながる社会へ。市民参加型SNSと自治体向けAIで「デジタル民主主義」を推進|代表 伊藤あやめ/谷口野乃花(Polimill株式会社)起業家インタビューインタビュー

- 【#186】日本の漫画やアニメを世界に広め、「生きる希望」を与えていく|代表取締役会長 保手濱 彰人(株式会社ファンダム!)起業家インタビューインタビュー