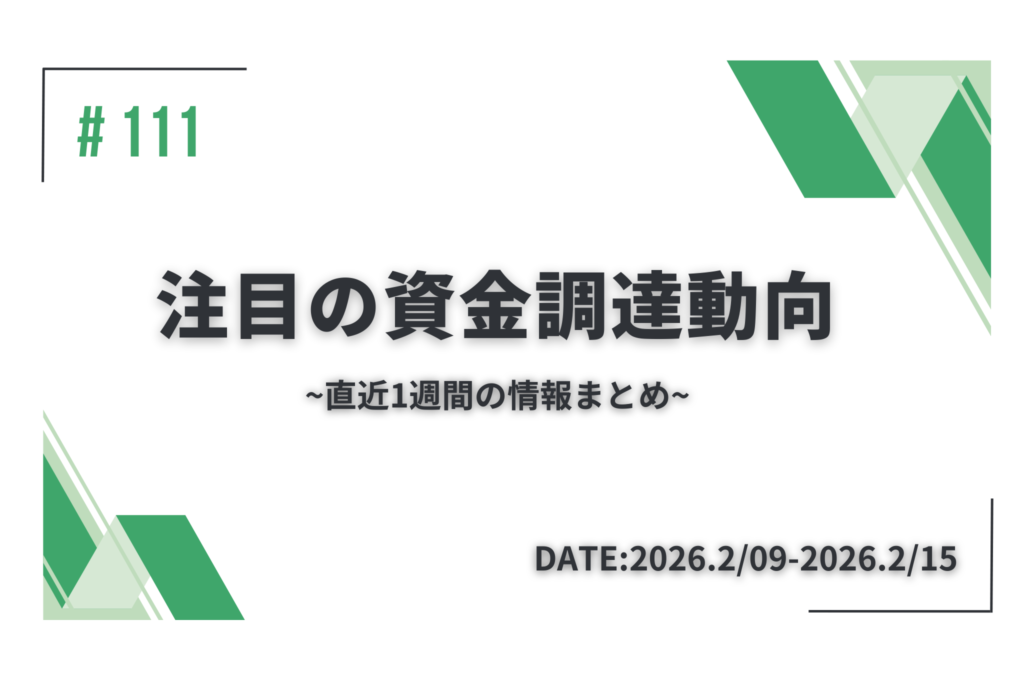【#401】経済予測AI『xenoBrain』 不確実な時代に企業経営を支える新たなスタンダードを目指す|代表取締役社長 関 洋二郎(株式会社xenodata lab.)

株式会社xenodata lab. 代表取締役社長 関 洋二郎
株式会社xenodata lab.は、AIを活用した世界初の経済予測プラットフォーム「xenoBrain(ゼノブレイン)」を運営しています。大量の経済指標をAIを使い分析し、原材料価格や為替、市場需要など、企業の経営判断に必要な未来予測を提供しています。代表取締役社長の関 洋二郎氏に、事業内容や今後の展望なども含めて詳しくお聞きしました。
企業の経済意思決定をサポートするAI経済予測
事業の内容をお聞かせください
私たちは、AIを活用した経済予測サービス「xenoBrain」を提供しています。例えば「鉄鋼価格が今後どうなっていくのか」「為替はどうなるのか」「工作機械の受注は増えていくのか」といった経済指標について、AIが予測を行い、ユーザーは検索するだけで予想結果や分析結果を簡単に見ることができます。
従来の経済予測では、多くの企業が調査業務に時間を費やし、さまざまなデータを見て分析していました。それをAIが自動で「次はこうなるだろう」といった予測を提供しています。
現在の顧客は、ほとんどが大手企業です。導入理由として多いのは、DXの推進と不確実性への対応です。人の手で行っていた予測業務をAIで代替することで、業務の効率化ができます。また、大手企業は新技術への投資余力があり「AI活用が進む中で、自社も取り入れてみよう」といった考えから、導入が進んでいます。
お客様からは様々な評価をいただいておりますが、今のところ新しい概念のサービスとしては良い評価をいただいています。xenoBrainの特徴として、数万の経済指標や数千万本のニュース記事を学習しており、経済動向の影響から決定されるような指標において中期的な動向を予測することについては精度は高いです。例えば、工作機械の受注や半導体の販売などはまさにそのようなケースです。逆に、経済動向とは関係なく人為的な期待で形成される相場となると、瞬間的には難しいということもあります。
しかし全体的には従来の「人と経験と勘」による予測をAIに置き換えることで、業務の効率化ができているといった声をいただいています。
具体的な実績を教えていただけますか?
我々の価値提供としては、1つは業務効率化、もう1つは予測を用いて利益の最大化をもたらすということです。
業務効率化については、幅広い品目の予測が必要な化学メーカーなどの製造業で、顕著な効果が出ています。これまでExcelで関数を組んで手作業で行っていた予測作業が、AIによるデータ解析に置き換わったことで、大幅な時間短縮とリソース最適化を実現できています。
ですが、私たちが目指しているのは、単なるコスト削減ではなく、正しい経営判断による顧客企業の利益向上です。しかし、この点については具体的な数字を挙げて「xenoBrainを利用してこれだけ利益が出ました」と言いにくい側面があります。
というのも、実際のところ、企業は私たちの予測をそのまま使うよりも、「AIではこういう予測が出ている」「市場ではこのような話がある」といった複数の情報を総合的に判断して意思決定を行っています。最終的には人の判断が入るため、その成果を「すべて私たちのおかげ」と言い切れない部分があるのです。
本来であれば定量的な効果測定をしたいところですが、現状では顧客からの評価やコメントといった定性的なフィードバックが中心となっています。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
大学時代、経済を学んでいたため、その知識を生かして社会に貢献したいと考えていました。当時は何をしたいのか、何をすべきかわかっていなかったのです。慶應義塾大学では「法学部は弁護士、経済・商学部は会計士」といった流れがあり、それに習い会計士を目指しました。
途中で「これが自分のやりたかったことなのか?」と迷いましたが、「合格してから考えよう」と踏ん張りました。大学在学中に試験に合格できたものの、勉強に集中しすぎたあまり、就職活動の時期を逃してしまったのです。結果的に監査法人以外に選択肢がなく、監査の世界に足を踏み入れることになりました。
監査法人では、ITの統制にも関わりました。会計士合格後「次の時代は英語・IT・デザインだ」と書かれた本に影響を受け、財務に加え英語とITを身につけたいと思い、国際的でIT部門にも会計士が入れる監査法人を選びました。
その後、経済データベースサービス企業で働いていましたが、何年か経過したころこの環境でやれることはやりつくしたと感じるようになりました。特に最後の半年は燃え尽き感があり、部署異動の話が出た際に引き継ぎをしたところ、同じ新しいことをやるならば起業して新しいことをやっても良いのではないかといった思いが芽生えました。
その程度の判断だったので起業のタイミングは、突発的で準備はゼロの状況でした。事業内容は固まっていませんでしたが前職で事業開発をやっていたこともあり業界動向は常に追っていたので、事業アイデアの候補はいくつかありました。
2015年当時、AIはまだ一般的に「SF的な話」といった認識でしたが、私は「確実に来る」と考え、会計士としての経験と経済データの知識を活かせる「経済データ×AI」の領域に焦点を当てたのです。
正解は自分しか知らない
仕事におけるこだわりを教えてください。
人のアドバイスに頼らず、自分で考え抜くことです。
起業して3年ほどは、人のアドバイスを聞き過ぎていたと反省しています。当時は、先輩起業家や投資家からのアドバイスを素直に受け入れ、試していましたが、多くのことでうまくいきませんでした。
コロナをきっかけにそんなアドバイスをする人とも接点が全くなくなり、と同時にこれまでのアドバイスのほとんどがこの環境下で役に立たないと気づきました。この時に、「この事業をこの時代にやっているのは私だけ」と気づきました。事業環境も時代も違う状況では、他人の経験はほとんどが役に立たないとようやく気づくことができました。
それ以降、困難に直面した時ほど人のアドバイスや誰かのありがたい言葉に頼るのではなく、とにかく自分で考えるようにしました。経営の答えは世の中どこにも落ちてないし、自分たちの頭の中でしか導けないと覚悟し、不都合なことでも事実を整理し、徹底的に考え抜く方針にシフトしました。
他人に意見を求めないというと危険な経営者に映るかもしれませんが、「このタイミングのこの課題は自分しか持っていない」といった認識から、自分が最も正解に近いはずだと考えるようになってから、さまざまなことがうまく回り始めました。
起業から今までの最大の壁を教えてください
AI研究開発の不確実性と、それに伴う時間とコストの増大です。
私の頭の中には、起業前に勤めていた会社での開発経験の感覚がありました。当時はエンジニアと一緒にものを作って売る、具体的にはサーバーの開発をして、画面を作って売るといったプロセスでした。しかしAI分野では、その一歩手前に研究開発という段階が必要になります。この部分を完全に甘く見ていたのです。
最初のリリースは2019年で、会社設立の2016年から約3年かかりました。リリース後、売上や技術をアピールして資金調達を行い、さらに研究開発に投資するといった循環を繰り返して今に至ります。

誰もが安心してAI予測を利用する社会へ
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
チームの存在です。
何度も困難に直面し「会社を手放すしかないのか」と考えたこともありました。しかし、これほど素晴らしい、尊敬できる社員を集めることは二度とできないだろうと思ったことが、最後の最後の踏ん張りになりました。彼らの頑張りを不正解にしてはいけない、そういった気持ちが、危機的状況の中でも踏ん張る力となりました。
組織づくりでは、企業理念やバリューなどを意図的に作っていません。バリューは策定方法を間違えると経営陣の考えを押し付けることになり良い面悪い面のある難しい概念かと思います。弊社では思いやりを持とうですとか、誠実でいようですとか時代を超えても変わらない普遍的な善悪や道徳観があれば、それ以上をルールとして定める必要はないという考えで会社を運営しています。
これは私が優れた道徳観があるとか、私の理念に社員が共感しているということではなく、現在の社員一人ひとりが元々持ち合わせている優れた人間性から発言されていっているものであり、それを経営側が継続的に体現していくといった発想です。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
まずは経済予測という体験を、大手企業の経営層に広く浸透させていきたいと考えています。そして、その先を見据えているのは、中小企業や個人も含めた高度な経済予測AIを民主化していくことです。
これまでこの分野では優れた技術革新は大資本をもつ企業でしか享受できない時代でした。経済予測AIも大企業の経営判断だけに留めておくのではなく、個人や中小企業でも手軽に利用できる環境を整えていきたいと思っています。最初からそちらを狙うとビジネスモデルとして難しい面があるため、現在は大企業から取り組んでいます。
例えば個人投資家が「株価が今後どうなるだろう」と思った時に、私たちのプラットフォームでAIによる信頼性の高い予測が確認できる。国内ではそういった形で浸透させていき、その後は海外展開も視野に入れています。

事業ドメインを明確に設定する
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
まだ成功者でもない私が言うのはかなりはばかられますが、少し自分の考えをいうなれば事業ドメインの選択は、時間をかけて徹底的に行うことが良いと思います。
私が甘く見ていた部分ですが、それがビジネスがスケールするかどうかを90%以上決めます。もし会社を大きくしたいという野心がベースにある場合、「やりたいこと」と「儲かること」は全く別物だと捉え、事業ドメインを真剣に考えることが、起業で最初に一番時間を使うべきところだと思います。
資金調達については焦る必要はなく、また焦らなくてよい環境を作ることが重要だと思います。起業直後はお金がなくてもなんだかんだ存続できるケースが多いです。そして、投資家やパートナー選びにはこだわりを持ち、シード段階では多くの選択肢を検討し、最適と思えるまで粘ることが重要かと思います。シード期のミスは最後まで尾を引くと思います。弊社は運よくシードにミスは無かったパターンでしたが、周りの話を聞くとゾっとすることも多くあります。
あとは、コスト管理です。資金調達に成功すると気が大きくなり、コストに対する意識が甘くなりやすいです。「資金を調達したから使わなければならない」と思いがちですが、当たり前ですが無駄なコストはかけるべきではないです。起業初期は気持ちが前のめりになりやすいので、注意が必要なのだと思います。
貴社のサービスに興味がある投資家や企業へのメッセージをお願いします
当社が最も大切にしているのは信頼関係です。どれだけ技術が進化しても「絶対に当たる」ことがあり得ない世界で、オーソリティと信頼性が何よりも重要になります。そのため私たちは、過剰な広告や誇大な表現を避け、誠実に技術開発と研究に注力してきました。
経済の予測に関しては、どう考えても人間に勝機が少ないジャンルであり、ほぼ確実に「AIによる経済予測」が当たり前になる時代が到来すると確信しています。これは私たちが成功しようと、しまいともその未来になると思っています。もちろん、その時には中心に私たちがいることを目指していますし、最も良い位置にいるのは我々だと思っています。
生成AIが先に注目を集めましたが、予測AIについては今まさに爆発的な普及の入口一歩手前まで来ています。今後の流れを考えると、私自身、非常に楽しみです。私たちのサービスに関心をお持ちの投資家や企業様がいらっしゃいましたら、一度ご連絡ください。
▽お問い合わせはこちらから
https://www.xenodata-lab.com/contact

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:関 洋二郎氏
慶應義塾大学商学部在学中に公認会計士2次試験に合格し、在学中よりあらた監査法人(現PwCあらた監査法人)にて、メーカー、小売り、卸売業を中心に上場/未上場企業の財務諸表監査、内部統制監査などの公認会計士業務のみだけでなく、システム監査、データ監査業務など、IT統制にも従事する。2012年に株式会社ユーザベースに入社し、アジア最大級ビジネスプラットフォームであるSPEEDA事業の事業開発部責任者として、国内外の市場環境調査、プロダクト戦略の立案、データサプライヤーとのアライアンス、仕様設計、リリース検証、本番運用の一連のプロセスについての執行を担当。また、2013年にはユーザベース全社員投票により選出されるMVPを受賞。
企業情報
|
法人名 |
株式会社xenodata lab. |
|
HP |
|
|
設立 |
2016年2月12日 |
|
事業内容 |
経済分析特化のLLMを駆使した経済予測AIプラットフォーム「xenoBrain」を運営 |
関連記事