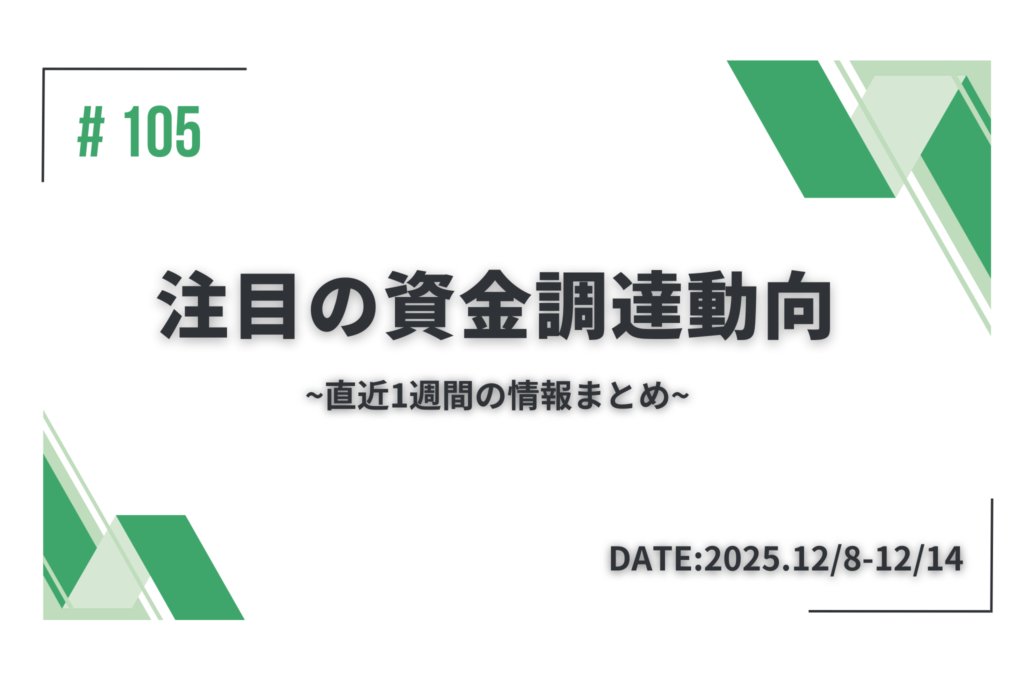株式会社emome 代表取締役 森山穂貴
高齢者施設のレクリエーションクラウド「シニアカレッジ」や、施設内での買い物サポートサービス「SATIMER」などを展開する株式会社emome。介護を通じて日本の未来を明るくしたい、と挑戦を続ける代表取締役の森山穂貴氏に、事業の原点やこだわり、今後の展望について伺いました。
枠にはめず、つながる。介護現場から描く理想の高齢社会
事業の内容をお聞かせください
弊社は、高齢者の生活を豊かにするため、高齢者施設を支援するクラウドサービス事業の開発や展開を行っています。グループ会社が介護事業所を24拠点ほど運営しているので、現場の声を聞きながらプロダクト開発に取り組んでいます。
最初にリリースしたのが、介護施設内のレクリエーション時間に活用できる動画のプラットフォーム「シニアカレッジ」です。現在は800本ほどのコンテンツを提供しており、職員が独自に企画を考えなくても、質の高い時間を提供できる仕組みとなっています。
また、百貨店などと連携し、高齢者が施設にいながら商品を購入できる「SATIMER」も展開しています。従来、生活必需品の購入機会はある程度充実していましたが、娯楽としてのショッピング体験は十分に提供されていませんでした。そこで我々は、ショッピングを「エンターテイメントアクティビティ」と捉えてサービスに実装しています。
「シニアビジネスオープンイノベーションラボ」では、新たな商品を一から開発するのではなく、既存の商品の届け方に着目し、ご自宅への配送やサブスクリプションでの購入の仕組みの提供を行なっています。
さらに、国内に約30万ある介護事業所のデータベースを構築し、検索性や集客力を高める取り組みも進めています。これと連携するかたちで、介護士向けのメディア「クレセント・オンライン」も展開しています。
介護業界は、「こうあるべき」という固定観念が強い産業です。もちろん大切にすべきルールはありますが、行動を制限するのではなく、業界の固定観念を問い直していけるような情報発信をしていきたいと思っています。

高齢社会の課題をどのように捉えているかお聞かせください
高齢者の方々は、時間に余裕があります。その過ごし方は一人ひとり異なり、「こうあるべきだ」と一括りにできるものではありません。むしろ、これまで高齢者の過ごし方を一括りにしてきたことが、生活を豊かにする妨げになっていたのではないかと考えています。
「旅行に行きたい」「甘いものを買いやすくしてほしい」という個別の想いに対し、我々は独自のリソースや他企業との連携を通じて応えています。
我々が重視しているのは「コミュニティ」の力です。介護は「する側・される側」という一元的な関係を生み出してしまうものです。今後、働き手が減少していくなかで、共助の関係性をどう築くかが非常に重要だと思っています。
例えば、我々が運営している「サロン」と呼ぶデイサービスでは、職員が積極的に介入するのではなく、利用者同士のコミュニケーションを促す設計をしています。その結果、サロンの利用日以外でも連絡を取り合う関係性が生まれ、自然なつながりが育まれています。
新たな施設を建てて閉鎖的なコミュニティをつくるのではなく、既存の都市インフラに共助の関係性を育んでいくことが、理想的な社会の在り方だと考えています。特に、自然発生的にコミュニティが育ちにくいニュータウンやベッドタウンにおいて、我々が介入することで、人と人のつながりを生み出す価値は大きいと考えています。
我々の強みは「保険外事業」と呼ばれる領域にあります。社会保障制度が厳しさを増すなかで、介護業界の売上の多くは公的な介護保険に依存しています。こうした背景には、「誰に、どのような価値を届けるのか」というBizDev視点での運営が求められてこなかったことにあります。
そうした中で、我々は既存の形式にとらわれずに、高齢者の生活を豊かにすることを考えてサービスの展開を行ってきました。お客様が喜ぶことを届けてきた結果として、売上の50%近くを保険外収益として構成することができています。
収益の一部を事業所に還元することで、事業所が持続的に運営できる仕組みを整えながら、お客様にもきちんと喜んでいただくことを実現しています。
事業を始めた経緯をお伺いできますか?
私自身、もともと別の事業に取り組んでいたのですが、うまくいかず、体調も崩していました。失うものが何もない状況の中で、介護事業を営む実家から「戻ってこないか」と声をかけてもらったことが、介護の現場に関わるきっかけとなりました。
それまでの私は、他人と自分を比べてしまうことがありましたが、介護の現場に入ってからは、目の前にいる一人の高齢者を笑顔にすることだけを考えて働くようになりました。「自分は誰に価値を届けるべきか」が明確になり、「自分がやらなければならない」と強く思えたことが、この道に進む大きな転機となりました。
介護施設に携わる中で、レクリエーションに対して面白みを感じないことがあり、自分自身でやってみたところ手応えを感じました。これを全国に広めていきたいと思ったことが、シニアカレッジを始めるきっかけでした。
以前手がけていたのはマッチング系の事業でしたが、成果が積み上がっていく実感を得にくいところがありました。その点、シニアカレッジはコンテンツ事業であるため、取り組んだ分だけ成果や資産が形として蓄積されていきます。この実感を持てることも、私がこの事業に参画した理由の一つです。

目の前の一人と、業界全体を見つめる
仕事におけるこだわりを教えてください。
私が大切にしているのは、「誰に対してサービスを届けているのか」を忘れないことです。介護の現場では、初めてお会いする方から「来てくれてありがとう」と手を握ってくださることがあります。一人ひとりに向き合うことの重みを、日々実感しています。
この業界は、日本の財政や社会保障にも直結する重要な分野であり、世界からも注目を集めています。だからこそ、目の前の一人を大切にするミクロな視点と、業界全体を見渡すマクロな視点の両方をもつことが必要だと思っています。
採用においては、能力よりも「人として良い人かどうか」を重視しています。思いやりや礼儀、マナーを持っているかどうかを、最も大切な判断基準にしています。
また、会社運営の面では、「ルールとカルチャーを分けて考えよう」と伝えています。たとえば、定例会議など形式的な場も、日頃から気軽に意見を交わせるカルチャーがあれば不要になることもあります。目標を達成しようとするとき、すぐにルールに頼るのではなく、それをどうカルチャーで解決できるかを皆で考えるようにしています。
起業から今までの最大の壁を教えてください
最近は、エリート起業家と呼ばれる人が増えていると思いますが、私自身も同じような手段をとり起業の道を選びました。心の奥底にあったエリート意識を拭いきれず、他人と自分を比べてしまうことにずっと悩んできました。
体調を大きく崩した時期には、自分がこの社会に何も貢献できていない「無」の存在であると感じていました。何も失うものがないと思えた時から強くなれたと思います。やるべきことがあるだけでとても幸せなことだと、強く感じました。
よく、「年齢の割にしっかりしているね」と言っていただくことがありますが、それは一度立ち止まり、自分自身と深く向き合った経験があるからだと思っています。人は一人で生きているようで、実は人に支えられ生かされている方が多いと思います。
ですが、起業家は自分の力で生きていかなければいけません。そう気付けたことが、私にとって強くなれたきっかけです。

日本発。介護の可能性を世界へつなぐ
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
「今、何をしているのか?」と聞かれたら、「日本から世界に燦然たる産業をつくっています」と答えると思います。実際に取り組んでいることは、おじいちゃんやおばあちゃんの暮らしを豊かにすることですが、その根底にあるのは、「日本に生きる人がもっと明るい未来を描ける社会にしたい」という想いです。
私はこれまで約13年間、香港やシンガポールなど海外で過ごし、日本との差を肌で感じてきました。日本がどう見られているかは、基本的にすべて自分の責任だと考えています。私は一億数千人の一人にすぎませんが、「自分×一億人」の視点で見れば、その力は決して小さくないと信じています。
「日本が明るい未来を描けるまでは、この仕事はやめられない」という思いがモチベーションにつながっています。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
まずは、今取り組んでいる事業を着実に伸ばしていくことです。
日本は、世界に先駆けて超高齢化社会を迎えた国です。そのなかで、ある程度準備できている部分もあり、我々が実践している介護の取り組みは、今後ますます国際的に求められると感じています。
特に、アジア圏には日本の介護を必要としている人たちがたくさんいます。だからこそ、将来的には日本の介護の知見やサービスを、海外に届けていくことに挑戦していきたいと考えています。
自分を知り、道を選ぶ。本当の起業家とは
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
私自身、まだ道半ばですので、アドバイスできることは多くありませんが、会社を立ち上げることだけが起業ではないと思っています。
私はアントレプレナーを、「自分の人生に責任を持ち、自分の人生を自分色に染められる人」と定義しています。社会に大きなインパクトを与えたいという志はとても大切ですが、それを実現する手段は必ずしも会社を立ち上げることだけではありません。
むしろ会社を立ち上げると、自分を表現する以上に、ジレンマやしがらみに直面することも多くなります。本当の意味での起業家とは、自分がどんな人間で、何を実現したいのかを深く理解し、自分に最も合った選択ができる人ではないでしょうか。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:森山穂貴 氏
2002年生まれ。東京大学社会心理学研究室在籍。LINE株式会社にて、プロダクトマネジメントに従事し、トークタブ上部コンテンツの企画・実装に携わる。2023年に株式会社emomeを創立、代表取締役に就任。次世代レクリエーション「シニアカレッジ」や、大企業との事業共創を展開。
企業情報
|
法人名 |
株式会社emome |
|
HP |
|
|
設立 |
2023年4月27日 |
|
事業内容 |
|
関連記事