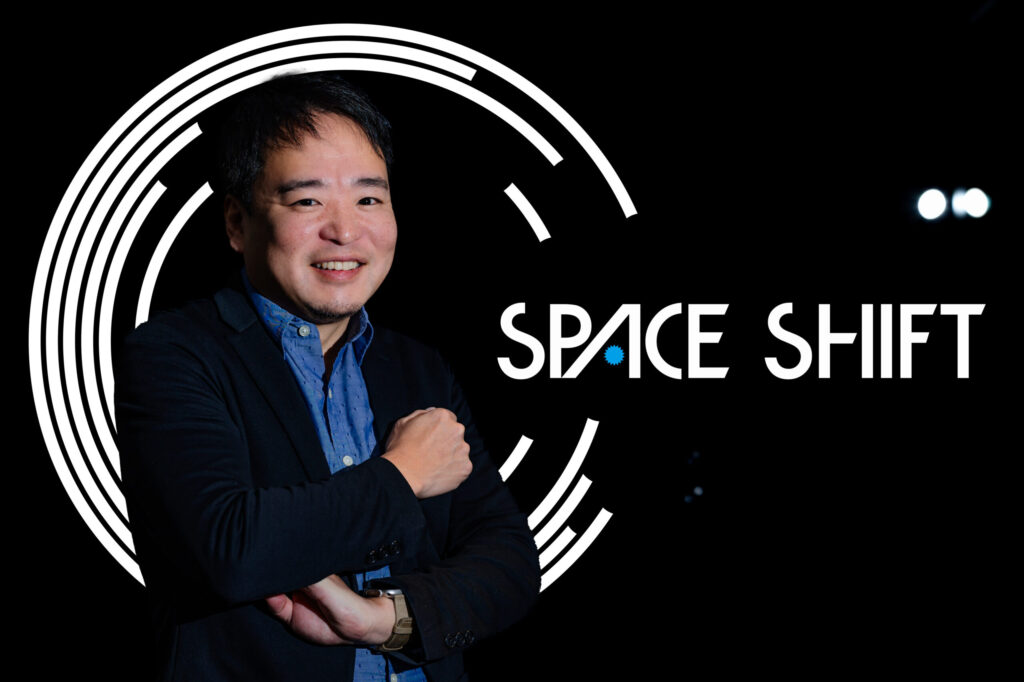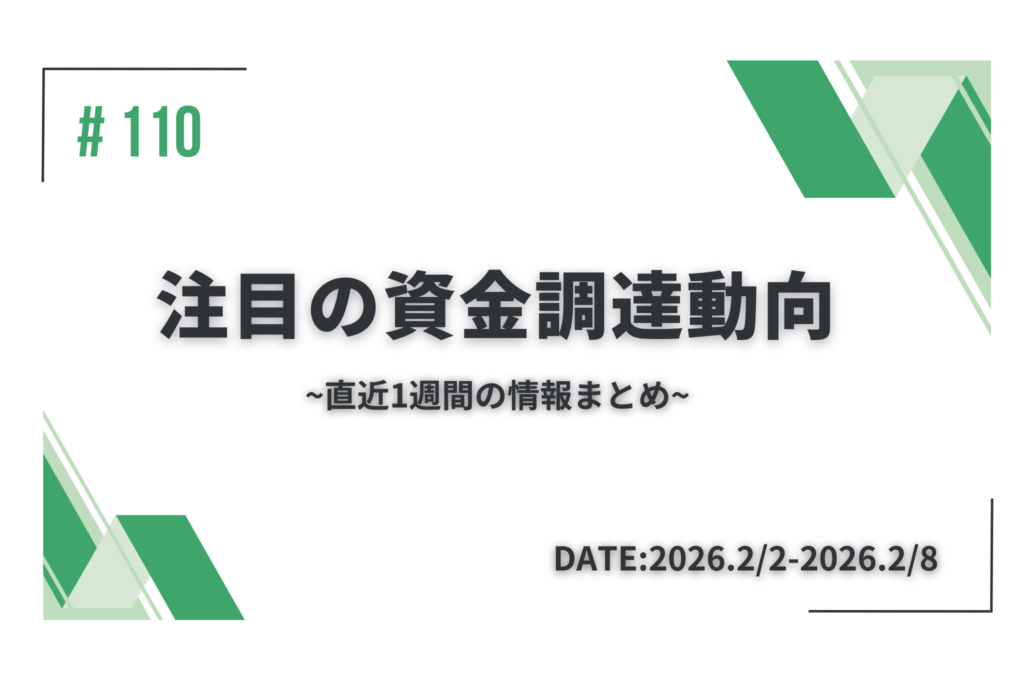株式会社あるやうむ 代表取締役 畠中 博晶
地域課題の解決を目指し、DAOやNFTといったWeb3技術を活用したユニークな取り組みを行う株式会社あるやうむ。主に地方自治体と連携しながら、移住者が地域内外をつなぐ仕組みや、NFTを活用したふるさと納税返礼品など、現場とデジタルを掛け合わせた新しい地域支援モデルを展開しています。今回は代表取締役の畠中博晶氏に、事業の背景や移住支援のあり方、そして今後のビジョンについて詳しくお話を伺いました。
地域の中と外をつなぐ。
事業の内容をお聞かせください
我々は、NFTやDAOの技術を活用し、主に地方自治体と連携しながら地域課題の解決に取り組んでいます。現在は、都市部などから移住した方が移住先と外とをつなぐことを支援するオンラインコミュニティの運営事業を中心に展開しています。
地域には様々な課題がありますが、これまでのように地域内や近隣事業者だけで解決を図るのではなく、遠く離れた場所からでも外部の知見やノウハウを活用できるよう、デジタル上にその土台を整えています。
課題に対してオープンに意見を出し合い、アイデアや交流が生まれるオンライン空間をDAOとして整備し、運営しています。
こうした地域に移住し、DAOのマネジメントに取り組む方を「移住DAOマネージャー」と呼んでいます。興味を持ってくださった方には丁寧なヒアリングを実施し、希望や特性とマッチする地域課題を抱える自治体をご紹介しています。
双方にとって幸せなマッチングとなることを目指しています。国の制度である地域おこし協力隊を活用し、現在は全国で14名(取材時点)ほどが活動しています。
また、もう1つの事業として、NFTを活用したふるさと納税の返礼品に取り組んでいます。アートやチケット、ウイスキーの引換券などをNFTとして提供し、偽造防止や所有証明といった技術の強みを活かして、地域の魅力を届けています。

活動後のキャリアについて教えてください
活動期間は最短で1年、最長で3年ですが、その後のキャリアは多様に広がっています。
たとえば、現場でのオンラインコミュニティの運営経験を活かして、コミュニティマネージャーとして活躍することができます。また、情報発信やSNS運用にも関わっていただくため、そうしたスキルを活かしたキャリアもあります。
実際に役場へ就職したり、地域内の既存事業を引き継ぐ方もいらっしゃいます。地域には様々な課題があるので、月に数十万円の成果を上げられる事業のネタも多く、我々がネタの見つけ方や事業化のアドバイスをすることもできます。
また、産休や育休、介護などで一度キャリアが途切れてしまった方にとっても、この仕事は再出発の良い機会になります。たとえば就職氷河期世代で家族の世話も重なり、希望していた大学進学や就職ができなかった方がこの仕事をきっかけに新しいキャリアに出会えた事例もあり、人生の転換点として大きな可能性を秘めた働き方ができると考えています。
▼地域おこし協力隊DAOの募集はこちら
https://alyawmu.com/chiikiokoshi-dao/
事業を始めた経緯をお伺いできますか?
私は東京で生まれ育ちましたが、19歳のときに東京以外で活躍したいと思い、京都大学への進学をきっかけに滋賀県大津市に移住しました。
大学2回生の頃、仮想通貨やブロックチェーンの世界に魅了され、トレードで一定の資金を得たことで、この先の人生で何をしたいかについて考えるようになりました。
もともと街づくりに関心があったことから、地方政治に関わる仕事に就きたいと考え、一番好きな札幌に移住し、ゆくゆくは政治や行政の面から札幌や北海道の街づくりに携わりたいと思いました。
ただ、政治家になるためには、市役所勤務や政治家の秘書、芸能人、経営者といった限られた選択肢しかなく、その中で私が現実的に目指せるのは経営者だと考え、札幌で会社を立ち上げました。
当初は雑貨などのグッズを扱っていましたが、思うように熱量が続かず、手応えも感じられませんでした。そこで、大学時代から得意としていたブロックチェーンの知識と、街づくりへの関心を掛け合わせる形で、現在の事業に至りました。
NFT事業に着手したのは、ブロックチェーン技術を事業として活かせるチャンスだったからです。仮想通貨は日本の法制度上、個人や小規模な会社では扱いが難しい領域ですが、NFTは電子上の証明書や流通経路としての仕組みであり、比較的規制も緩やかです。
我々でも挑戦しやすい分野だったことから、NFT事業に取り組むことを決めました。

一つの地域にとどまらず、全国へ。時間をかけて築く、共創の土台
仕事におけるこだわりを教えてください。
こだわりは、大きく3つあります。
1つ目は、全国すべての地域で仕事をすることです。地域に関わる事業者の多くは、拠点から近い範囲に活動を限定しており、関係人口や地域のファンを生み出すための取り組みをしている事業も少ないのが現状です。
ただ、新しい取り組みに前向きな方や、外部からのアイデアを受け入れたいと考えている公務員の方は、必ずどこかにいらっしゃいます。そうした方とつながるためにも、全国をどさ回りし、一つの地域に閉じこもらず多くの地域を巻き込む姿勢を大切にしています。
2つ目は、移住候補者を経歴だけで判断しないことです。たとえ気になる点があったとしても、その方が活躍できるかどうかは実際に話してみなければ分かりません。必ず全員と面接でお話しし、書類だけでその人の可能性を閉じないよう心がけています。
3つ目は、事業の本体をフルリモートで運営することです。面白い仕事の多くが東京に集中する中、新たに事業を始めたい方の多くは上京を選びます。だからこそ私は、地方にいて活躍の場が限られている優秀な人たちにも参加してもらいながら事業をつくっていけるよう、フルリモート体制にしています。
また、移住者にとって大切なマインドセットは、焦らないことです。地域のすべての方に理解してもらうのは簡単なことではありません。まずは、その地域で影響力をもつキーパーソンと信頼関係を築き、伴走することで、自然と周囲にも理解が広がっていきます。
そして受け入れ側の地域にも、外部からの意見を尊重していただくよう、事前に共有しています。そのため、大きな認識のズレが起きることも少なく、我々としてはマッチ度が高いと感じています。現時点でマッチングした移住者の中には、途中で辞めた方はおらず、継続的に取り組んでいただいています。
起業から今までの最大の壁を教えてください
自治体ならではの導入タイミングの少なさが壁です。
民間企業との違いとして、多くの自治体では新しい取り組みを導入する際に、議会で予算を可決する必要があります。しかし自治体の予算決定は当初予算の年に1回であることが多く、導入のタイミングは年に1度しかありません。
たとえ話が前向きに進んでいても、地域内で別の事案が発生したことで取りやめとなれば、次の機会はまた1年後になってしまいます。
我々に非がない外的要因によって進行が止まることもあるため、その分、運転資金を長く維持しなければなりません。こうした成約までの長さは他のビジネスにはない事業特性上の壁となります。
成功事例を地方から。未来のローモデルを目指して
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
個人的なモチベーションとしては、地方にいながら成功するロールモデルになることです。東京以外の地域では、若いうちからある程度の規模で挑戦しようとする方が少なく、成功事例も多くありません。
学生ベンチャーやスタートアップの多くが東京に集中するなか、地方にいながら投資を集め、成功事例をつくる生き字引的な存在になることが一番のモチベーションです。
実際に京大や北大に通っていた頃、皆さん頭が良い一方で、東京の学生のほうが圧倒的に多くの情報を持ち、世の中をよく見ていると痛感しました。
だからこそ今は、東京に出なければ何も始まらない、と考える世の中の流れを変えたいと思っています。地方で挑戦しようとする若い方たちが活躍できる資金をつくり、応援する環境を整えることが、私の中長期的なモチベーションです。

今後やりたいことや展望をお聞かせください
今後は、我々の事業をさらに多くの地域へ展開し、来年は30〜40の自治体への導入を目指しています。コミュニティを通じて知見やアイデアが地域に集まり、実際に地域が変わっていく成功事例を全国に増やしていきたいです。
現在の地域社会には、新しい仕組みや息吹を積極的に取り入れていく民間事業者がまだ少ないと感じています。我々は現在、ふるさと納税と地域おこし協力隊の2つの制度を活用していますが、国にはもっと多くの支援制度が存在しています。
そうした制度を柔軟に使いこなしながら、地方を発展させていきたいです。そして、地域ごとの課題に対して最適な制度を組み合わせた支援パッケージを提供していきたいと考えています。
東京に行かなくても挑戦できる。実体験からのアドバイス
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
東京にいる方は起業家支援の仕組みやベンチャーキャピタルについての情報を得やすく、相談先も多いと思います。一方で、地方にいて簡単に東京に行けない方や、今いる場所で挑戦したいと考えている方もいると思います。
地方で学生起業をするときに陥りがちな落とし穴のパターンはある程度決まっています。私自身も遠回りをしながら進んできた経験があるので、地方で起業を考えている方には「それが落とし穴なのか、それとも伸びしろなのか」といった観点から、幅広くアドバイスができると思います。
札幌、秋田、新潟など、地域に根ざして挑戦している仲間も各地にいます。お金の有無に関係なく、意見交換を通じてお互いの事業を育てていく関係性を大切にしているので、お気軽にご連絡ください。ホームページからメッセージを送っていただければと思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:畠中 博晶 氏
京都大学在学中の2017年、両親から渡された教習所代をもとに仮想通貨の裁定取引を始める。 これをきっかけに、ブロックチェーン/仮想通貨の世界にのめり込む。 その後、裁定取引で稼いだ資金で2020年3月に念願だった札幌へ移住し、同年11月に株式会社あるやうむを創業しました。
企業情報
|
法人名 |
株式会社あるやうむ |
|
HP |
https://alyawmu.com/ |
|
設立 |
2020年11月18日 |
|
事業内容 |
自治体向けサイト及びシステムの企画、制作、構築および運営。 NFT・DAO を活用した地方創生コンサルティング・開発 |
関連記事