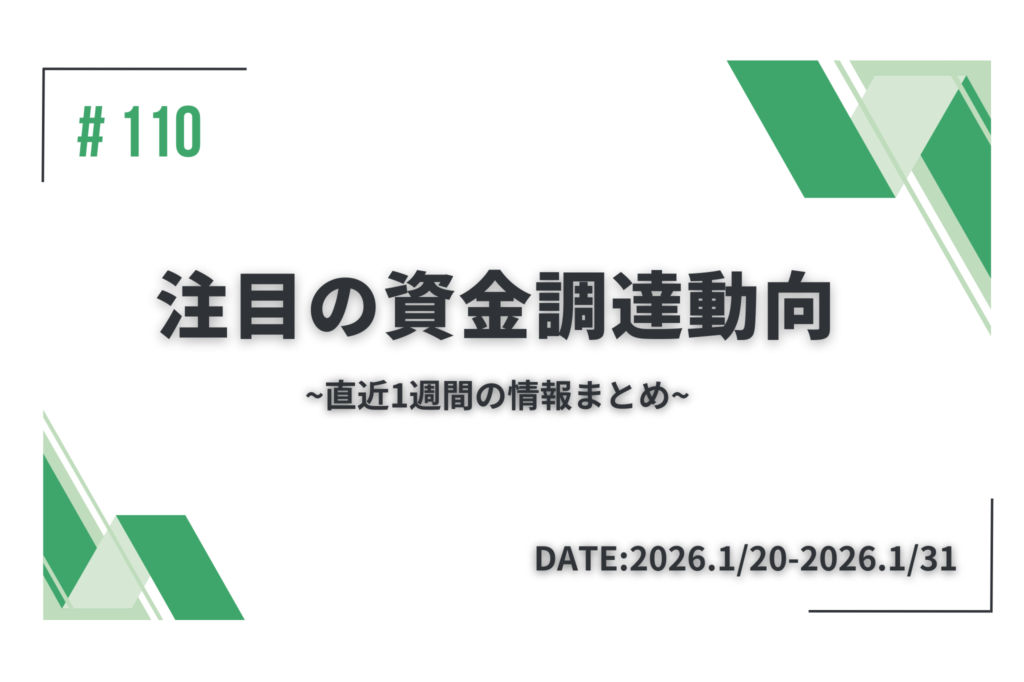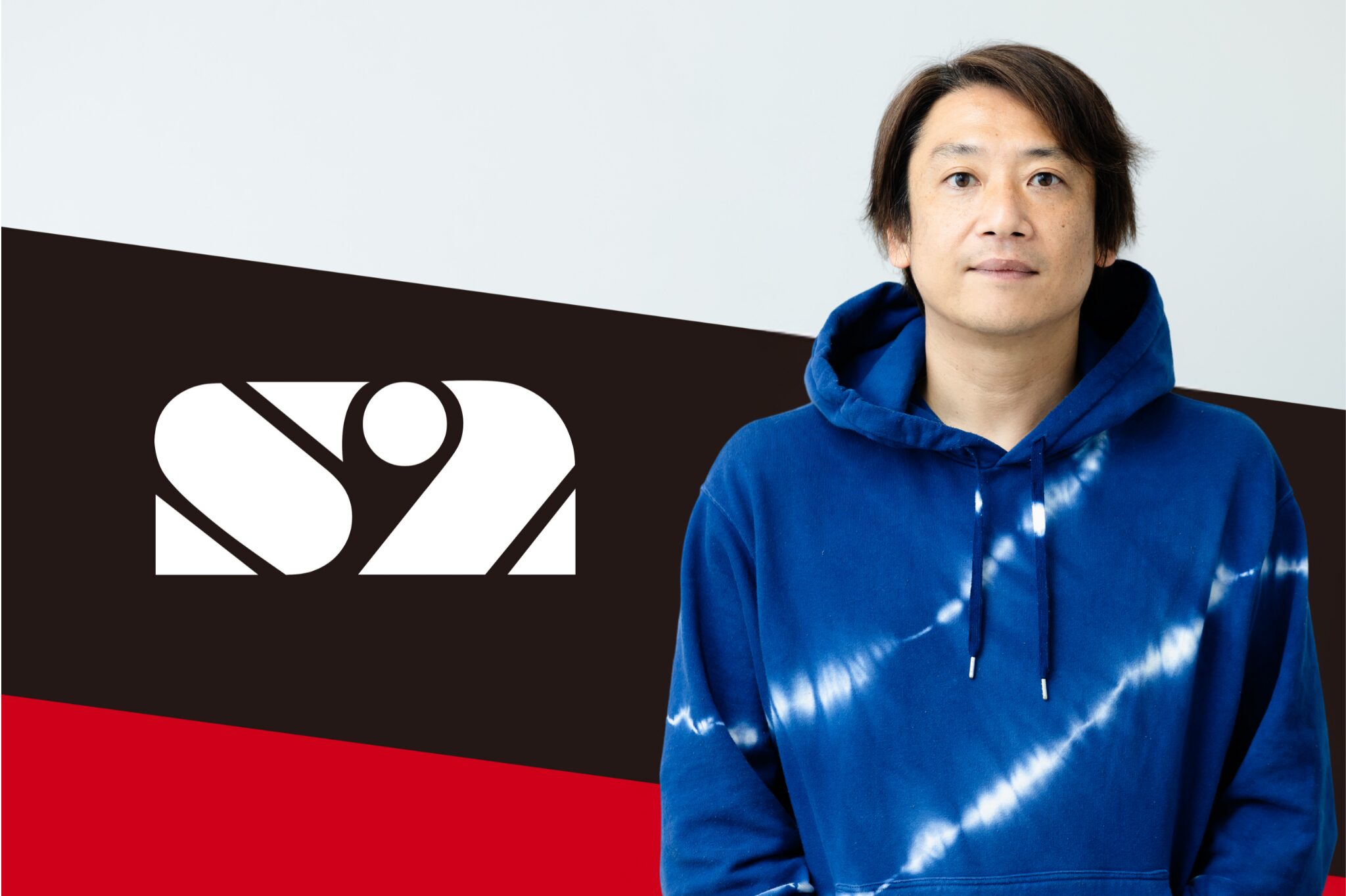
株式会社エスツー 代表取締役 須藤 晃平
大型イベントのチケット販売や災害時の各自治体HPなど、短期でアクセスが集中するサイトの実績。これらの「絶対にダウンさせるわけにいかない」サイト、そして「大切な一日のためだけのサーバー」とも言えるような特別な日に向けたサーバー管理という難しい案件で実績と信頼を築いてきた株式会社エスツーが、今ふるさと納税やeスポーツに関する新しい事業を手掛けています。何故あえて新領域に挑戦し続けるのか、代表取締役の須藤晃平氏にお聞きしました。
大規模な集中アクセスがあっても落ちない、他の追随を許さないサーバー管理
事業の内容をお聞かせください
弊社は、「クラウドMSP・データセンター事業」「ふるさと納税関連事業」「ブランディング、デザイン事業」「BPO事業」「eスポーツ事業」を5つの柱として事業を展開しています。
弊社はサーバー管理で20年の実績があります。「落ちないサーバー」を構築できるという点では日本屈指の会社であると自負しています。
通常は定期契約が多いサーバー事業において、弊社は数日間限定のイベントで数百台のサーバーを運用するといった、特殊なニーズにも対応しています。
過去にはドームクラスのイベントチケット販売や夏フェスのWebサイト、大学の合格発表サイトや災害時の自治体サイトなども手掛けてきました。同時に数億のアクセスがあっても、弊社ならサイトを安定稼働させることができます。
また我々は他社が管理しているサーバーのトラブルにも対応可能で、「サーバーで困りごとがあればエスツーに」と、広く認知していただいています。
ふるさと納税関連事業では、自社でふるさと納税のサイトを持ちたいという事業者様向けに、受付システムのパッケージ販売を行っています。
通常は膨大な費用と日数がかかるところ、最短・最速・最安値での導入が可能な弊社のシステムは、全国の事業者様に選ばれています。
ふるさと納税が活発になれば、地方に資金が流れ、自治体の税収が増加します。それはつまり地域活性や雇用創出にもつながっていくことなので、弊社では引き続きこの事業に注力していきます。
弊社のBPO事業は雇用創出の観点から生まれたビジネススキームです。元々は最低賃金、高齢者率日本一の秋田県の弱みを、何とか強みに変えたいという思いからスタートしました。
具体的には24時間365日稼働でかつ、デジタルスキルが高い環境というサーバー会社の特長を活かし、画像加工や文字起こし、翻訳の副業人材を集めて、首都圏の会社などに手頃な価格で高品質なサービスを提供しています。また弊社はWebデザイン専門の制作チームも抱えており、ここでも地域雇用の創出に微力ながら努めています。
最後に、弊社の手掛ける事業で現在最も注目を集めているのが「MATAGI SNIPERS(マタギスナイパーズ」というアジア・パシフィック初のシニアeスポーツチームの運営です。
MATAGI SNIPERSは平均年齢69歳というチーム編成にも関わらず、実力は若手プロも驚くレベル。瞬く間にマスコミやSNSで話題になり、動画の総再生回数は3,000万回に達しています。
弊社の事業はどれも独自の強みと実績があるという点で、共通していると思います。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
24歳のとき、東北で会社を立ち上げました。出勤前にサーフィン、仕事後にスノーボードをするようなライフスタイルを実現したいという思いが、東北地での起業のきっかけです。
当時はリモートワークが一般的ではなく、東京では理想の働き方が難しかったことに加え、東北にも自分が働きたいと思える会社がなかったため、「それなら自分でつくろう」と決意しました。
サーバー会社を立ち上げたのは、誰もやりたがらない仕事だったからです。サーバーは24時間365日の対応が求められ、連絡があるのは不具合やクレームのときばかりです。敬遠される仕事にこそ、成功のチャンスがあると考えました。
最初にこの事業で注目されたきっかけは、とある人気アーティストの全国ツアー中にサーバーがダウンし、唯一我々が対応できたことです。
このときの実績を足掛かりにして、集中アクセスを要するエンタメ業界で信頼を積み重ねていき、気づけば「大事な時のサーバーといえばエスツー」と言っていただけるようなポジションを築くことができました。
ふるさと納税の事業を始めたのも、年末にアクセスが集中するというサイトの特性上、我々のノウハウが生かせると考えたからです。そして地域活性化の観点から非常に意義のある事業でもあります。
デザイン部門や地域ブランディング、BPO、そして「MATAGI SNIPERS」の事業を手掛けるようになったのも、元は同じ理由からです。
「日本一給料が安い」「日本一高齢者が多い」と言われる秋田のネガティブな部分をポジティブに変え、雇用を創出してお金を生み、高齢者が生き生きと活躍できる場を作りたいという思いが、これらの事業を立ち上げた動機となっています。
こだわりは持たない、けれど人としての軸はぶらさない
仕事におけるこだわりを教えてください。
特別なこだわりがあるわけではなく、正直、事業に強い執着もありません。できる限りのことをやってみて、それでもうまくいかなければ、潔く新ビジネスを停止するといつも考えています。
経営者がこだわりなど持っていると、会社は時代に置いていかれます。ですから私は固定観念も、プライドすら持たずに譲るべきところは躊躇なく譲ります。
一方で、自分自身の人としての軸はぶらしていないつもりです。そのために努力や苦労をしているわけではないのですが、「どんなときも明るい方がいい」「有名になることには興味はない」といった一貫した考え方があります。
それがあるからこそ、従業員もずっと私についてきてくれているのだと思います。
サーバー事業は、担当者が辞めてしまうと同じスキルと経験を持つ人材の確保が難しく、事業の継続に大きなリスクが生じます。
ですが、当社では従業員の定着率が高く、技術の積み重ねとお客様の信頼を重ねています。これからも自分らしいスタイルを貫きながら、仲間とともに働き続けていけると信じています。
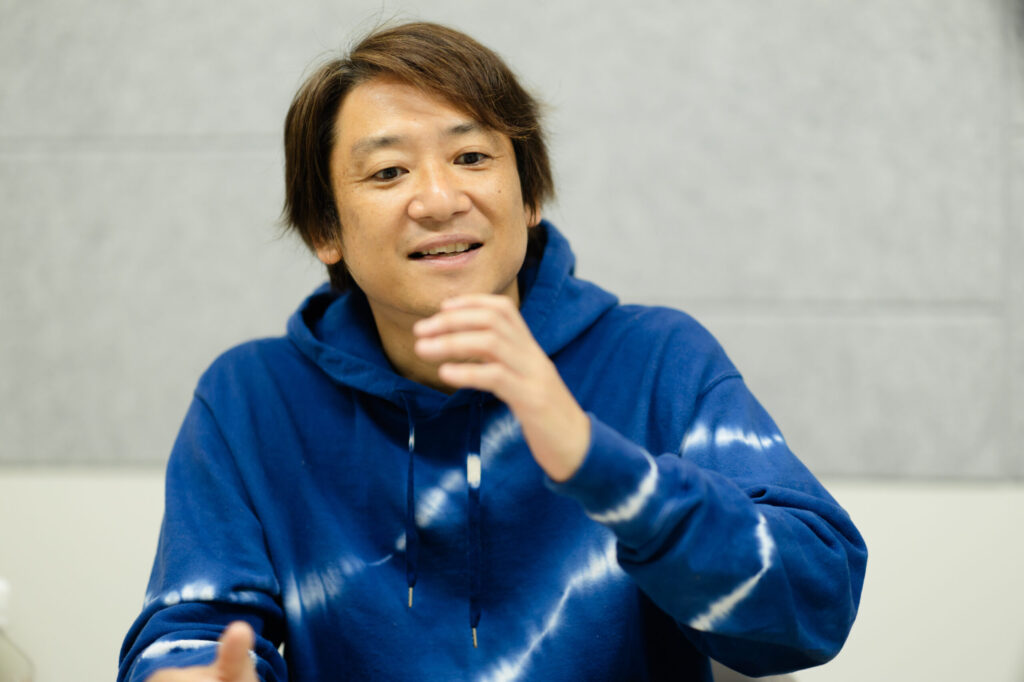
起業から今までの最大の壁を教えてください
最大の壁は間違いなく、起業5年目で経験した東日本大震災です。
仕事ができない、働きたくても働けない、それどころか食べる物がない状態が続き、温かい食事を食べると、自然と涙が出てきました。そんな状況で、従業員に対する責任を負って経営者として何とかやり抜かなければなりませんでした。
あの頃は、従業員の半分には電話に張りついて「何かお困りごとはありませんか」とひたすら声をかけ続けてもらい、もう半分の社員にはリュックを背負わせて食べる物を探しに出てもらっていました。
とにかく必死で仕事を取りに行くしかなかったのです。従業員たちは毎日、朝から8時間以上かけて街を歩き回っていました。
今の平和な暮らしの中ではあり得ないことのように思われるかもしれませんが、あの経験が我々の会社を強くしたのだと思っています。誰にも守ってもらえない過酷な状況の中で、生きていくために会社の全員が一枚岩になっていました。
本気で営業に取り組んだ甲斐もあってか、翌年には過去最高の売上も記録しました。そして当時の状況下でサーバーが止まらなかったという事実も、我々の大きな実績になったと思います。
生きたくても生きられなかった仲間の分まで働く
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
震災で生き残った自分たちが怠けるなんて、そんなことは許されるはずがないという思いが根底にあります。
事実、働きたくても働けない、生きたくても生きられなかった人が沢山いたからです。彼らの分も働き、東北を建て直すというつもりで必死にやってきました。
今も覚えているのが、震災後に全従業員を集めて話をしたことです。「今から10年は死に物狂いで働く。そうしないと被災された方たちに申し訳が立たない。一切手を抜かず、全国からこの東北に金を集めるんだ」という話でした。
話を聞いていた従業員にもその気持ちは伝わったと思います。それから東北以外から仕事をもらうということに対しての彼らのモチベーションは凄まじいものでした。
当時私の話を聞いて頑張ってくれた従業員は、今全員が弊社の幹部になっています。やはりあの震災のときの思いを共有しているというのは、特別な絆だと感じます。

今後やりたいことや展望をお聞かせください
今後も「いかに東北に仕事を作り続けるか」という観点で事業を伸ばしていきたいです。
特に新卒の若い世代だけでなく、主婦や学歴がない人たち、さらには高齢者など様々な背景を持つ人たちの雇用の機会を創出することが、経営者たる自分の最大の責任だと思っています。
東京にある仕事をできる限り東北へ呼び込み、地域活性化につなげたいというのが私の考えです。
また「MATAGI SNIPERS」に関していうと、目指すのは徹底して世界一の称号です。彼らは目覚ましいスピードで実力を伸ばしています。
「年を取る」というのは、今若い世代にも私自身にもいつか必ずやってくることです。だからこそ今から30年先の未来に、高齢者が幸せに生きる1つのモデルケースを「MATAGI SNIPERS」で作っていきたいと思っています。
また、個人的には秋田の若い人たちを育てる活動にも力を入れています。首都圏からも経営者を呼んで一緒に勉強会をやったり、秋田のクリエイターのための東京でフェアを企画したりもしています。
そういった形で東京と秋田をつなぐ橋渡しとしての役割も果たしていきたいです。
40歳以上になってからの経営を支えるのは「人間力」
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
起業を考えている時点で人並外れた情熱はあると思うので、若い人たちに情熱について説くつもりはありません。
ただ、事業は立ち上げるだけでなく続けることが大切だと思うので、私からはもう少し長期的な視点でのお話をしたいと思います。
若い頃は特に、自分自身の才能がまっすぐに現れてとても良いビジネスが生まれます。私自身の経験を振り返ってもそうですし、20代の人が経営するスタートアップを見ていると実際どれも素晴らしいビジネスモデルだと感じます。
けれど、年を重ねるにつれて発想は時代とズレが生じるようになり、その頃にはイノベーションを起こすような企画が生まれにくくなります。そうなったとき、経営者に残されたものは何かというと、それは人としての厚みしかないのです。
人間として厚みがある経営者のところには人が集まり、それが大きなイノベーションが起こるようになります。40歳を過ぎて若い頃のような発想力も才能も発揮できなくなったとき、それまで築きあげてきた信頼と人脈がものを言うようになります。
ですから、若いときからお金にも人間関係にもだらしなくならないように、誰からも信用されるような誠実な経営者像を追求してほしいと思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:須藤 晃平 氏
1980 年生まれ。薬科大学を中退後、19歳の時にオーストラリアで漫画喫茶を開店。その後、首都圏のコンサルタント会社に就職。バブルのIT 業界に違和感を感じ 2006 年、仙台市で株式会社エスツーを設立。世界最先端の技術を武器に現在では数十万のサイト、システムのサーバ管理を担い、今もなお急速に 事業を拡大している。現在では秋田県eスポーツ連合の代表理事も務めている。
企業情報
|
法人名 |
株式会社エスツー |
|
HP |
|
|
設立 |
2006年5月17日 |
|
事業内容 |
|
関連記事