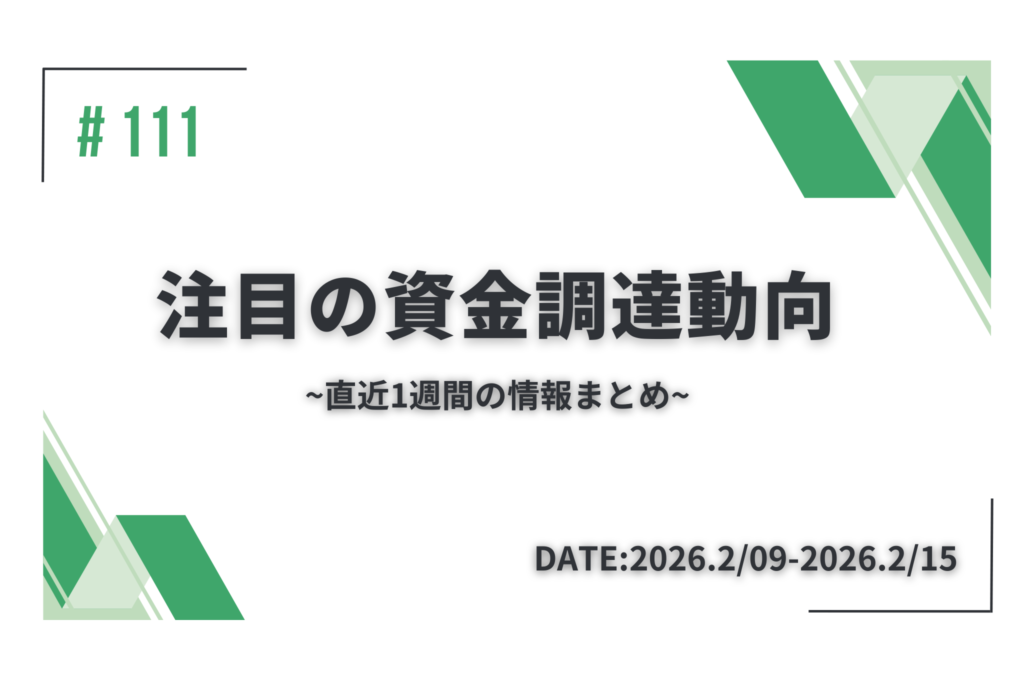株式会社ZIAI 代表取締役 櫻井昌佳
傾聴AIを活用し、誰にも言えないセンシティブな悩みを抱える人々を専門家へつなぐ事業を展開しています。社会課題解決と事業成長の両立を目指し、自治体との連携を進めています。カウンセリングを日常に溶け込ませる未来を目指し、日々邁進している同社の代表取締役、櫻井昌佳氏にお話を伺いました。
誰にも言えない悩みを、AIを通して専門家へつなげる
事業の内容をお聞かせください
AIを活用して、悩みを抱える方の声を受け止め、必要に応じて専門家へとつなぐ仕組みを提供しています。
例えば、いじめや虐待など深刻な問題を抱える子どもたちが、身近な大人には話せないけれど、匿名のAIになら打ち明けられるというケースが多くあります。
AIであれば、誰かにどう思われるかを気にせずに済みますし、時間や場所に縛られることなく話すことができます。実際、AIによる傾聴は感情の整理にも役立っていて、怒りや不安といったネガティブな感情を平均21.5%軽減したというデータもあります。
しかし、AIに話すことだけでは、課題そのものが解決するわけではありません。例えば、精神面が関わるケースでは、AIが一時的に気持ちを和らげても、現実的な変化にはつながりません。
そのため、私たちは「いかにAIから人間の専門家につなげられるか」にも力を入れています。
例えば顧客が教育委員会や学校の場合、必要に応じて自治体と連携して、スクールカウンセラーなどに繋げ、伴走支援をする取り組みを行っています。家庭の経済的な事情や子育てに関する悩みにも対応しており、必要であれば専門家に繋ぐこともできます。
また、不調を抱える方が、すぐに病院を受診できるとは限りません。予約が取りづらいなど十分な支援が受けられない人が多く存在します。
既存のいのちの電話やSNS相談なども常に相談できるわけではないので、必要な時に支援できていないという課題があるのが現状です。私たちはそうした方々の一助になりたいと考えています。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
私はもともとインドで、NGOを7年間運営しています。スラム街に住む女性たちへの性暴力を防ぐ取り組みをしていて、これまでに約2万3000人への介入を行ってきました。その結果、私たちが活動した地域では性暴力の発生率が8〜9割も減ったという成果もでています。
ところが、2020年にコロナウイルスが本格化し、私たちの現場活動も止まらざるを得なくなり、日本に一時帰国することになりました。現場での活動ができない中で、日本でも何か社会課題に取り組むことはできないかと考えたのが、今の事業を始めるきっかけでした。
その頃、日本では自ら命を落とした著名人のニュースが頻繁に報道されており、自殺率が高いことを疑問に思いました。インドやバングラデシュでは社会課題は山積みですが、自殺率は日本よりも低いです。
そこで、社会課題の多さと自殺率は、必ずしも比例していないのではないかと考えるようになりました。その違いはどこにあるのかと考えた時に私が仮説として持ったのは、心のストッパーの有無です。
インドでは、ヒンドゥー教や仏教といった宗教や、家族の絆が自分の心を保つ大きな役割をしているのに対し、日本のような先進国では、そういった役割が徐々に小さくなってきているのではという考えです。
だからこそ別のストッパーが必要であり、それを今の社会で担っているのが悩み相談やカウンセリング。それなのに”つながらない”ことが当たり前になっている今の仕組みは、非常に大きな課題ではないかと思うようになっていきました。
テクノロジーの力で、いつでも気軽に悩みを話せる場所をつくりたいと考え、AIの研究者やエンジニア、臨床心理士たちとともにNPOを立ち上げたのがスタートです。

便利さより、困っている誰かのために
仕事におけるこだわりを教えてください。
“仕事の進め方”というより、”仕事の選び方”におけるこだわりは強いのかなと思います。昔から便利な世の中をさらに便利にすることにあまり興味を持てませんでした。
それよりも、辛さや苦しみなどを抱えている、基本的人権が犯されている、命の危険があるなど、マイナスの状態にいる人々をどうやったら0に引き上げられるか、に人生を賭けたいと思っています。
実際のところ、頭に浮かぶアイデアのほとんどが社会課題に直結しています。誰かの困りごとを本質的にどう解決するかを考えることが自分の中で一番好きですし譲れない軸なんだと思います。
今は社会起業家という立場ですが、あくまで軸にあるのはどうすれば社会課題を解決できるかという視点で、それが実現できるならどのような形であれトライしたいと考えています。
起業から今までの最大の壁を教えてください
一番大変だったのは、NPOから株式会社へ移行する際の組織の価値観の再構築でした。当時は、とても優秀なメンバーたちが本業を持ちながらも集まり、NPOを立ち上げました。
しかし、約3年の研究開発を経て社会実装を本格的に進めていくタイミングで、どうしてもこれまでのスピード感では戦えないと判断し、チーム体制の見直しおよびスタートアップとして再始動することとなりました。
もちろん全員にフルタイムとしての給与を支払えたら変わっていたことがあるのかもしれませんが、この時に辞めてしまった人も少なくありません。
私にとっては、志を同じくする彼らと一緒に新しい何かを作り上げていくこと自体がすごく重要だったので、これまで築き上げてきたものを自分の手で壊していくような感覚になり、とても苦しい経験をしました。

カウンセリングを日常に溶かす
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
エンドユーザーの方から「このサービスがあるから今、生きていられる」といった声をいただくことがあります。そういった言葉は、本当に大きな励みになりますし、支えにもなっています。
もちろん、中長期的に見れば、AIとの対話に依存しているように見える状態かもしれません。
ですが、そこからきちんと人間の専門家へとつなげる仕組みが機能しているなら、一時的な心の拠り所としてはとても意味のあるものになっていると思っています。
また、自傷行為や薬など何かに依存している方にとっては、依存先を増やす手段として傾聴AIとの対話を活用することも有効だと考えています。こういったエンドユーザーからの生の言葉を聞くと、私たちのサービスが役に立っていると感じ、とても嬉しく感じています。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
当初から掲げてきた目標は、2030年までに、年齢、経済状況、そして居住地域関係なく、悩みを抱えたときに相談できる居場所をつくることです。そして、その先に必要なサポートへとつなげられるような、一次予防の仕組みを社会に実装することです。
2020年に活動を開始したので、今はその道のりの折り返し地点です。ここからの5年間で、基盤を確かなものにしていくことが直近の目標です。そして2040年に向けての展望は、悩み相談やカウンセリングを、日常の中に溶け込ませていくことです。
私自身、以前はただ話を聞いてもらうだけで何が変わるのかと、正直疑問に思っていました。しかし、何気ない近況を話したり、雑談をすることは相手に答えを求めているわけではなく、自分自身の気持ちが軽くなったり、誰かと繋がっている感覚を得ることで、安心することができます。
そう考えると、相談やカウンセリングといった言葉が、かえって壁を作り、利用するハードルを上げてしまっているのかもしれないと感じました。「あのときの対話はカウンセリングだったのかもしれない」と後から思うような、人々に気付かれずないカウンセリングの形を社会に広げていきたいと考えています。
頭で考えるより、まず一歩を踏み出す
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
起業を考えている人には、とりあえず始めてみるというのが個人的な意見です。
多くの人が何かを始めるときに0か100かの発想にとらわれがちですが、実はその間にできることは山ほどあります。思い立ったその日からでも、始められることはあります。
それから、頭の中で考えていることの9割9分は、正直うまくいきません。海外の起業家が「Action produces information(行動が情報を生む)」とインタビューで語っていて、まさにその通りだと納得しました。
インドのNPOを始めたときも、日本でNPOをはじめたときも、スタートアップとして勝負している今も、事前に練った戦略や計画は基本的にその通りにいきませんでした。
実際に行動してみないと、分からないことばかりです。やってみないと、自分のアイデアが上手くいくのかも、自分がその領域で勝負し続けたいと思えるのかどうかも分からないままです。
だからこそ、まず一歩踏み出すことが何より大事だと思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:櫻井 昌佳 氏
神戸大学卒業後、大手商社に入社。人事課やIT起業での勤務を経て日本とインドの2拠点でNGOをそれぞれ立ち上げる。23年4月に株式会社ZIAIを立ち上げる。
企業情報
|
法人名 |
株式会社ZIAI |
|
HP |
|
|
設立 |
2023/04 |
|
事業内容 |
傾聴AIアルゴリズムの開発・提供 |
関連記事