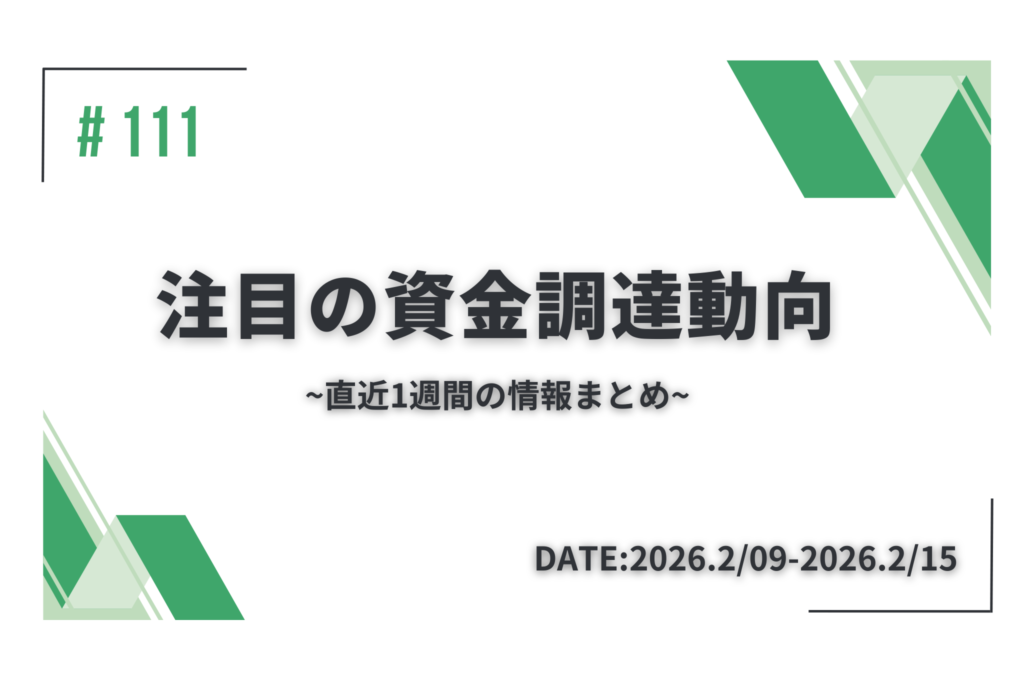【#504】トピック空間型SNS『Nester』が実現する、ハッシュタグ起点のフラットなコミュニティ|代表取締役 丸山 耀平(Nester株式会社)

Nester株式会社 代表取締役 丸山耀平
トピック空間型コミュニティSNS「Nester(ネスター)」は、ハッシュタグを起点にユーザーが集まり、リアルタイムの会話や共創が生まれる新しいSNSです。開発・運営するのは、Nester株式会社代表取締役の丸山耀平氏。SNSにおける情報の偏りやフロー構造に課題を感じ、ユーザーの関心から始まる場づくりを軸に、空間型の仕組みを構築しています。今回は、創業の背景やサービスの特徴などを伺いました。
空間型SNSから始める、もっとフラットな世界
事業の内容をお聞かせください
ハッシュタグを起点にした、空間型コミュニティSNS「Nester」を開発・運営しています。
一般的なSNSは、タイムライン上で投稿が流れていくフロー型ですが、Nesterはハッシュタグの先に空間が存在するという設計思想に基づいています。
ユーザーが任意のハッシュタグをクリックすると、そのテーマに関心を持つ人々が集まる専用の場が開かれ、情報は流れてしまうことなく、その場に蓄積され続けます。


たとえば、「#生成AI」といったハッシュタグには、今何人が参加しているかが可視化され、入室すればすぐに会話がスタートします。フォロワー数やアルゴリズムに依存せず、誰もが話題の中心になれるのが特徴です。
機能は大きく3つあります。1つ目はリアルタイムで交流できるチャット機能、2つ目が意見の集約を行える投票機能、3つ目が共同編集ドキュメントであるOpenNoteです。
情報が一部の発信者に集中しがちな従来のSNSに対し、Nesterはもっとフラットで公共性の高い空間が必要だとの課題意識から生まれました。少人数でも成立する空間から始まり、興味関心ごとに人が集まり、最終的には日常的な情報インフラとして機能することを目指しています。
Nesterは、完全分散型のコミュニティづくりに適している一方で、オンラインサロンといったクローズド空間も作成できます。SlackやLINE公式のような機能を備えつつ、必要に応じて課金設定を行うこともできます。
誰もが自然体で会話できる空間を提供し、ハッシュタグを軸に人や情報が蓄積されていく、日本初の新しいSNSの形です。
サービスを広げるための取り組みについて教えてください
Nestモデレーター制度というハッシュタグ争奪戦です。
Nesterでは、ハッシュタグの先にトピック空間Nestがあります。最初にそのハッシュタグをクリックしたユーザーが「Nestする」ことで、当該Nestのモデレーターになります。
初期は良いハッシュタグを早押しで確保する椅子取りゲームの面白さが核ですが、中期以降は交流のハブ化によりプロフィールへの導線が増え、長期ではNestに掲載される広告収益の分配によって不労所得化の可能性が生まれます。
将来的には、広告収益等で価値が可視化されたモデレーター枠をオークションで売買する構想もあり、取得後の育成、そして流動化という新しいデジタル資産形成を実現します。
なお現在は無料会員でも1日1件Nestすることが可能ですが、最終的にはPremium会員のみがモデレーターになれる予定のため、今が良質なハッシュタグを押さえる好機です。
事業を始めた経緯をお伺いできますか?
父が経営者だった影響もあり、小学生の頃から経営者になることを意識していました。
大学では建築デザインを学びましたが、次第に「デザインの力で社会をどう変えられるか」に関心を持つようになり、世界一のクリエイティブな会社をつくる夢が芽生えました。
その実現には、まず影響力と資金力を持つことが必要だと考えました。どちらも得られる手段として注目したのがSNSの分野で、そこからNesterのアイデアに辿り着いたのです。
起業を本格的に考えたのは、大学2年生の終わり頃です。建築設計の勉強と経営の両立は難しいと判断し、大学を辞めて経営者として生きる道を選びました。
当時すでに、デバイスやウォレットの構想もあったので、親から借りた1万円を手に新潟から上京し、知人の紹介を頼りに初対面の方の家に居候させてもらいました。
自分でやると決めた以上、まずは動いて経験を積まなければ始まらないとの想いで行動していました。
空間にこだわり、ユーザーにこだわる
仕事におけるこだわりを教えてください。
一番大切にしているのは、ユーザー目線で設計することです。もともと建築やデザインを学び、クリエイティブに向き合ってきた経験から、ユーザーファーストの視点は自然と身についていました。同時に、幼い頃から経営にも関心があり、マーケティングや市場分析にも触れてきました。
社会的な課題や競合の動向、ユーザーの顕在・潜在ニーズをマクロで捉えながら、最終的にはユーザー目線に立ち返って設計に落とし込みます。マーケティングとデザインの両方を学んできたからこそできる、ハイブリッドなプロダクト設計を意識しています。
Nesterには、チャット、投票、ドキュメント編集、ブログ、オンラインサロンといった多機能を備えながらも、タップひとつで空間に入れる直感的でシンプルな体験を重視しています。複雑な機能を違和感なくひとつの空間にまとめ上げる納める力こそ、私たちのクリエイティブの強みだと考えています。
組織としても、トップダウンではなく、クリエイターがリーダーとなって導くスタイルを大切にしています。私たちは、インフラであり続ける存在であるために公共性の高さをバリューに据えています。
ミッションは、「興味・関心を持つ人に、必要な人や情報との出会いを届け、居場所を提供すること」。その実現手段として、Nestの空間をつくっています。そしてこの状態が当たり前になる社会を目指すことが、私たちのビジョンとなります。
誰もが使えて、誰もがつくれる。情報がより民主的で公的なものになり、クリエイターが経済的に支援される。そんな社会を実現するために、こだわりを持ってプロダクトをつくり続けています。

起業から今までの最大の壁を教えてください
最初に直面した壁は、プロダクトの開発でした。
Nesterはもともと、不動産投資家である父の依頼を受け、不動産アプリの開発からスタートしました。ただ、どれだけ多機能なアプリであっても不動産アプリ単体で勝負するのは集客の面で厳しいという判断に至りました。
そこで「不動産×SNS」という形に切り替えましたが、開発コストと工数とのバランスが取れず、継続は難しいと判断しました。そのとき、SNSに一本化すれば自然とユーザーが集まりやすく、収益モデルにもつなげやすいと考え、不動産機能を切り離す決断をしました。
大学時代に尊敬していたデザイナーの先輩に相談するなかで、ハッシュタグの先にコンテンツがあるSNSの着想にたどり着いたことが、現在のNesterの原型です。その後は約2カ月間、寝る間も惜しんでデザインを描き続けました。
タイミングをみて法人を新たに設立し、2024年11月にNester株式会社として再出発を切りましたが、ここが大きな壁を乗り越えた瞬間だったかもしれません。
現在は、本格的に資金調達に挑んでいる段階です。まさに今、向き合っている壁だと感じています。
社会の仕組みそのものを変える挑戦へ
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
野望があることです。
単にNesterを成功させたいだけでなく、デバイスやOS、ウォレットなどを軸に、金融革命やデバイス革命といったものを成し遂げ、幅広いプロダクトを生み出したい想いがあります。
それはビジョンであると同時に、私の人生そのものとも言える目標です。この道を妥協したら私の人生ではない、と言えるほどの強い想いがあります。

今後やりたいことや展望をお聞かせください
単にサービスをつくって終わりではなく、社会そのもののあり方をデザインしたいです。
若い頃、Appleのスティーブ・ジョブズに憧れていました。彼が製品をつくるだけでなく、社会全体の仕組みや文化のアップデートに関わっていた姿がとても印象的でした。私自身も、日本や世界の先頭に立てるような存在になりたいと思っています。
その第一歩として、ウォレット開発に取り組み、決済インフラを持つことを目指しています。世界中の通貨を一つのアプリで管理・決済できる仕組みを発展させることができれば、クレジットカードや銀行といった既存の金融インフラに頼らない、新しい経済のかたちをつくることができるはずです。
だからこそ、ウォレットを起点にさまざまなデジタルサービスと連動するアプリ市場やクラウド型のOSなども構想しています。ただ作るだけではなく、デザインが自然に溶け込む世界観を描いています。
ゆくゆくは、政治や教育にも関わっていきたいです。その想いとしては、日本を勝たせるためのエゴかもしれません。例えば、外貨を稼いで日本円で納税するだけでも経済の仕組みは少しずつ変えられるはずです。民間から社会を動かしていける可能性があると思っています。
すぐに実現できる話ではありませんが、自分がつくったもので誰かの役に立ち、社会を少しでも良くしていける仕組みを、ひとつずつ形にしていきたいと思っています。
勢いよりも、土台づくりを大切に
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
私はすぐ行動してしまうタイプで、何度も失敗を経験してきました。だからこそ伝えたいのは、最初から自社開発に踏み出さないことです。資金的なリスクが伴い、赤字倒産の危険性もあるからです。
もし知識やスキルがあるのであれば、まずは受託開発から始めて、資金と経験をしっかり蓄えた上で、自社株だけでプロダクト開発に挑戦するほうが安全です。
私のように、何も決めずに上京して勢いで事業を始めるよりも、確実に経験も資金も得られると思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:丸山耀平 氏
長岡造形大学 建築・環境デザイン学科 2年生末に中退
株式会社ZEN AUTO 代表 2018年設立
企業情報
|
法人名 |
Nester株式会社 |
|
HP |
|
|
設立 |
2024年11月 |
|
事業内容 |
次世代SNS「Nester」の開発・運営 |
関連記事
RANKING 注目記事ランキング
- 【#468】意見が政策につながる社会へ。市民参加型SNSと自治体向けAIで「デジタル民主主義」を推進|代表 伊藤あやめ/谷口野乃花(Polimill株式会社)起業家インタビューインタビュー

- 【#363】お金いらずで寄付ができるECサービス、世界を救う第一歩に|代表取締役 藤本 巴(株式会社ギバース)起業家インタビューインタビュー

- 【#544】保護犬・保護猫の命をつなぐ。福祉と仕組みづくりで、寄付に頼らず築く持続可能な社会|CEO / 代表取締役 伊東 大輝(株式会社ANELLA Group)起業家インタビューインタビュー

- 【#268】定年齢層向けイベントアプリ『シュミタイム』で、高齢者の社会的孤立を救う。|代表取締役CEO 樗澤 一樹(株式会社ジェイエルネス)起業家インタビューインタビュー

- 【#578】赤ちゃんの感情を可視化するAIアプリ『あわベビ』で、産後うつの課題を解決|代表取締役・CEO 中井 洸我(株式会社 クロスメディスン)起業家インタビューインタビュー