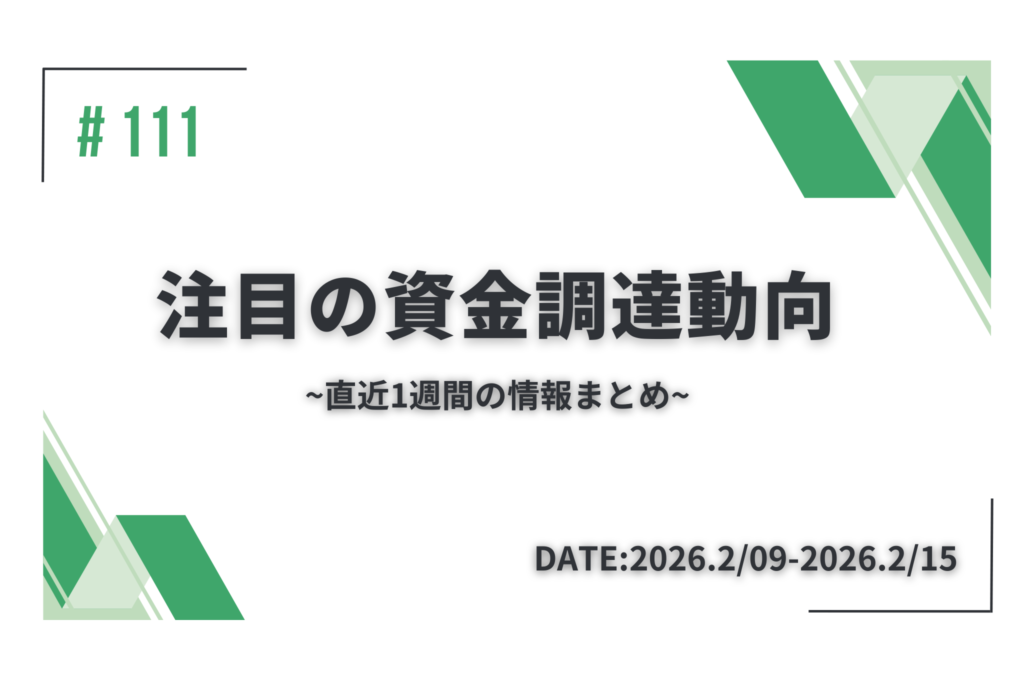【#530】特許出願書類の作成をAIが支援。知財×生成AIで発明者のアイデアを形にする|代表取締役CEO 森下 将宏(株式会社ユアサポ)

株式会社ユアサポ 代表取締役CEO 森下 将宏
特許出願書類の作成を支援する生成AIソリューション開発・提供を行っている株式会社ユアサポ。これまで、国内約30事業者の知財業務の効率化を推進しています。知財×生成AIで発明者のアイデアを形にする、株式会社ユアサポの代表取締役CEO・森下将宏氏に事業を始めた経緯や今後の展望を伺いました。
特許出願書類の作成を生成AIで支援
事業の内容をお聞かせください
当社は、企業の知財部門や特許事務所・弁理士事務所向けに、生成AIを活用した特許出願書類作成支援ツールを開発・提供しています。これは、決して専門家の代わりとなるようなツールではなく、これまで現場で特許出願書類作成に携わっていた方の業務効率化を支援するDXソリューションです。
弁理士や知財の専門家でも膨大な時間がかかる出願書類の初稿作成を、生成AIを活用して瞬時に作成できるのが我々の強みです。最近では、出願に必要な図面作成も画像生成のAIモデルを用いて出力しています。
基本的には、インプットした発明内容のデータをもとに、請求項・明細書・図面を生成します。インプットの方法は様々で、ファイルを添付して入力する、発明内容をテキストにして入力するなどの方法があります。発明内容をまとめる作業を生成AIに委ねて、生成AI側で発明提案書の叩き台を書き上げることもできます。
生成AIを活用することで、工数の削減・人手不足の解消・品質のばらつきの抑制など、幅広いニーズに応えることが可能となります。
そんな当社のサービスには特徴が3つあり、1つ目が、お客様のスタイルに合わせた書類作成です。特許出願書類はお客様によってその内容や形式が異なることも多いです。そこで私たちは事前にお客様ごとに過去の出願データをもとにしたデータベース構築を行い、それら独自のスタイルを出力に適用できるようにしています。
2つ目は、Word上ですべて完結することです。当社サービスはWordアドインとして提供しているため、従来のワークフローを変えずに使用できる点が強みの一つです。
3つ目は、機密情報の管理です。当社はセキュリティも非常に重視しています。新規発明に関するデータは全て、お客様のローカル上で保存する仕組みになっていて、当社のデータベースには一切保存されないようになっています。
また現在は大手クラウドベンダーが提供するエンタープライズ向けの生成AI推論環境を用いてサービス提供をしておりますので、お客様の入力した情報がAIモデルの学習に使われることは一切ありません。
現在は、トライアルを含めて約30事業者に導入いただいています。国内最大手の企業や特許事務所でも、導入を進めていただいています。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
前職もスタートアップの初期メンバーということもあり、いつかは起業したいという思いがありました。時期の巡り合わせもあり、2019年に株式会社ユアサポ(旧社名: キビタス株式会社)を創業したことが始まりです。
当時は現在のように生成AIがない時代で、テクノロジー単体のソリューションによる課題解決に限界を感じていました。テクノロジー単体というより、もう少し世の中にインパクトを与える事業をしたいと思い、法律×テクノロジーで起業したというのが最初の経緯です。
紆余曲折を経て昨年10月にピボットを決断し、生成AI領域で事業をやることは決めていたのですが、汎用的なソリューションというよりも、特定専門領域に絞ることにしました。
さらに、生成AIを用いて付加価値の高い領域にチャレンジしたい気持ちがありました。そこで事業アイディアを検証するなかで、生成AIによる特許出願支援領域は海外では注目されつつありましたが国内ではまだ注目されていなかったため、何かソリューションができそうだと考え参入を決意しました。
事業転換で覚悟を決めた
仕事におけるこだわりを教えてください。
知財領域については、私の経歴としては新参者や部外者のような気持ちがあります。ただ、部外者視点や外部者視点を持ってやっていることは、必ずしも悪いことだとは思っていません。
自分が知財領域に関わって、知財領域は非常にソフトウェアによる改善の余地が大きいと感じています。
だからこそ、これまで自分がずっとやってきたソフトウェア開発やソフトウェアプロダクトの視点を持ち、どのように業務効率化ができるのかということを考えています。一番重要なことは、お客様にとって何が良いのかを考えることだと思っています。
特許明細書などの特許出願書類には、絶対的な正解の書き方があるわけではありません。企業や弁理士事務所、担当者ごとに正解が変わるため、それぞれの正解に対して製品が自然に合わせられることが、当社のプロダクト思想です。

起業から今までの最大の壁を教えてください
起業当初に展開していたBtoCのリーガルテック事業から現在の「知財×生成AI」に至るまでの道のりは、まさに壁というよりも沼に近い感覚でした。
前の事業が思うように成果を出せず、ピボットを決意したものの新しいアイデアが見つからず、受託業務で会社を維持していた時期が2年ほどありました。実際に起業してからは常に動いてはいたものの、会社としては停滞感を抱えていた時期でした。
そんな中で、多くの方々に相談を重ねる中で既存株主から「やるなら思い切った事業をやった方がいい」というアドバイスをいただきました。それをきっかけに試行錯誤を続ける中で知財×生成AIという領域に挑戦し、今の形につながっています。
このまま続けても意味がないと感じ、次の挑戦で結果が出なければ会社をたたむくらいの覚悟で取り組んだことが、自分にとって大きな転機だったと思います。
お客様からのフィードバックと生成AIの発展が一番のモチベーション
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
お客様からのフィードバックが一番のモチベーションです。お客様からツールを使いたいとお問い合わせをいただき、実際に使用してフィードバックをいただくことが、一番の励みになります。
生成AIの発展もモチベーションです。生成AIでできることが増えているので、当社の付加価値は大きくなり、お客様に還元できるものが日々多くなっていると感じています。
お客様からのフィードバックと当社のプロダクト、生成AIの発展により、事業プロセスの全体的な改善を行っています。自社サービスの開発自体においても生成AIを活用するなど、社内の業務改善を進めています。
事業転換をした頃は、良くも悪くも気持ちを新たにゼロの状態からもう一回始めたようなものですが、その時から生成AI前提で事業も組織体制もすべて切り替えました。結果的に、生成AIの進化に伴いすべてアップデートされる状態となっています。

今後やりたいことや展望をお聞かせください
一つ目はプロダクトについてです。現在は国内における特許出願のみに対応していますが、今後は日本から海外への展開も生成AIを通じて支援したいと考えています。
二つ目は自社組織についてです。現在は、人間が生成AIに指示するというパラダイムから抜け出せていないので、生成AIが生成AIに指示をしながら、より自立駆動的に機能する組織設計を進めていきたいです。
また、知財業界における生成AIの利活用については、大企業や大手特許事務所などからもお問い合わせをいただいているものの、各社ともまだ活用が進んでいない印象があります。そのため生成AIを通じてできることやその可能性については、当社からも積極的に発信していく必要があると感じています。
目指す組織と採用したい人材についても考えています。生成AIの利活用を前提とした組織なので、生成AIに興味がある方というのが大前提だと思っています。また、生成AIを通じて小規模で組織活動を自動化していくチームになると思うので、そのような新しい組織運営の方法に興味がある方は当社に合っていると思います。
現在は、業務委託を含め10名未満のチームですが、今後組織の中核として働ける人材を数名程度増やしていきたいと思っています。
絶対に勝てるドメインを持つ
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
起業にあたっては、自分の強みとなる領域を持つことが大切だと考えています。私の場合は、生成AIやBtoBのSaaSがその軸になりつつあります。誰にも負けないと自信を持てるテーマがあるかどうかで、起業の進めやすさは大きく変わると思います。
実際、起業を志しても事業として何をすべきか分からないという壁に直面することがあります。その状態で走り出してしまうと、苦しさばかりが先に立ってしまいます。
だからこそ、自分が勝てると信じられる専門分野を持つことを、これから起業を考える方々には強くお勧めしたいです。逆に、すでに何か得意分野を持っている方には、ぜひあと一歩踏み出して挑戦してみてほしいと思います。
たとえ今は明確な強みがなくても、半年から1年しっかりと取り組めば、誰でも何かしらのプロフェッショナルになれます。だからこそ、まずは自分だけの武器を見つけることが重要だと感じています。
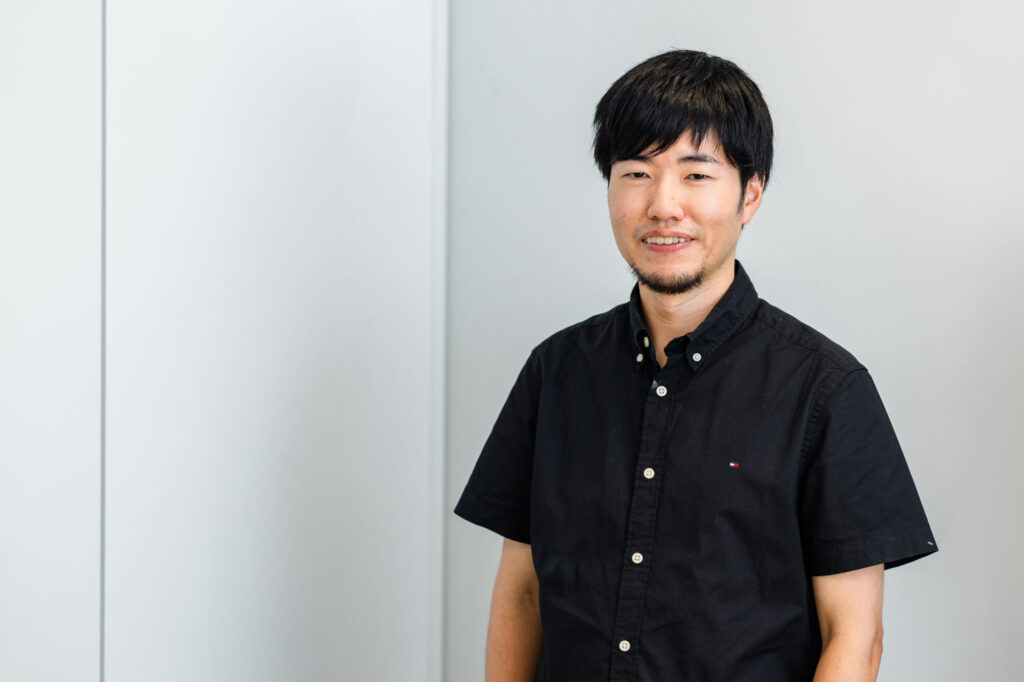
本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:森下 将宏 氏
京都大学経済学部卒、エディンバラ大学院修了。スタートアップ数社を経て情報セキュリティスタートアップの株式会社カウリスに執行役員COOとして就任。2019年、株式会社ユアサポ(旧社名: キビタス株式会社)を創業。
企業情報
|
法人名 |
株式会社ユアサポ |
|
HP |
|
|
設立 |
2019年4月10日 |
|
事業内容 |
知財・特許業務を効率化する生成AIソリューションの開発、提供 |
関連記事