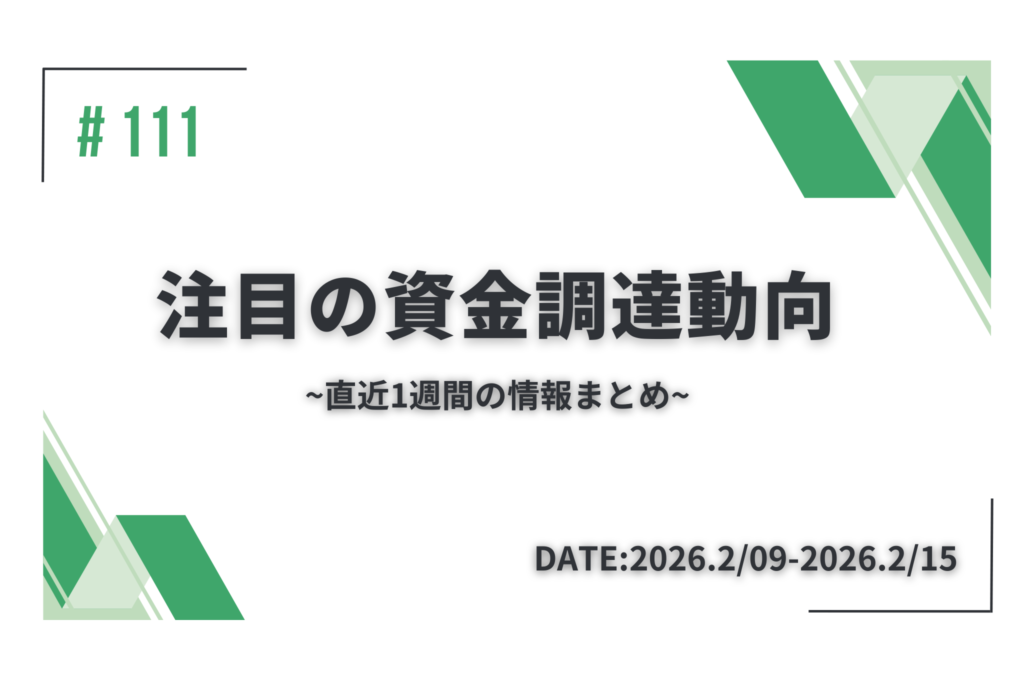【#531】食品流通業界のマーチャンダイジングを支援。「日常の食卓を、より豊かに美味しく」を追求する|代表取締役CEO 上村 友一(株式会社デリズマート)

株式会社デリズマート 代表取締役CEO 上村 友一
株式会社デリズマートは「おいしさと価値がなめらかに流通する未来」を目指し、食品流通業界でマーチャンダイジングの支援を行う企業です。代表取締役CEOの上村友一さんはミシュランレストランでの修行、食品OEMプラットフォームの会社の創業と売却といった異色の経歴の持ち主。デリズマートの起業に至った経緯や今後の展望についてお伺いしました。
商品開発スピードとMDエージェントサービスに強み
事業の内容をお聞かせください
弊社のおもな事業は、食品流通領域での商品開発や調達といった「マーチャンダイジング(MD)」の支援です。
一般的にスーパーなどの食品小売業は商品を仕入れて販売しますが、近年は、自分たちで商品を企画・製造・発売する「製造小売業(SPA)」の形態が増えています。
そんな小売業のSPA化に関して、商品開発や、調達ルート・製造業者のネットワーク構築など、オペレーションのリアルな部分にAIエージェントをはじめとしたデジタル技術を掛け合わせて、お客様のご状況に合わせた伴走型コンサルティングでサポートするのが私たちの仕事です。
顧客は、エンタープライズ企業と呼ばれる年商2000億円以上の食品小売業が中心で、皆さんも馴染みのあるお店ばかりです。そのようなお店のプライベートブランド(PB)の開発を支援しています。
通常、ゼロから商品を企画しようとすると、発売に至るまでに1年程度の時間を要しますが、弊社では味や利益率を多角的に設計しながら3か月程度で対応することができます。
従来の3分の1という圧倒的なスピードで商品開発ができるのは、メーカーとのネットワーク、経験によるコンサルティング力、商品設計図の“モジュール化”による効率化の実現の3点によります。
たとえば、PB商品のハンバーグを作るというとき、製造メーカー探し、商品設計、使用する食材の選定など、いくつもの作業を並行して開発していくこととなります。しかし、私はこれまでに多くの商品開発を手掛けてきたので、肉や野菜、調味料など必要な材料・素材の入手ルートを豊富に持ち合わせています。
これらの材料を組み合わせてアレンジするとともに、蓄積してきた商品設計図をベースに活用することでスピーディな商品開発を実現させています。リードタイムを最大限短縮できるというのは私たちの強みのひとつです。
事業を始めた経緯をお伺いできますか?
実は、今回は私にとって2度目の起業で、その前には仕込み用の食材を発注したい飲食店と製造案件を受注したい食品加工メーカーを繋ぐ、食品OEMプラットフォームを運営する会社を経営していました。
私は調理師専門学校を卒業後、ミシュランレストランでシェフとして働き始めました。当時は朝5時から深夜2時まで働き、その大半を食材の仕込みに費やしていました。
このサイクルを毎日繰り返すのはとても大変で、仕込み作業をアウトソーシングできたら、クリエイティブな仕事により多くの時間を割けるのではないかと強く感じていました。
委託可能な作業を共通化・外部化することで生産性が上がれば、料理の質も給与水準も上げられると考えて2018年に起業しました。
その会社は2020年に売却するのですが、その直後にコロナ禍が始まりました。外食向けの仕込みを請け負う事業だったため、クライアントへの影響は大きく、私はすでに退任していたものの、多くの相談が寄せられました。
その時に気づいたのが、スーパーやECの急成長です。そこで、メーカーから寄せられる相談に対してスーパー向けの商品を作るのはどうかと助言をしたのです。
そこで私は紹介役として個人事業主のような立ち位置でサポートすることになりました。気づけば20社ほどの顧問役を務めていました。
そんな状況を見た投資家の方から会社を作ったほうがいいと背中を押されました。正直悩みましたが、自分が役に立てるならと考え、2度目の起業に踏み切りました。

商品開発は「総合格闘技」
仕事におけるこだわりを教えてください。
特定の商品開発に強みを持つ企業は多々あります。メーカーや商社が既存の商品に別のラベルを貼ってオリジナル商品として提供するケースも少なくありません。
ただ、そのやり方は自社のネットワーク内だけで完結してしまいます。実は他にもっと最適な原材料や製造工場があるかもしれず、これは必ずしもベストな選択肢とは言えません。
一方で、私たちは世界各地から原材料や製造工場を選び抜き、どのルートで調達するか、サイズや数量をどう設定するかなど、あらゆる条件を組み合わせて、味や風味をつくり込みます。
さらには経営戦略の視点から最適な商品開発プロセス全体をデザインし、それを現場のオペレーションやシステムにまで落とし込むのです。総合的なアプローチができ、かつ、魚・肉・惣菜・スイーツと、幅広い商品を開発できるのが私たちの強みです。
これを可能にするのは、前職でのレシピづくりから納品に至るまでの経験とネットワークです。また、弊社の商品開発部には、食品スーパーやコンビニの開発部門でトップを務めてきた経験豊富な人材が揃っています。
だからこそ、幅広い商品をスピーディーかつ高品質に形にできるのです。
起業から今までの最大の壁を教えてください
もちろん、その時々で厳しいと感じる瞬間はたくさんありました。ただ、そもそもニーズがあって始めた事業なので、壁を感じたことは正直ありません。
それでも、人材マッチングの難しさだけは、最初の起業時からずっと悩みの種でした。
スタートアップは大企業のように新卒一括採用をするわけではなく、さまざまなバックグラウンドを持つ人の集合体です。長く力を発揮してくれる人もいれば、数か月で「合わない」と辞めてしまう人もいました。
売上が不安定な時期に優秀な人材が加わってくれるのは本当にありがたいことです。しかし、どうしてもカルチャーが合わない場合もあり、そのときに経営者として「NO」を言えるかどうかは大きな試練でした。
合理的に考えれば別の道を選ぶのが正解なのですが、感情的に割り切れず決断を先送りにしてしまうこともあり、それが経営の足かせになったこともあります。
難しいのは採用そのものよりも、採用後に合わないと分かったときにどう判断するかです。起業家は一般的に攻めの力が強いですが、人材に関しては撤退や後退の判断も欠かせません。
その意味では、人事こそが私にとって最大の壁であり、今でも毎回悩みながら向き合っている部分です。

おいしさを極め、スケールさせる
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
おいしいものを追求したいというのが私の人生観です。自分自身、食べることや美味しいものが大好きで、その思いが自然と美味しいものをつくる仕事へとつながっています。
現在、私たちが提供している商品は、多くの消費者が手に取りやすい価格帯になっています。
私が一流レストランでの修業で培った技術をコンシューマー向けの量産商品に落とし込み、日常の食卓に届けるようにしています。その価値は計り知れず、これは私にしかできないことだと考えています。
おいしさを極め、それをスケールさせることができれば、誰もがこれまで以上においしいものを日常の食卓で楽しめるようになります。これはものすごいことだと思いますし、それが、私を突き動かす最大のモチベーションになっています。
生活の基盤である日々の食卓は、電気や水道のような生活に欠かせないインフラとも言え、これを支え、豊かにすることに貢献していきたいと考えています。

今後やりたいことや展望をお聞かせください
実店舗に留まらず通販やデリバリーなど、購入手段は日々多様化し、大きく変化しています。しかし、食品に対する需要そのものは変わりません。
買い物のDX化を手掛ける企業は数多くありますが、私たちが挑んでいるのは商品そのものにおける構造変革です。
単に仕入れて販売するのではなく、自らつくり出し、お客様に届け、さらにその声を反映して次の商品を生み出す。これからの食品小売企業にはこのサイクルを構築することこそが不可欠だと考え、会社を立ち上げました。
今後は、食品小売企業が商品開発におけるサイクルや調達ネットワーク、商品開発のノウハウを組織内に蓄積できるクラウドシステムを提供したいと考えています。
私たちのサービスの本質は美味しいものをつくることにあります。クラウドシステムを活用することで、商品開発におけるコストを削減できれば、誰もが手に取れる価格帯で、美味しいものを次々と生み出せます。
まずは国内で仕組みを確立させ、さらにその先のステップでは5年・10年先を見据えて海外企業への仕組みの提供を目指します。最終的には、ニーズのある場所であれば国内外を問わず、おいしいものを提供する企業を支援していくことが、私たちのビジョンであり、野望です。
無理に起業するよりもナンバー2の経験を
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
昨今の起業ブームの中で私が伝えたいのは、無理に起業する必要はないということです。
そしてもし起業するかどうか迷っている方がいたら、まずは起業家そのものを目指すよりも、まずはナンバー2として経営を支える経験を積むことを強く勧めたいと思っています。
起業家を支えるナンバー2には、優れた常識感覚とバランス感覚が不可欠です。その経験を重ねることで、次は自分でも種をまいてみようと自然にステップを進めていけるでしょう。
さらに重要なのが、「プロダクトアウトかマーケットインか」という考え方です。私は、最初は必ずマーケットイン、つまりニーズから始めるべきだと考えています。
これはゲームでいえばどのステージから始めるかという話に近いです。自分のつくったものをどう売るかを考えるのは、いきなり上級ステージから挑戦するようなものです。もちろん不可能ではありませんが、難易度は非常に高いです。
ですから、起業初期は市場のニーズから入るのが最も確実です。そして、もしプロダクトアウトから始めるにしても、失敗しても落ち込む必要はないという気持ちで臨むことが大切だと思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:上村 友一氏
2008年3月東京調理師専門学校卒業。2008年4月(株)ひらまつ入社。アジェントASO配属。ミシュランガイド2つ星獲得。欧州系レストランで修行後、大手携帯通信キャリアの営業職に従事。2019年8月 食品OEMプラットフォームを展開するフードテック企業を創業。代表取締役就任。2020年10月退任。2021年2月(株) デリズマートを創業。
企業情報
|
法人名 |
株式会社デリズマート |
|
HP |
|
|
設立 |
2021年2月5日 |
|
事業内容 |
食品流通業界の調達DXサービス |
関連記事