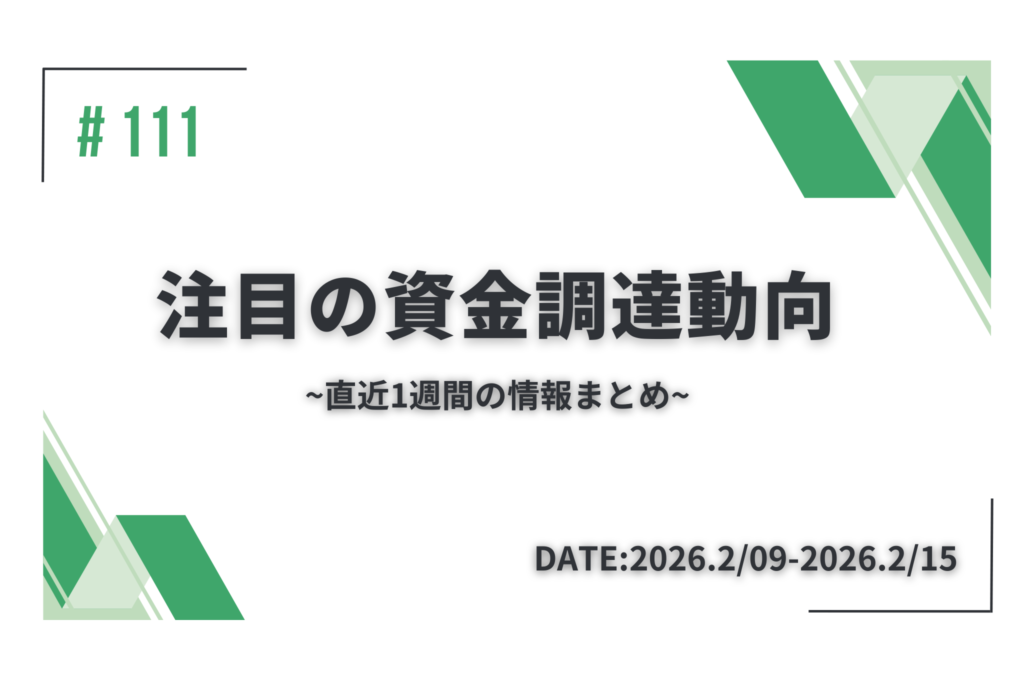【#541】1年目から結果を出す農業支援。「診断」で現場を変えるAIブレーン『e-kakashi』|代表取締役 CEO 戸上 崇(グリーン株式会社)

グリーン株式会社 代表取締役 CEO 戸上 崇
グリーン株式会社は、農業の意思決定を支援するAIブレーン「e-kakashi」を提供する企業です。データを取るだけでなく、植物生理学や栽培学などの専門知識とAI技術を融合させています。代表取締役 CEOの戸上 崇氏に、事業内容や今後の展望なども含めて詳しくお聞きしました。
1年目から農業の生産性をUPする農業AIブレーン
事業の内容をお聞かせください
栽培における意思決定を支援する「e-kakashi」を提供しています。
環境センシングと呼ばれるIoT技術で環境データを取得し、集めたデータを単純に見える化するだけではなく、AIで処理・分析し、栽培に役立つ情報として提供しています。そのため導入したその日から、データを使って栽培に役立てることができるのです。
また、植物の生長を阻害する要因を特定する、もしくは植物の光合成がしにくい環境になっていないかなど、植物が環境をどの様に感じているのかを容易に分析できる機能を備えています。
農業情報工学という分野では、植物生理学、植物病理学、栽培学、園芸学といった学問とITの融合に加えて、栽培現場の知識が必要なため、こうした診断に特化している企業は極めて少ないです。
そのような高度な技術が必要な、植物にとっての環境がいいかどうかを読み解き、診断できる点こそが弊社の大きな強みです。
事業を始めた経緯をお伺いできますか?
高校卒業後、オーストラリアに渡り、現地の大学の応用科学部で地理情報システムとリモートセンシングを学びました。
そこで農業に関する課題が与えられました。地図データ、収穫量、肥料などのデータから様々な情報を読み解く技術が、非常に面白いことに気付きました。
卒業後、日本に帰国し、三重大学で農業ICT分野の研究に携わり、自分の研究が生産性向上や技術継承に貢献できることに喜びを感じ、博士課程まで進みました。
博士課程修了のタイミングで、私の研究成果を社会実装するのであれば、民間企業でしか叶えられないと考えました。
そこで2013年に大手通信企業に入社し、私の研究していた分野である農業ICTの知見を活用して「e-kakashi」の事業推進に携わることになりました。その後アプリとデバイスをリニューアルさせ成果が出てきたタイミングで、より事業に集中したいと思い、2024年に独立しました。

植物・農家・企業それぞれが喜ぶ形を追求する
仕事におけるこだわりを教えてください。
植物目線、農家目線、そして関わってくださる企業さん目線であることです。
仕事を通して、目の前の方の課題を解決でき、感謝の言葉を直接言っていただけることは、なかなかありません。その声を積み重ねていきたいです。
そのためには、農家さんが抱えている現場課題に向き合う必要があります。現時点で課題だとも思っていないことでも、植物目線の発想ではデータを活用して改善できることはたくさんあることに気付き、それらには非常に価値があります。
農家さんにとってメリットがあるだけではありません。例えば農作物に病気が発生しそうだとわかった時に、地域の資材屋さんがタイムリーに農薬の提案やサポートができるようになれば、農業の正しい循環が綺麗に回り始めるのではないかと考えています。
起業から今までの最大の壁を教えてください
起業してから今まで、行動変容を起こすことの難しさに課題を感じています。
例えば水やりは雨まかせという考え方は根強い一方で、気象データや土壌データに基づく最適なタイミングは、収量や品質に直結します。
近年の干ばつの影響に加え、ある団体との共同取り組みでは天候任せにせず、必要な時に必要量の水を与えることで成果が出始めました。実際、導入から半年で収穫量の変化が確認された事例もあります。
また、とある「e-kakashi」の導入者は毎日データをチェックし、水やりや施肥の判断に活用しています。都市型農業のように畑が遠くても、今日は畑に行くべきかをデータで判断でき、無駄な往復を減らして作業を効率化できます。こうした事例が蓄積され、現在は必要な時に必要なだけ与えることが大切であることを広く届ける段階に入っています。

お客様の課題解決に貢献し続ける
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
農家さんやパートナー企業さんから感謝の声をいただくことです。自分たちの事業が社会に役立っている、課題解決につながっている実感が、モチベーションです。
あるJAさんでは、農家を始めて3年目の方の生産量が昨年度のベテランの方の生産量を上回ることができたという成果を出しています。たった半年で技術継承が進む可能性が十分にあり、さらに生産性も上がる可能性があります。
また、食の安全保障という観点で考えた時、日本国内で生産を維持できる体制を作る必要があります。食は人への栄養の供給といえるため、絶対に維持しなければいけないし、国内で供給できる体制を作る必要があります。
そこにコミットできるのが私たちのソリューションであり、社会課題の解決に貢献できると考えています。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
私たちが解決したいのは、食料問題です。食料が十分あって、毎日お腹いっぱい食べられれば、貧困国の子どもたちが学校に行けないというような問題もなくなります。
教育を受ける機会が得られれば、もっと違う可能性が広がるはずです。私たちは、このビジネスを通して食料問題を本気で解決し、それによって紛争も減らしたいと考えています。
例えば、コロンビアの農村部では、貧しくて学校に行けない農家の若者たちが、家族を養うために望まぬ職業に従事せざるを得ない現実があります。
そこで、農村部で科学的に農業を読み解ける農家さんを育成すれば、この課題を解決できるのではないかと考えました。そういう方々は、栽培コンサルタントとして活躍できますし、貧困につながる問題も軽減できます。
この現実を変えるためにも、さらに力を尽くしていきたいと考えています。

社会問題の解決より先にやるべきこと
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
社会課題と現場課題を見極めることです。
例えば技術継承は社会課題ですが、技術継承のためにデータを取るだけでは不十分です。具体的にどのデータを取れば何が解決できるのかまで考える必要があります。
社会課題から入ると、解決は難しいです。なぜなら、社会課題は現場課題を解決した後に解決されるものだからです。社会課題の中には現場課題が入っており、現場課題を掘り下げて考えていくとうまく解決することができます。
もう一つは、諦めないことです。社会実装の目処が立たない時、思うような成功事例が出ない時は必ずあります。それでも諦めずに進み続けることが大切だと思います。
本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:戸上 崇氏
オーストラリア・ニューサウスウェルズ州公立チャールズスチュアート大学卒業後、国立三重大学大学院の修士課程に進学し、農業ICT分野の研究に携わる。 2012年 同大学院博士課程にて、農業現場におけるセンサーネットワークおよび情報の利活用に関わる研究で博士号を取得。
2013年1月にソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)に入社以降、e-kakashiプロジェクトの技術開発をリードし、e-kakashiの事業責任者として事業に従事。 2018年から海外を対象とした政府間のスマート農業プロジェクトのプロジェクトリーダーを務め、コロンビア、エクアドル、ブラジル、エチオピア、モンゴル、ウズベキスタンにてプロジェクトの推進実績を持つ。2024年にグリーン株式会社を創業、ソフトバンク株式会社よりe-kakashiの事業譲渡を受け、同社にてサービス提供を開始。
このほかアメリカの”Science”主催の”Science Robotics meeting in Japan”、”Science Webinar”、米州開発銀行主催FOROMIC2018、インターアメリカンダイアログとラテンアメリカ協会主催で米国政府や企業・研究機関並びに在ワシントンの中南米・日本関係者などを対象としたセミナーや国務省などの米政府機関・米大学・研究機関の代表や駐米ペルー大使など約30名の専門家によるラウンドテーブル、JICAの研修プログラム、大学や農業大学校での特別講義、第8回アフリカ開発会議のサイドイベントへの登壇など多岐にわたり講演活動を行っている。
また、農地や山林を生かした脱炭素に力を入れる福岡県久山町の小学校2校で、子どもの頃から農業や食料に関心を持ってもらうため、スマート農業に関する出前講座を開くなど、農業や先端技術などを将来につなげる活動も精力的に行っている。
2023年度〜ひろしま型スマート農業推進事業に係るサポートチームアドバイザーに就任。
企業情報
|
法人名 |
グリーン株式会社 |
|
HP |
|
|
設立 |
2024年4月18日 |
|
事業内容 |
|
関連記事
RANKING 注目記事ランキング
- 【#468】意見が政策につながる社会へ。市民参加型SNSと自治体向けAIで「デジタル民主主義」を推進|代表 伊藤あやめ/谷口野乃花(Polimill株式会社)起業家インタビューインタビュー

- 【#363】お金いらずで寄付ができるECサービス、世界を救う第一歩に|代表取締役 藤本 巴(株式会社ギバース)起業家インタビューインタビュー

- 【#544】保護犬・保護猫の命をつなぐ。福祉と仕組みづくりで、寄付に頼らず築く持続可能な社会|CEO / 代表取締役 伊東 大輝(株式会社ANELLA Group)起業家インタビューインタビュー

- 【#268】定年齢層向けイベントアプリ『シュミタイム』で、高齢者の社会的孤立を救う。|代表取締役CEO 樗澤 一樹(株式会社ジェイエルネス)起業家インタビューインタビュー

- 【#578】赤ちゃんの感情を可視化するAIアプリ『あわベビ』で、産後うつの課題を解決|代表取締役・CEO 中井 洸我(株式会社 クロスメディスン)起業家インタビューインタビュー