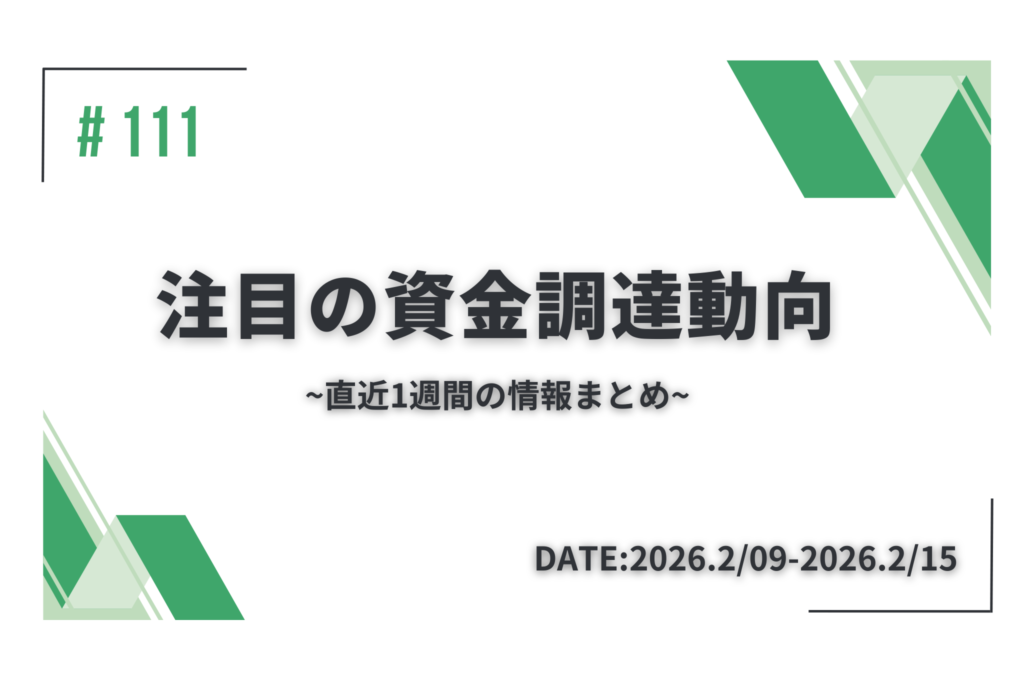【#548】学習完了率を2倍に。対話とAIで実現する次世代の人材育成プラットフォーム『Matter』|代表 百野 拓也(株式会社Matilda Books)
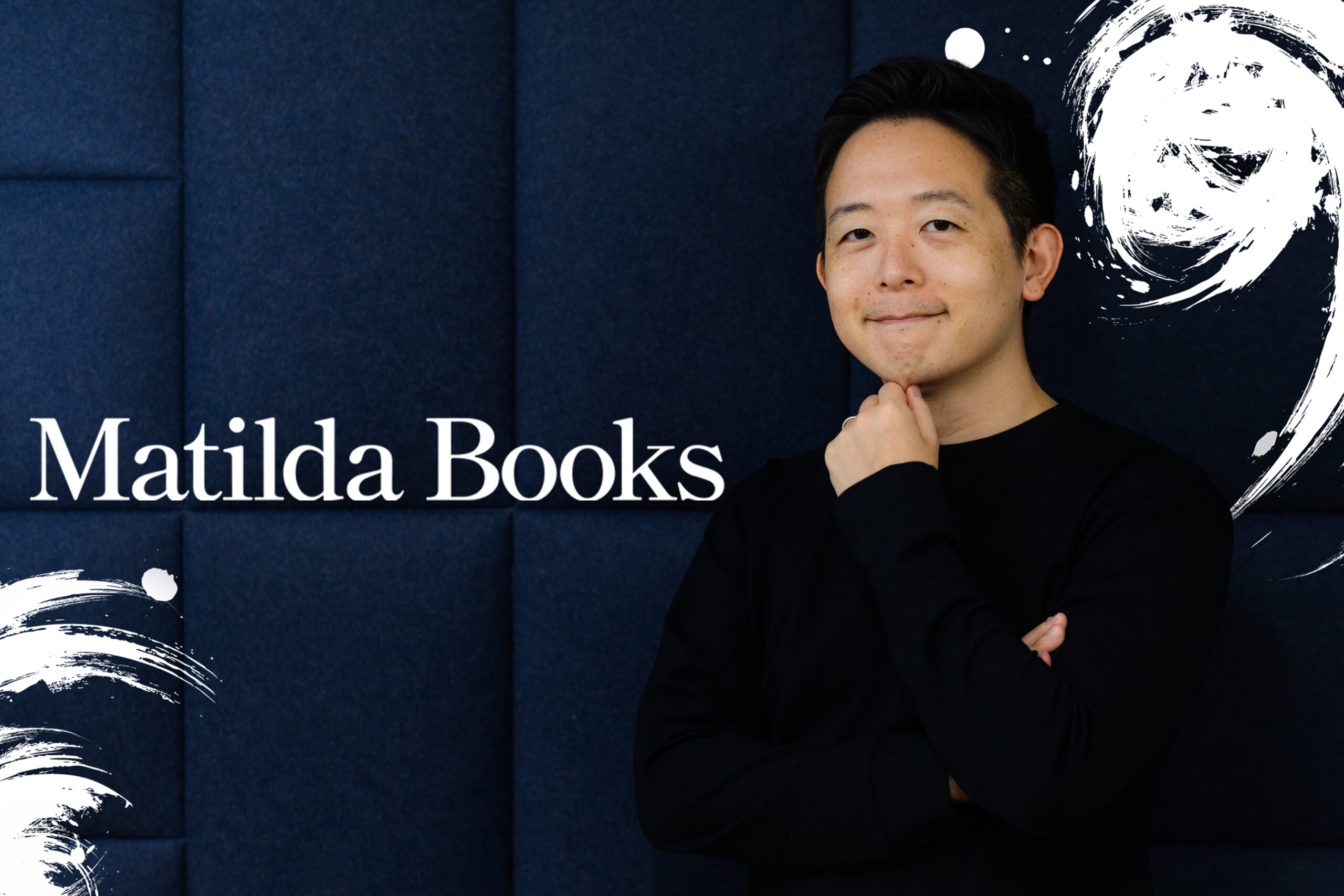
株式会社Matilda Books 代表 百野 拓也
株式会社Matilda Booksは、対話を通じた人材育成を支援するSaaS企業です。従来の一方向的な社内学習とは異なり、AIがグループ学習の場を自動化し、従業員同士の対話から個々のスキルを可視化。人材育成の効率化とコスト削減を実現しながら、組織の持続的な成長を支えます。代表の百野 拓也氏に、事業内容や今後の展望なども含めて詳しくお聞きしました。
一方的な学習から従業員同士が学び合う形へ導く
事業の内容をお聞かせください
事業は大きく2つあり、人材育成を支援するSaaS「Matter」の提供とコンサルティングです。
「Matter」では、企業内での従業員同士の学び合いを促進し、そこで生まれる対話をデータとして提供するサービスを提供しています。これは経済産業省も推進する「スキルベース」という潮流に沿ったもので、企業の従業員のスキルを可視化し、育成に活かしていく取り組みです。コンサルティングもまた、人材育成の観点から、主に大企業のサポートをしています。
企業が抱える課題は大きく分けて2つあります。1つ目は、DX人材育成やマネジメント研修を行う際の、従業員スキルの可視化が難しいということです。人材やコンサルタントを多数配置すれば可視化自体は可能になりますが、これでは手間とコストがかかってしまいます。
2つ目はeラーニングの効果が見えにくい点です。一方向的な学習になるため、身についているのかがわかりにくいというのがeラーニングの難点です。「Matter」は、インプットした内容をアウトプットする機会や、従業員同士で学び合う文化を作りたいという企業にご利用いただいています。
そんな「Matter」の特徴は、ファシリテーションの自動化です。日程調整やグルーピングなど学習機会の設定が自動的に進行するため、ファシリテーターをアサインする必要がなく、学習者同士の学び合いが促進されます。例えば、受講生が1,000人いるコースで5人のグループを組む場合、200グループを作ることになり管理が負担となってしまいますが、「Matter」ではこれを自動化できます。
もう1つの特徴は、グループ学習中の対話データ解析によるスキル可視化です。会話内容だけでなく、表情や目線も分析し、学習へのエンゲージメントや理解度をAIが判定、結果を人事側にフィードバックします。
通常のeラーニングは個人学習ですが、私たちはグループで学ぶ形式をとっています。例えば学習テーマがプログラミングだったとすると、「習得したプログラミング力を自分の部署でどう活用するか」というような、学んだ内容に関する問いを出し、これについてグループでディスカッションをします。
問いへの答えを共有し合うことで刺激を受け、学びのモチベーションも高まります。そうして深い理解へと繋がるのです。
私たちがグループ学習を重視する理由は、大手人材企業などの調査でも、グループ学習が学びのモチベーション向上や理解を深めることに有効であると示されているためです。私たちはこの学び合いを「ピアラーニング」と呼んでいます。

導入企業の特徴と、具体的な成果を教えてください
導入企業は主に人材育成に投資をしている大企業で、その中でも特に、DX人材育成やリスキリングのニーズが高い企業が中心です。営業職が多い企業などで、従業員のデジタル化推進の手段として活用いただいています。
そのうちの多くは、大手の研修会社との連携で導入いただいており、既存の研修プログラムに組み込む形で提供しています。
例えば、およそ1,000名が参加する人材育成プログラムを提供するお客様においては、口座の難易度の高さからこれまでに多くの離脱者が生じていました。理由は、オンラインで一方的に受講する形式では孤独感を感じやすく、困った時に相談できる相手がいないためです。
そこで、従業員同士が支え合い、学び合う文化を作りたいと要望する企業が私たちのサービスを導入するようになりました。過去には、ピアラーニングを活用することで、学習完了率が2倍に向上した例があります。また、グループ学習のフォローにかかっていた人件費を約40%も削減したという事例もあります。
利用者からは、他の受講者がどのような気持ちで講座を受けているのか、どのように学習しているのかを知れたことに対する満足が多く寄せられています。参加者の9割以上が当サービスを評価してくださり、満足度は非常に高いと言えます。
事業を始めた経緯をお伺いできますか?
デロイトトーマツで組織人事のコンサルティングをしており、その後サムライインキュベートというVCで新規事業のコンサルティングを担当しました。
退職後は、フリーランスのコンサルタントとして独立しました。当時はフリーランスのコンサルタント市場が拡大していたこともあって、一人で生活していく分には問題ありませんでしたが、スタートアップでプロダクトを作りたいといった思いが強くなり、開発を始めました。
社名の「マチルダブックス」は、当初出版業界の支援を目指していたことに由来しています。書店が閉店していく状況に貢献したいと考え、名前をつけました。
しかし、出版業界は私のバックグラウンドとは異なり、業界の課題も深く、十分に貢献できないと判断しました。そこでピボットし、自分の経験を活かせる現在の事業に至ったのです。
従来の研修の形態にどのような課題を感じていましたか?
学習のゴールが明確でないため、学ぶ意欲が湧かないといった構造的な問題です。
私自身、研修があまり好きではなく、意味を感じられないことが多かったです。また統計データによると、日本の社会人は諸外国と比較して自己学習の時間が圧倒的に少ないと言われています。真面目な国民性なのに、社会人になると勉強しなくなる理由は「キャリアは会社が与えるもの」という意識が定着しているからだと思います。
解決策は、会社が必要とするスキルと従業員が持つスキルのギャップを可視化し、育成の道筋を明確にすることです。「この育成を受ければこのポジションに就けて、給料も上がる」とわかれば、学ぶ意欲が生まれます。
例えばエンジニアはスキルが顕著に表れるため、自発的に学習し、それに連れて給料も上がります。これを他の職種でも実現すべきだと考えています。スキルの可視化が進めば、学習の目的が明確になり、構造的な問題を解決できるのです。

相手の目線に沿った価値提供をする
仕事におけるこだわりを教えてください。
お客様にとっての価値は何かを考え、相手の視点に立った価値提供をすることです。
私は営業からキャリアをスタートし、その後コンサルティングに携わってきたため、常にお客様と向き合い続けてきました。お客様の課題は何で、それに対して何を提供できるのかを考えるという基本姿勢は、この経験から来ているのだと思います。
私たちはツール提供だけでなくコンサルティングも提供できるため、お客様の状況に応じた柔軟な価値提供を心がけています。これはこだわりと言うよりも、当たり前にやっていることに近いです。
全てが自分次第という環境で働ける喜び
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
自由に意思決定でき、全てが自分次第という環境で働けることです。
スタートアップを経営すると大変なことも多いですが、自由に決められて、全てが自分次第といった環境で働くことが自分に一番合っていますし、喜びをもたらしていると思います。
また、ありきたりかもしれませんが、自分たちが企画して開発したソリューションがお客様に受け入れて、価値を提供していると感じる瞬間がやりがいを大きく感じる部分です。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
お客様に日常的に使っていただける機能を、より拡充したいと考えています。
私たちのプロダクトには「学び合いの促進」と「対話データからのスキル可視化」といった2つの特徴があり、中でも強みとなっているのがスキル可視化です。
スキル可視化というのは非常に難しい技術です。Zoomの録画を文字起こしして、それをChatGPTに入れるだけでは、精度の高い可視化は実現しません。それだけでは、AIが不要な情報まで拾ってしまうため、プロンプトを丁寧に積み上げて精度を高めていく必要があります。この技術の蓄積が私たちの差別化ポイントになっています。
ただ、ピアラーニングや学び合いは、あくまでも学びの手段の一つです。今後は様々な育成シーンに対応できる機能を増やしていきたいと考えています。例えば1on1のロールプレイで部下役のAIを立てて練習できるようにするなど、リアルな練習の場を提供するのに加え、そこでの会話内容やスキルを全て解析できる仕組みを作ります。
セールストレーニングやAI面接など、育成・練習・研修といった様々なケースに対応したAIを提供し、そこで得られたデータを全てスキルとして蓄積していきます。ピアラーニングだけではお客様との接点が限られてしまうため、機能拡充によって接点を増やし、ゆくゆくは「Matter」を日常的にご利用いただけるサービスにしていきたいです。

将来的にどのような組織にしたいとお考えですか?
ミッションに共感してメンバーが熱く働ける、独自のカルチャーがある組織にしたいと考えています。
本来はスタートアップらしく、メンバーが情熱を持って働く組織が理想です。ですが、社内には私含めコンサルティングファーム出身の方が多く、今現在はプロフェッショナルな雰囲気が漂う組織になっています。
コンサルティングファーム出身者は独立志向が強く、淡々と仕事をこなす傾向があります。自分の仕事には誇りを持っていますが、会社への帰属意識は薄く、いつでも転職できるといった感覚を持っている方が多いです。
この状況を変えて、弊社ならではの色やカルチャーを持った組織を作りたいと考えています。
失敗した時の戻る場所を作っておく
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
自分の経験からしか語れませんが、スキルを身につけておくことをお勧めします。会社がうまくいかなくなっても、なんとかなるという状態を作ってから起業する方がいいと私は思います。
少し堅実すぎるかもしれませんが、「困ったときに戻る場所がある」という安心感があることで、様々なチャレンジができるからです。
もちろん、勢いで飛び込んでいくのも良いでしょう。ただ、自分の人生には自分で責任を持たなければいけないので、何か一つでも拠り所を持った上で起業する方が、心にゆとりを持って事業に取り組めると思います。
採用を強化されているそうですね。どのような人材を求めていますか?
今、一番採用に力を入れている職種はエンジニアです。現状では、開発の一部を外注しているため、これからの開発の中心に立てるようなリードエンジニアやCTO候補を求めています。
もう一つは、ビズデブの人材です。今後、ピアラーニング以外にも様々な機能を開発していきたいと考えています。サービス提案における対話を通じて、お客様のニーズを汲み取りながら「これを作ろう」と小さな事業を立ち上げていける方が必要です。
私たちはコンサルティングサービスも提供していますが、現在、チーム構成はマネージャークラスが大部分を占めています。意欲的な若手の方で、これからコンサルティングスキルを学びたい、あるいはスタートアップでサービス開発に携わりながら成長したいといった方にも、ぜひ来ていただきたいと思っています。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:百野 拓也 氏
企業情報
|
法人名 |
株式会社Matilda Books |
|
HP |
|
|
設立 |
2022年5月25日 |
|
事業内容 |
|
関連記事