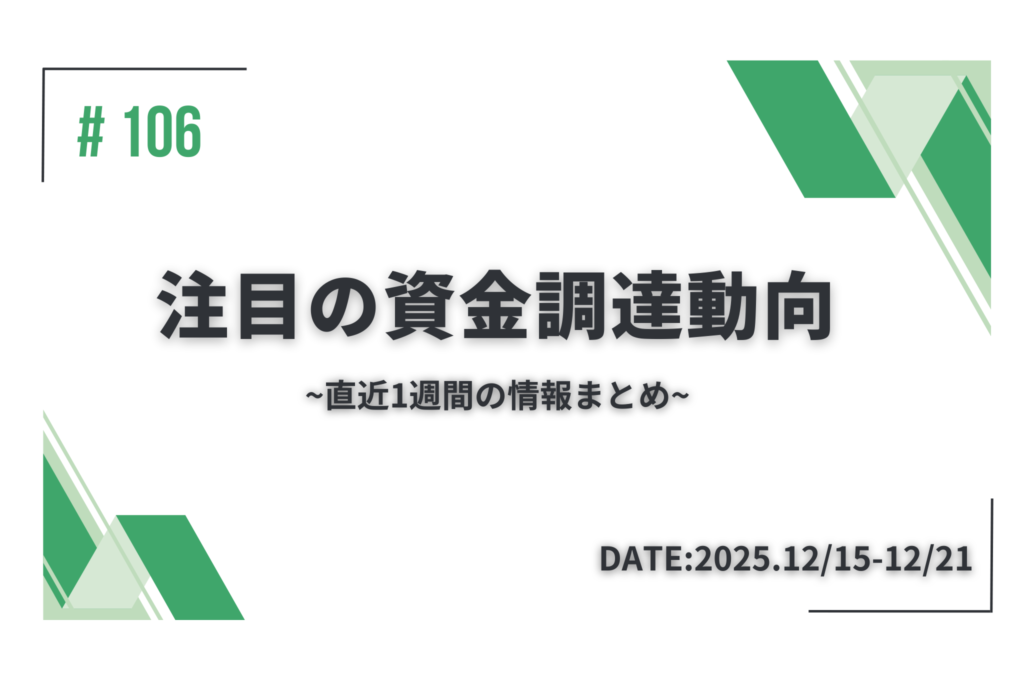株式会社Rabee 代表取締役 上松 勇喜
外部委託は原則として使わず、自社で育成したクリエイターだけでシステム開発に取り組む株式会社Rabee。さらに採用する人材は異業種から転職してきた未経験者が中心。業界でも珍しいスタイルを貫くその背景には、代表取締役の上松勇喜氏の並々ならぬ想いがありました。今回は上松氏に起業の経緯や、経営者として直面した壁についてお聞きしました。
自社で育成したクリエイターチームが、一気通貫で開発に取り組む
事業の内容をお聞かせください
弊社はIT領域で3つの事業を手がけており、1つ目がクリエイター育成、2つ目が受託開発、そして3つ目が自社サービスの開発です。
クリエイター育成では未経験の人を採用してエンジニアやデザイナーとして教育し、現場経験を積んでもらい、一流のクリエイターへと育てています。弊社では経営陣も全員が現役のクリエイターですので、クリエイターとして働く側の気持ちもよく分かりますし、現場でリアルに必要とされるスキル習得を指導できるのが強みです。
受託開発の事業は、そうして育成したクリエーターたちがチームになって取り組んでいます。このサービスの強みとしては、企画からコンセプト設計、ワイヤー、デザイン、開発や運用までを一気通貫で請け負える点です。ただ、運用の手間はできるだけかからないようにシステム開発を行っているので、基本的には顧客企業側でしっかりと運用ができる形で納品しています。
さらにクリエイター育成のノウハウを生かし、顧客企業の従業員の方にプログラミングなどのスキルを習得してもらい、修正や運用がしやすくなるようサポートもさせていただきます。
3つめの自社サービスの開発ですが、現在はタイピング練習サービスの「Ankey」や、エンジニア同士でコードを共有できるコミュニティサービス「Runstant」などを運営しています。また、献立をSNS感覚でシェアできる「menuble」は、デザイナーの1人が「こういうの作りたいです」と提案してきたもので、面白そうだからやってみようと社内で盛り上がって実現しました。
やはり、自分たちが作りたいと思ったものを作るのが一番楽しいですし、従業員にはクリエイターの仕事の楽しさを体感する機会を沢山持ってほしいと考えています。そのため今後も自社サービスの開発には力を入れていきたいです。
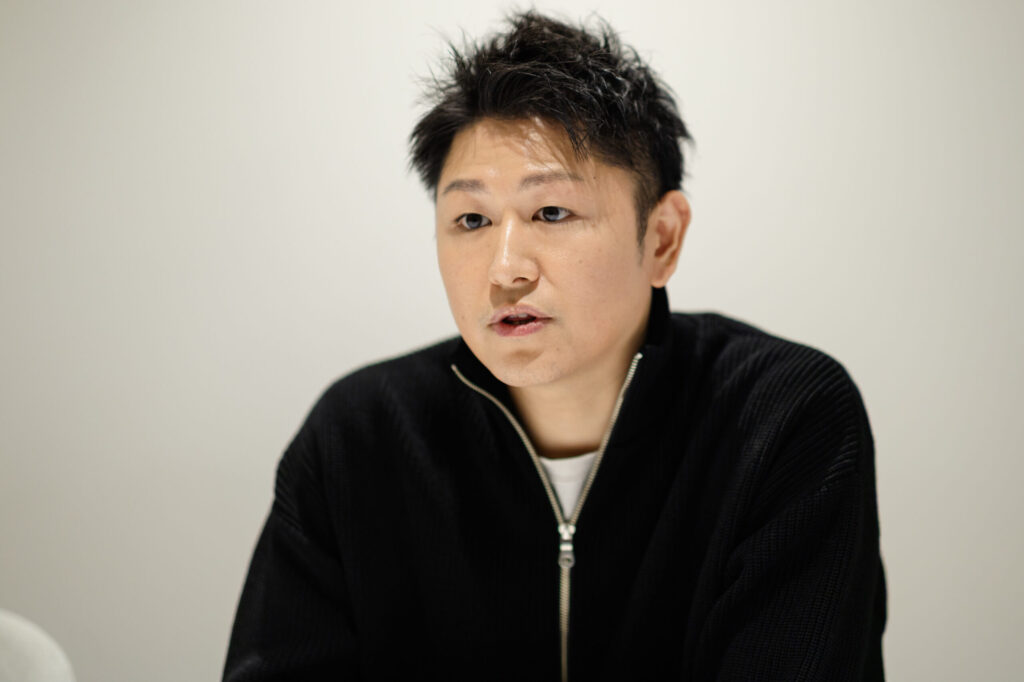
事業を始めた経緯をお伺いできますか?
私は10年以上、現場のエンジニアとして働いてきましたが、ずっと「こんなに楽しい仕事は他にないんじゃないか」と思いながら、夢中で取り組んできました。
しかし、地元に帰るたびに、友人たちから「仕事がつまらない」「辞めたい」といった愚痴を聞くことが多く、強い違和感を覚えるようになりました。自分にとって仕事は楽しいものだという感覚が当たり前だったからこそ、そのギャップに戸惑い、衝撃を受けました。
「それなら、自分で楽しく働ける環境をつくろう」、そう考えたのが起業のきっかけです。クリエイティブな仕事に挑戦できる場所をつくれば、もっと多くの人が仕事を楽しいと思えるのではないか?とそんな想いが芽生えました。
構想を練っていた頃、前職の同期だった友人と再会しました。彼は転職先で仕事に退屈している様子でした。そこで、「プログラミングのハードルを下げて、もっと気軽に誰もが取り組めるプラットフォームをつくりたい」という構想を話したところ、なんと翌日、彼は本当に会社を辞めてきたんです。
「で、会社の登記はいつするの?」と聞かれ、私も腹を括りました。そこから、彼と2人で会社を立ち上げることになりました。
未経験者を育てることを前提にしたこともあり、社員はすぐに集まりました。ただ、当然最初は収入もなく、数ヶ月間は私個人の貯金を切り崩して社員の給与を支払う日々が続きました。不安な毎日でした。
そんな中、ありがたいことに、役員メンバーそれぞれの前職からのご縁にも助けられ、設立間もない時期にもかかわらず複数のご依頼をいただくことができました。おかげさまで、事業は初年度から黒字化。以降も一度も外部からの資金調達をせず、自己資本・手元資金のみで運営を続けています。
目の前の仕事ひとつひとつに真摯に向き合い、誠実にやり遂げることで信頼を積み重ね、また新たなご縁につながる。その繰り返しの中で、おかげさまで仕事が途切れることなく続き、今年で7期目を迎えることができました。
これからも、「まずは目の前の仕事に誠実かつ全力で向き合う」という姿勢を大切にしながら、信頼を積み重ねていきたいと思っています。
どんな状況でも忘れない「クリエイティブは面白い」という気持ち
仕事におけるこだわりを教えてください。
仕事をするうえで大切にしているのは、「クリエイティブを学んだり、何かをつくったりするのは、とにかく楽しいことだ」という姿勢です。
やればやるほどできることが増えていきますし、実力や経験を積めば、これほど大きな裁量を持って取り組める仕事はなかなかないと思います。もちろん、面倒なことや大変な場面もありますが、それでもこの前提さえ忘れなければ、基本的には楽しく仕事ができるはずです。
私の中ではプログラミングやデザインの仕事は本当に面白く、これを知らずに死んでいくとしたらこんなに勿体ない話はないと思っています。全ての人が一度はこの仕事を経験し、その上で合わなければ別の職種を選べばいいと思っているくらいです。クリエイティブな仕事にはそのくらいのポテンシャルがあるというのが、私の考えであり仕事の軸にもなっています。
もうひとつ大切にしているのが、「仕事を選ばないこと」です。どうしても「成長のため」と考えると、目の前の仕事を選り好みしてしまいがちですが、それではいつまでも本当に重要な仕事は任せてもらえません。
クリエイティブという軸は持ちながらも、雑務や領域を超えた仕事にも積極的に取り組む。そうした姿勢が周囲からの信頼につながり、それが巡り巡って、クリエイターとしてさらに大きな成長につながる仕事を任されるようになっていく。
そんな良い循環を、チーム全体で作っていくことが大切だと考えています。

起業から今までの最大の壁を教えてください
一番苦労をしたことは、組織構築の部分です。かつて弊社では、仕事をする人としない人で完全に分かれてしまった時期がありました。当時は実質2割くらいのメンバーで売上のすべてを作っている状態だったのです。
その問題に向き合わないまま、新型コロナウイルスの感染拡大でリモートワークが始まり、状況はますます悪化しました。有休や日報などもチェックできておらず、言わば性善説に基づいて従業員任せにしていたため、任せた仕事をしなかったり副業に熱中したりする従業員も少なくありませんでした。
今振り返ると、当時は誤解を招くようなコミュニケーションが多かったなと私自身反省しています。毎日のように一緒に飲みに行ったり、プライベートでも遊んだりと、立場が曖昧になるような距離感で接してしまうことも少なくありませんでした。
また、スケジュールやクオリティの都合で、任せたはずの仕事を途中で巻き取って自分でやってしまう場面も多く、相手の成長機会を奪ってしまっていたなと。
組織としてこのままではいけないと考え、もう一度会社としてのビジョンを伝えて意識づけを行い、コロナの中でもオフィスに出社して働く環境を整えました。その方針に合わずに半数近くの従業員は離職してしまいましたが、それから少しずつ人は増えていき、今はまた当時よりも多い人数で働くことができています。
組織構築のところでは役員の間でも意見が割れるところがあって、楽な道のりではありませんでした。けれど、その問題から逃げずにしっかりと向き合い、会社のカルチャーに合った人を採用するという努力を地道に続けてきたことで、今のチームが存在するのだと考えています。
会社の未来を信じて残ってくれたメンバーのために
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
すでにお話ししたとおり、組織構築を真剣に考えるようになった段階で、続々と従業員が会社を離れていってしまった時期がありました。けれどそんなときでも、半数以上の従業員はRabeeという会社を信じて残ってくれました。今は経営者として、彼らの気持ちに応えたいという想いがモチベーションになっています。
オフィスに出社すると、あちこちでメンバーが楽しそうに相談したり、議論したり、つくったものを見せ合ったりしている光景をよく目にします。
そんな瞬間にふと、「本当に起業してよかったな」と感じます。
さらに言うと、起業してから色々なことを経験しましたが、やはりクリエイターは面白いという信念は揺らぐことがありません。好きな仕事だからこそ、これからも何があっても続けていきたいと思っています。そして、そんな想いを共有できる仲間が増えていくことが、何よりの喜びです。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
私たちが目指しているのは、面白いプロダクトをつくり続ける「最強のクリエイターチーム」です。
「世界を変えたい」「大きなことを成し遂げたい」といった壮大な目標は持っていません。信頼できる仲間たちと一緒に、ワクワクしながら面白いものをつくり続ける。そして、そこに周りの人たちも巻き込み、一緒に楽しんだり、喜んでもらう。
そんな状態を目指し、それを途切れることなく続けていくことが、Rabeeのミッションです。
今はエンジニアやデザイナーがフリーランスとして働くことも増えていますが、私たちは「一人でできることには限界がある」と考えています。だからこそ、外部への委託は基本的にせず、自社で育てたクリエイターたちだけでチームを組むことを大切にしています。
お互いにしっかりと意思疎通を図り、チームワークを活かしてこそ、本当に優れたプロダクトが生まれると信じているからです。これからも、一人ひとりが実力あるプロフェッショナルでありながら、仲間と力を合わせてものづくりができる、そんな場をつくり続けていきたいと思っています。
実は、Rabee は上場を目指していません。外部から資金を入れると、どうしても「しがらみ」が生まれ、自分たちが本当に面白いと思うものを自由につくれなくなる。そんな経験を、私自身が前職で痛感したからです。
だからこそ、Rabeeは株式を役員で保有し続け、自分たちの裁量の中で決断し、動いていくと決めて経営してきました。これからも、自分たちが本当に良いと思えるプロダクトを、ひたすら世の中に届けていきたいと考えています。

「何をやるか」よりも「誰とやるか」
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
ベンチャーらしくない考え方かもしれませんが、私は仕事において本当に大切なのは「何をやるか」ではなく、「誰とやるか」だと思っています。
起業しようか悩んだときも、最終的な判断の軸はそこでした。自分の想いや信念に共感してくれて、一緒に頑張れる仲間がいるかどうか。そこさえ確信できれば、きっと楽しくやっていける。そんな気持ちで起業しました。
もし今、自分のやりたいことを話してみて、それに「一緒にやろう」と本気で言ってくれる信頼できる仲間がそばにいるなら、挑戦してみるのもいいかもしれません。
採用にも注力しているようですが、詳しくお聞きできますか?
弊社でもチームづくりで苦労をした時期があるので、現在は会社のビジョンやカルチャーに共感してくれることを重視して採用を行っています。経験のあるデザイナーやプログラマーだと他社のカルチャーに染まっていたり、自分1人で仕事をする癖がついていたりするので、採用は未経験の人材を優先しています。
弊社で現在活躍しているメンバーは、前職が美容師や学校の先生、バーの店長など、経歴も本当にさまざまです。まったくの未経験で始めても、活躍することは十分にできます。大切なのは「目の前の人の役に立ちたい」「チームに貢献したい」という意識だと、我々は考えています。
Rabeeでは現在も一緒に働いてくれる仲間を募集中です。チームワークで大きな仕事ができるクリエイターになりたいとお考えの方は、ぜひご応募ください!
▽お問い合わせはこちらから
本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:上松 勇喜氏
1988年、福岡県生まれ。学生時代から趣味でアプリやゲームの開発を始める。
2010年、コンシューマーゲーム開発会社にゲームプログラマーとして入社し、複数のタイトルの開発に携わる。
2012年、株式会社ディー・エヌ・エーにエンジニアとして転職。ソーシャルゲームや教育コンテンツの開発に従事。
2018年、株式会社Rabeeを創業。クリエイターの育成に取り組みながら、受託開発や自社サービスの開発を行っている。
企業情報
|
法人名 |
株式会社Rabee |
|
HP |
|
|
設立 |
2018年8月15日 |
|
事業内容 |
|
関連記事