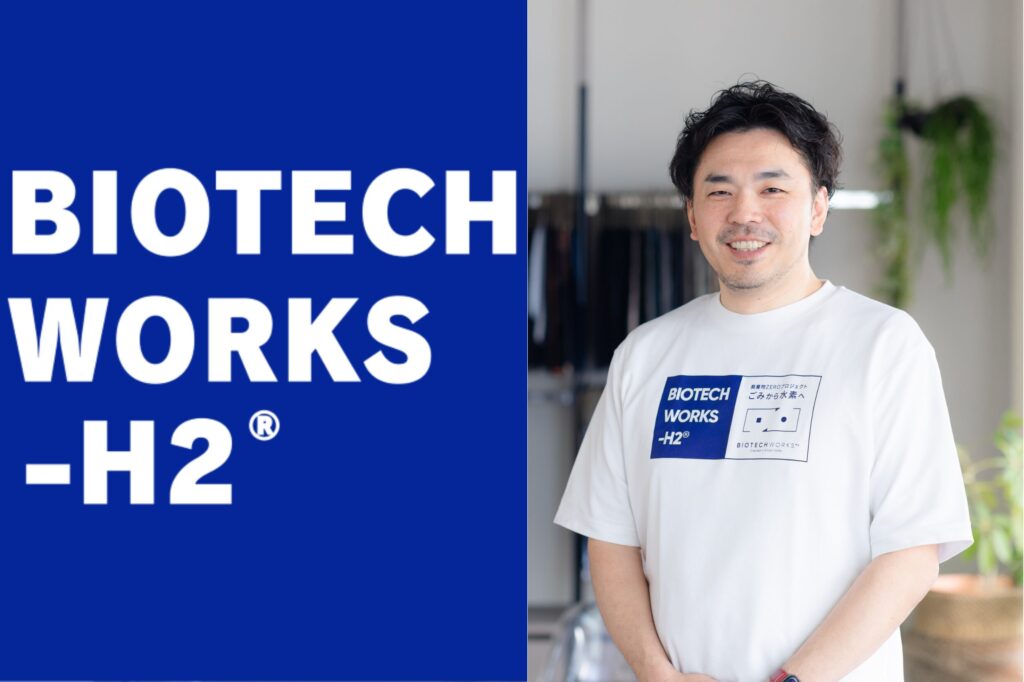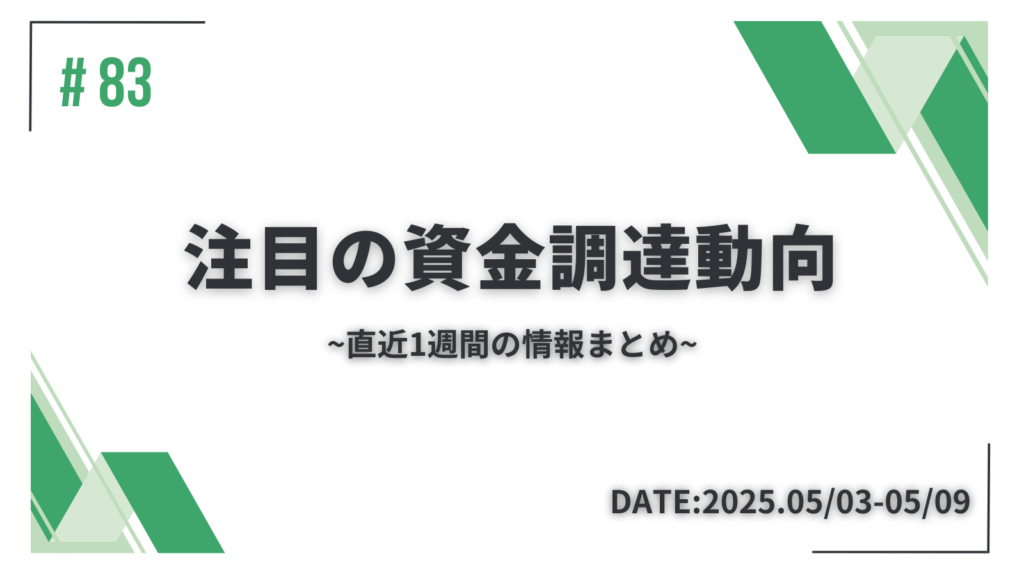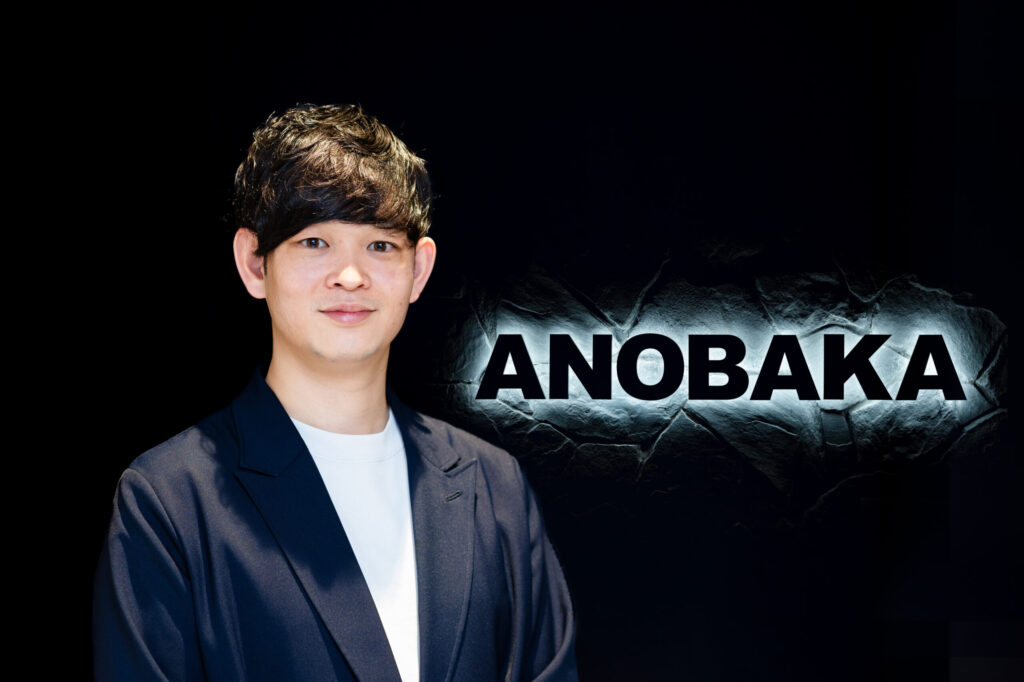【#000】AR技術を用いた新しいスポーツ「HADO」で人と人、国と国のつながりを作る|CEO/Founder 福田 浩士(株式会社meleap) 

株式会社meleap CEO/Founder 福田 浩士
AR技術を用いて、自分の手から「エナジーボール」を放ち、相手と対戦する新スポーツ「HADO(ハドー)」を開発された株式会社meleap CEO/Founder福田浩士氏に、HADOがいかにして多くのファンを獲得していったのか、その経緯と今後の展開について伺いました。
魔法のようなエナジーボールで戦う「HADO」
事業の内容をお聞かせください
弊社、株式会社meleapは「AR(Augmented Reality:拡張現実)」の技術を使った新しいスポーツであるテクノスポーツ「HADO(ハドー)」の開発・運営をしています。
ゴーグルを装着し、センサーを腕に身に着けると、魔法のように「エナジーボール」や「シールド」を出せるになります。1ゲーム80秒で、ドッジボールのように互いにエナジーボールを投げ合い、当てるとポイントとなるゲームです。
現在、「HADO」は日本では提携店舗を含め全国13店舗でプレーでき、世界39か国に展開しています。国内外で大会も開催していて、2025年以降は100を超える大会が予定されています。
ユーザーの年齢層は小学生から40代までと幅広いです。目的別にユーザー層を見ると、レジャーとして楽しむ方、趣味として続けている方、そして、競技者として大会に参加する方と大きく3つのレイヤーに分かれます。
HADOがスポーツとして面白いのは大前提ですが、コミュニティに魅力を感じて通ってくださる方も多いです。HADOを通してさまざまな人と知り合い、一緒にチームを作って大会出場を目指されています。
普段はスポーツをしていなかったけれど、HADOを始めて運動習慣ができたとおっしゃる方は多いです。テクノスポーツは物理的な接触がほとんどないので、フィジカルコンタクトのある他のスポーツと比べるとケガをしにくいのです。そしてなにより、運動が苦手な人でも楽しむことができます。
サッカーやバスケットボールなど、一般的なスポーツは基本的な運動能力が重要になり、どうしても筋力や持久力、体格が優れている人が有利になります。一方でHADOは、運動能力が高くなくても、戦術やチームワークなどでカバーできるため、運動が苦手な方でも楽しめるのが大きな魅力といえます。
教育現場やイベントなどでも導入されているそうですね。
小学校から中学校、高校、大学、専門学校まで幅広く、さまざまな形でHADOを取り入れていただいています。小中学校では体育の授業のほか探究学習やICT学習として導入されることが多く、ほかにも部活や修学旅行で活用いただくこともあります。
我々はHADOを「新しいスポーツ」として展開していきたいと考えています。2012年からダンスが中学生の保健体育の必修となったように、HADOの部活が創設されて子どもたちの全国大会が開催されたり、トッププレーヤーは進学に有利になったり、そうしたところまで広げていくことを目指しています。
教育以外では、企業やスポーツクラブとのコラボレーションも増えています。HADOはカスタマイズも可能ですので、そのコミュニティならではのコンテンツにして来場者の満足度を上げることができるのです。たとえば、Bリーグの試合会場では、人気バスケ選手のアバターと一緒にHADOがプレイができる体験コンテンツを提供しました。
そのほか、自治体とコラボレーションしてご当地キャラクターをモチーフにしたオリジナルコンテンツを作ったり、地方の観光資源をカスタマイズしてゲームにしたり、さまざまな可能性があります。また、高齢者向けの運動促進ツールとしても十分活用できますので、福祉施設との連携も検討しています。
まだまだ、HADO未体験の方はたくさんいると思います。実際にやってみると、イメージしていた感覚とまったく違います。誰でも楽しめるコンテンツなので、家族や友達、同僚などと一緒に、ぜひ一度体験していただきたいですね。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
大学院に入ってからビジネスに興味を抱くようになりました。起業セミナーや起業塾に顔を出しているうちに、起業への関心が高まっていき、自分の「やりたいこと」を実現するためには起業が必要だと気づいたのです。
僕が「やりたいこと」は、漫画『ドラゴンボール』に出てくる「かめはめ波」を実際に打つことでした。それを実現するためXR技術に着目して研究開発をはじめ、HADOが生まれビジネスへとつながったのです。
XRの技術は専門外でしたが、面白さを感じました。他社の事例を見て、自分なりに考えたり、研究したりしてノウハウを積み重ねていきました。
面白くなければエンターテイメントとしての価値はない
仕事におけるこだわりを教えてください。
「それは面白いのか?」と自問自答することです。僕たちが行っている事業はエンターテインメントなので、コンテンツとして面白くなければ、エンターテイメントとしての価値はありません。
自分たちが心から楽しめるか、面白いと思えるのか、ワクワクするビジュアルを描けているかなど、胸が高鳴る体験を常に想像し続けることを大事にしています。

起業から今までの最大の壁を教えてください
テクノスポーツのマーケットへの売り出し方に苦戦しました。
僕らが「新しいスポーツを作りたい」と言っても、「新しいスポーツだからやってみたい」と手を挙げる人は少ないです。
そこで目をつけたのが、「ショッピングモールで家族と楽しい時間を過ごしたい」「楽しく運動習慣を身につけたい」といった方たちです。
こうしたユーザーの心理を理解して体験を設計していくのは大変でしたが、売り出し方を模索する中で、HADOのさまざまな可能性に気づくことができました。
HADOを世界がつながる文化コンテンツに
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
ARやXRの分野はまだまだ発展途上で、常に技術が進化しています。これからさらに魅力的なコンテンツが作れますし、それによって世界は変わっていくはずです。その先の光景を見てみたいという思いが、僕のいちばんのモチベーションです。
また、ユーザーが店舗やイベントなどでHADOを楽しんでいる姿を直接見ることができるのはやりがいにつながっています。
以前、ある親御さんが「うちの子は不登校で引きこもりがちだったけれど、HADOに出会って外出するようになり、他の子と人間関係を築けるようになった」とおっしゃっていました。
実はこうした話は珍しくなく、HADOは子どもも大人も関係なく、内にこもりがちな人が外に出るきっかけになったり、人間関係を築いたり、運動習慣を身につけたりできるコンテンツでもあるのです。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
類似のサービスを提供する人や企業も出てきていますが、それについてはあまり気にしていません。むしろ、僕らがARスポーツのリーディングカンパニーとして、どう市場を作っていくかを検討しています。
まさに市場を作っている最中なので、スピード感をもってそれを進めていくこと、そして、市場としてきちんと成立させていくことが重要です。
技術の進化スピードは非常に早いです。遠隔対戦やAIを使ったコンテンツなど、取り入れられる新しい技術はたくさんありますので、新しいプロダクトを次々に作ってマーケットに出していきます。
また、数年に一度開催してきた世界大会の規模を大きくしていき、HADOを世界的に人類がつながる文化コンテンツにしていきたいと考えています。オリンピックやワールドカップ、万博など、さまざまな国が参加して一つになるイベントは、いまの時代だからこそ求められるものです。世界の分断が指摘される中、スポーツを通じて国と国とのつながりを作り、平和に貢献していきたいと思っています。

与えられた時間、人生には限りがあるから
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
自分のやりたいことが明確であれば、そこをとことん追求し、挑戦するべきだと思います。
僕自身、最初にHADOをリリースするまでに一年半ほどかかりました。新しいコンテンツを作ったもののリリースできずに終わらせたプロジェクはたくさんあります。新しいものを作ることは決して容易ではありません。
でも、与えられた時間、人生には限りがありますから、「やりたい」と思うことがあるのであれば、チャレンジすべきではないでしょうか。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:福田 浩士氏
東京大学大学院卒業後、株式会社リクルートを経て2014年に株式会社meleapを設立。”かめはめ波”を自らの手で撃ちたいという切実な想いからAR技術を活用し、HADO(ハドー)を作りだす。39カ国にHADOの店舗を展開。2016年からはAR/VR初の大会「HADO WORLD CUP」も開催。「テクノスポーツで世界に夢と希望を与える」というビジョンを掲げ、サッカーを超えるスポーツ市場の創造を目指す。
企業情報
|
法人名 |
株式会社meleap |
|
HP |
https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp |
|
設立 |
2014年1月24日 |
|
事業内容 |
・ARスポーツ・エンターテインメント事業 ・デジタル活用人材育成研修事業 |
関連記事