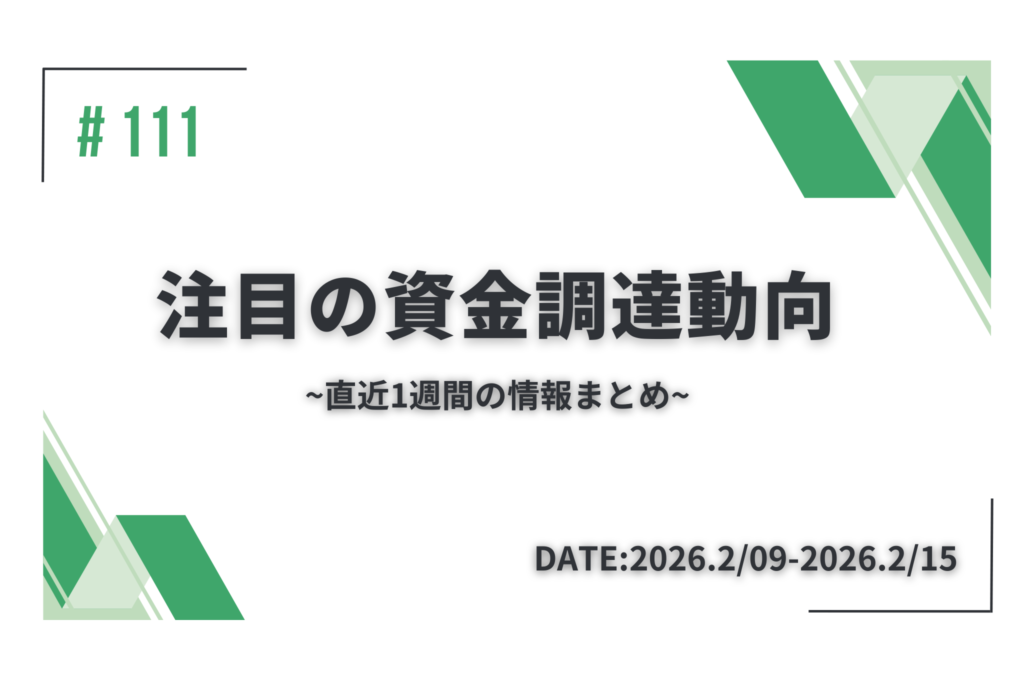【#406】日本をエネルギー大国にする切り札、廃棄物から水素を作る|代表取締役 西川 明秀(株式会社BIOTECHWORKS-H2)

株式会社BIOTECHWORKS-H2 代表取締役 西川 明秀
アパレル事業の世界から一転、廃棄物からエネルギーを生み出す革新へ。西川明秀氏は、衣服の大量廃棄という社会課題に真正面から向き合い、「ごみを水素に変える」という一見突飛だが本質的なアイデアを形にするため、株式会社BIOTECHWORKS-H2を立ち上げました。同社は米シリコンバレーで技術開発を進めてきましたが、西川氏がこだわったのは「最終的な実証は必ず日本で」という信念でした。今回は、強い信念とともに挑戦を続ける西川氏に、事業への想いと未来へのビジョンを伺いました。
廃棄物から生まれた水素を、さらに有益なエネルギーへ
事業の内容をお聞かせください
私たちBIOTECHWORKS-H2が取り組むのは、リサイクル不可能とされてきた廃棄物を水素に変換し、それを起点に再生可能エネルギーを生み出す事業です。「廃棄物=資源」という発想から、日本を世界に誇るサーキュラー・エネルギーモデル国家へと導く。それが私たちの目指す未来です。
なかでも私たちが狙いを定めているのが、カーボンニュートラルの切り札ともいえる「合成燃料(e-fuel)」の分野です。e-fuelを成立させるには、質が高く、安価かつ大量の水素とCO₂が不可欠ですが、その“水素の供給源”を私たちが担おうとしています。
これが実現すれば、「資源がない」と言われ続けた日本が、再びエネルギー主権を持ち、世界を牽引する存在へと躍進できる。私は「日本から世界を変える」、そして「強い日本を取り戻す」ことを自らの使命と位置づけています。今回のプロジェクトはそのための決定的な一歩です。
直近では、来年度から日本国内でフルスケールの実証プラントを建設予定です。これまでは米国のパートナー企業施設を活用し技術検証を進めてきましたが、いよいよ“限界点のない”本格的な実証を、日本の地で実施します。廃棄物由来の水素は、自動車や発電など、既存の経済インフラにも活用され、より環境負荷の少ない社会への転換を後押しします。
ただし、廃棄物から高純度の水素を得るプロセスは決して容易ではありません。特に最大の壁は、性質も含水率も不均等な廃棄物を「エネルギー源として最適化する」前処理工程です。これまで大手企業も踏み込めなかった領域ですが、私たちはIoTやAI、素材分析技術を駆使し、多業種のパートナーと連携することで、この難題に正面から挑んでいます。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
私が25年前に創業した有限会社やまぎんは、アパレルOEM/ODMを手がける企業でした。しかし2020年、コロナ禍によって海外からの注文がすべてキャンセルされ、廃業の危機に直面します。
そのとき私の中で湧き上がったのは、「このまま終わっていいのか」「撤退する前に、業界が抱える“衣料廃棄”という構造的課題に挑んでみよう」という思いでした。アパレルの現場で長年ものづくりに携わってきた私は、衣服がどれほど複雑な素材構成でできているかを知っています。ウールやポリエステル、ナイロンだけでなく、木製ボタンや金属ファスナーなどが混在し、とても“分別”できるような代物ではありません。衣類は、まさに“厄介なゴミの塊”なのです。
そんな中、私はふと、かつて学んだ「水素から服を作る」というプロセスを思い出しました。ならば逆に、「服=廃棄物から水素を取り出す」ことも可能ではないか。そう発想を転換し、リサイクルできないあらゆる廃棄物から水素を生成するという、新たな事業の構想が生まれました。
ただ、当時このビジネスモデルを日本国内で提案しても、どの企業も興味を示しませんでした。「廃棄物から水素? 無理に決まってる」。そう言われ続けるなか、私は日本での実現が困難と判断し、コロナ禍の中、自ら渡米。シリコンバレーで技術開発に没頭し、同時に協業できるパートナー企業を地道に探し続けました。
もちろん、最初の反応は「それは不可能だ」という否定的な声ばかりでした。それでも“おもしろい”と共感してくれる人が少しずつ現れ、技術的にも、人的にも協力の輪が広がっていったのです。
そして構想から3年──2023年、社内ベンチャーとしてスタートしていたこのプロジェクトを分社化し、「株式会社BIOTECHWORKS-H2」を正式に設立しました。
これまで米国のパートナー企業の施設を借り、プロトタイプレベルで実証を行ってきましたが、次のフェーズはいよいよ“限界点のない”フルスケール実証です。
このチャレンジこそ、日本の地で実施すべきだと考え、国内での実証プラント建設に踏み切る決断をしました。今回の実証には多額の投資をしていますが、これこそが日本でできること、日本から世界へと広めていける技術だと確信しています。

5回の倒産危機を経験、それでもチャレンジし続ける
仕事におけるこだわりを教えてください。
事業でも自身のあり方でも、私が最も重視しているのは「周囲からどう評価されているか」です。つまり、自分を客観的に見つめ続ける姿勢です。
かつてアパレル事業を展開していた頃、海外取引で詐欺被害に遭い、わずか一日で約4,000万円分の商品が消え去ったことがありました。当然、取引先の信頼もすべて失いました。今振り返ると、この失敗の本質は“自分たちはうまくやれている”という誤った自己評価にありました。外からの声に耳を傾けず、独りよがりの経営判断をしていたことが原因だったのです。
ここで言う“他人の評価を気にする”というのは、顔色をうかがうという意味ではありません。重要なのは、「自分たちがどう思うか」ではなく、「他人がどう感じ、どう関心を持ってくれるか」です。この気づきは、自身の失敗から得たかけがえのない教訓でもあります。
起業から今までの最大の壁を教えてください
私はこれまでに、5回ほど倒産の危機を経験してきました。けれど、挑戦にはリスクがつきものです。そして経営者にとって最大のリスクとは、まさに倒産そのものだと実感しています。
それでも、私が何度もその崖っぷちから這い上がってこられたのは、無謀とも言える挑戦に対して手を差し伸べてくださった方々の存在があったからです。
たとえば、無担保・無保証で3,000万円を貸してくださった国内商社の方。また、支払いが困難だった中国で、商品代金を全額立て替えてくれた現地パートナー。本来なら見放されてもおかしくない状況で、「それでも応援したい」と声をかけてくれた人たちが、確かにいました。
彼らがそう感じてくれた理由は、私が“挑戦をやめなかった”からだと思っています。私が向き合っているのは、決して簡単ではない社会課題です。けれど、そんな難題に対して、諦めず、真正面から取り組もうとするベンチャー経営者の姿勢が、誰かの心を動かしたのだと信じています。
こうしたご縁や支援には、感謝してもしきれません。私は、人に恵まれてここまで来ることができました。

2035年には日本のすべての非リサイクル廃棄物を水素に変える
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
私にとってのモチベーションは、「目的や目標を明確に掲げ、それをやり抜くこと」にあります。この姿勢は、祖父母や両親から教わったもので、子どもの頃から自然と自分の中に根づいてきた感覚です。
そしてもう一つ、大切にしている価値観があります。それが「ありがとうの精神」です。私の両親は、たとえ自分たちに直接関係のないことでも、私に対していつも「ありがとう」と言ってくれました。その姿勢を見て育った私は、どんな小さなことにも感謝の気持ちを持つことの大切さを、日々の仕事の中で改めて実感しています。
なぜ、目標を掲げて「やり切る」ことにこだわるのか。それは最終的に、誰かから「ありがとう」と言ってもらえる瞬間があるからです。こうした家族から受け継いだ価値観が、今の私の行動を支える原動力になっているのだと思います。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
私たちは、明確かつ具体的な成長戦略を描いています。まず掲げているのが、2028年のIPO(株式上場)。これは、事業立ち上げ当初から一貫して目指している節目です。IPOは単なる資金調達手段ではなく、私たちの事業が「社会に必要とされている」ということを示す一つの象徴的な証だと考えています。
さらにその先には、2030年に売上100億円、2035年には日本国内のすべての「リサイクルできないゴミ」を水素に変換すること。そして2050年には、世界に認められるユニコーン企業としての地位を確立することを目標に据えています。あとは、この道筋に従って一歩一歩、着実に進むだけです。
一方で、私には個人的に強く実現したいもう一つのテーマがあります。それが「リチウムイオン電池の100%リサイクル化」です。リチウムイオン電池は、元々日本人の研究者が生み出した誇るべき技術です。しかし、実はその研究者自身が「このまま世に出してはいけない」と警鐘を鳴らしていたことをご存じでしょうか。
なぜなら、リチウムイオン電池は製造段階でも廃棄段階でも大量のCO₂を排出し、結果として環境に大きな負荷を与える構造を持っているからです。その懸念は現実となり、現在も「魔のサイクル」は放置されたまま世界中に広がっています。
私は、これを終わらせたい。日本人が生み出した技術だからこそ、日本人の手で「価値のあるサイクル」へと転換したいのです。この挑戦もまた、「強い日本を取り戻す」という私たちの使命の延長線上にあると信じています。

どういった人材を求めているのでしょうか
私たちの業務は、AIやIoTを活用した廃棄物の最適処理設計、トレーサビリティ・プラットフォームの運用、そして国内外のプロジェクトマネジメントなど、多岐にわたります。組織としては、正社員に加え、志ある業務委託メンバーも重要な戦力として活躍しています。また、海外での展開を視野に入れ、グローバル志向を持つプロフェッショナルも複数名在籍しています。
採用においては「来るもの阻まず」で学歴や肩書きではなく実力と行動を基準にしています。誰でもチャレンジできる一方で、結果がすべてです。入社後わずか数年で数倍まで大きく昇給する人もいれば、変化のない人もいる。それが私たちのスタイルです。もしそうした働き方と弊社の事業内容にご興味をお持ちの方がいれば、一度ご連絡いただければと思います。
お問い合わせはこちらから
「できない」と言われているところにこそ、チャンスがある
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
一般的に「できない」と言われているところにこそ、チャンスがあります。むしろそこにしか無いと言っていいでしょう。
さらに言うと、人のアイデアや事業のコピーにチャンスはありません。つまりは、成功の可能性は自分の頭の中にしかないのです。自分の頭で考えたことからしか、チャンスは生まれないと思ってください。
そしてもう1つお伝えできることがあるとすれば、決めたらすぐに行動するべきということです。リスクを恐れて考えている時間は無駄です。100回挑戦すれば99回は失敗するのが当たり前で、しかも失敗なんて実は大したことではありません。
どの人もこれまで生きてきて数え切れないほど失敗を経験していると思いますが、今振り返ってみればほとんどは問題にもならなかったと思います。ですから失敗を恐れず、決めたらすぐ動くということを忘れないでください。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:西川 明秀氏
BIOTECHWORKS-H2のCEOで創業開発者。22歳で学生起業し、独自の事業戦略で急成長を実現。コロナ禍、新会社を設立しわずか3カ月でEXITを達成。2020年、循環型エネルギーの未来を見据えシリコンバレーでBIOTECHWORKS-H2を創業。強い日本を取り戻し、日本から世界を変える「サステナブルイノベーター」
企業情報
|
法人名 |
株式会社BIOTECHWORKS-H2 |
|
HP |
|
|
設立 |
2023年7月 |
|
事業内容 |
|
関連記事
RANKING 注目記事ランキング
- 【#468】意見が政策につながる社会へ。市民参加型SNSと自治体向けAIで「デジタル民主主義」を推進|代表 伊藤あやめ/谷口野乃花(Polimill株式会社)起業家インタビューインタビュー

- 【#363】お金いらずで寄付ができるECサービス、世界を救う第一歩に|代表取締役 藤本 巴(株式会社ギバース)起業家インタビューインタビュー

- 【#544】保護犬・保護猫の命をつなぐ。福祉と仕組みづくりで、寄付に頼らず築く持続可能な社会|CEO / 代表取締役 伊東 大輝(株式会社ANELLA Group)起業家インタビューインタビュー

- 【#268】定年齢層向けイベントアプリ『シュミタイム』で、高齢者の社会的孤立を救う。|代表取締役CEO 樗澤 一樹(株式会社ジェイエルネス)起業家インタビューインタビュー

- 【#578】赤ちゃんの感情を可視化するAIアプリ『あわベビ』で、産後うつの課題を解決|代表取締役・CEO 中井 洸我(株式会社 クロスメディスン)起業家インタビューインタビュー