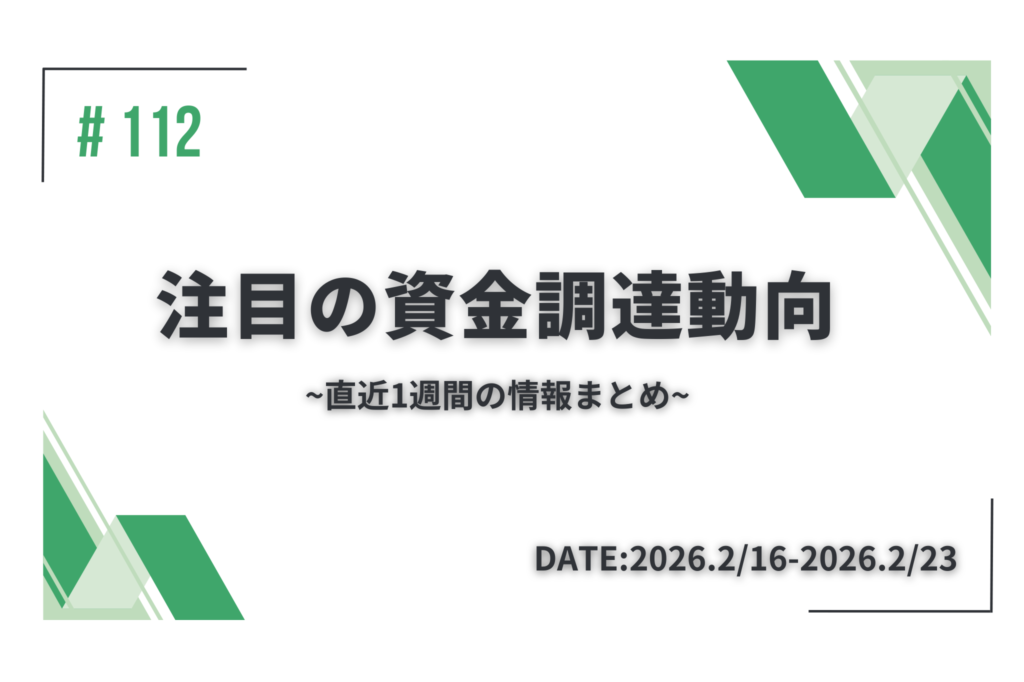【#468】意見が政策につながる社会へ。市民参加型SNSと自治体向けAIで「デジタル民主主義」を推進|代表 伊藤あやめ/谷口野乃花(Polimill株式会社)

Polimill株式会社 代表 伊藤あやめ/谷口野乃花
社会課題に対する市民の意見を集めるSNS型プラットフォーム「Surfvote(サーフボート)」と、自治体職員の業務を支援する生成AIツール「QommonsAI(コモンズエーアイ)」。2つのプロダクトを通じてAIの社会実装に挑む「Polimill(ポリミル)」代表の伊藤あやめ氏と谷口野乃花氏に、事業内容や今後の展望について伺いました。
目指すのは「ゆるやかな合意形成」
事業の内容をお聞かせください
伊藤あやめ氏(以下伊藤氏):SNSプラットフォーム「Surfvote(サーフボート)」と、生成AIプロダクト「Qommons AI(コモンズAI)」の2つを展開しています。
Surfvoteは、Web上でさまざまな社会課題(イシュー)を提示し、それに対してユーザーが意見を投票・投稿できるSNS型プラットフォームです。執筆者は現在約250名ほどで、毎月増えていて、
ユーザーはイシューの中から自分の意見に近いものを選び、選んだ理由を投稿します。選択し、意見を表明する。これがSurfvoteの基本的な流れです。
私たちが目指すのは、一種の「ゆるやかな合意形成」です。既存のSNSではさまざまな分断や対立が起きるケースも少なくありませんが、Surfvoteは分断を助長せず、異なる意見を持つ人同士であっても共通の価値観を見出し、それによって社会を前に進める「参加体験」と「成功体験」を同時に実現できる空間でありたいと考えています。
これまでに7つの自治体にご利用いただいており、
谷口野乃花氏(以下谷口氏):コモンズAIは、行政職員向けに最適化された生成AIです。
開発の背景には、サーフボートに集まる住民の貴重な声を、職員が十分に活用できていない課題がありました。窓口対応や書類作成といった日常業務をAIで効率化し、政策に向き合う時間を確保できないかと考え、2024年11月に正式版をリリースしました。
現在は250の自治体に導入されています。
最大の特徴は、全国の自治体が公開する議事録や総合計画、ガイドラインなどを事前に学習させている点です。データは市民向けに公開された情報をベースに独自のプロセスで学
ChatGPTなどの汎用AIと比べ、行政で実際に使われる表現やロジックに対応した出力が可能です。
自治体の方が議会の事前質問を準備する際に、過去の議事録の参照や他の自治体での対応方法などを簡単に調べることができ、好評のお声をいただいています。
現在は自治体ごとに100アカウントまで利用上限なく無料で提供
また、AIを最大限に活用するには、導入支援も重要です。当社は自治体の大小にかかわらず、全国で無料の研修を実施しています。このほか行政や大学と連携し、AIを社会実装させるための実証実験にも積極的に取り組んでいます。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
谷口氏:中学生のときに一度起業しましたが、高校時代にコロナ禍で廃業を経験しました。その頃、大学に進学する意味を見いだせず、高校卒業後はベンチャー企業に就職しました。
そこで、自分が本当に何に興味があるのかを考えるようになり、「地方創生」に関わりたいという思いに気づきました。
ちょうどその頃、今の会社を創業したメンバーの一人と偶然出会いました。当時、コモンズAIを立ち上げるタイミングで、その方が持っていた自治体に対する問題意識に強く共感しました。
自治体は本来「自ら治める」存在なのに、実際には政策立案を東京のコンサル会社に任せていることが多い。それでは地域でのまちづくりや人づくりができないと危機感を覚えました。大学に入学したばかりのタイミングでしたが、その思いに突き動かされ、入社を決意しました。
伊藤氏:私は大学卒業後、商社で金属を扱う部門に勤務していました。もともと社会の出来事や政治に関心があったのですが、実際に社会に出て強く感じたのは、同世代の中に広がる一種のあきらめムードです。
「どうせ意見を言っても変わらない」「誰も聞いてくれない」「だから選挙に行っても意味がない」といった空気感です。
ただ、私たちの世代が声をあげることを諦めたら、20年後、30年後の社会はどうなってしまうのかと強い危機感を感じていたタイミングで創業メンバーの方々から声をかけていただき、転職を決めました。
短期利益より社会実装
仕事におけるこだわりを教えてください
谷口氏:私たちが目指すのは、プラットフォームビジネスの確立です。短期的な利益にとらわれず、長期的な視点での投資を重視しています。コモンズAIが生活や業務の一部として自然に根付いていくことこそが、本質的な価値だと思います。
多くの自治体にご利用いただいているからこそ、事業連携の機会も広がっています。

伊藤氏:私も谷口と同感で、「AIの社会実装」を重視しています。自治体にはそれぞれ規模や予算、首長の方針など、多様な状況がありますが、すべての自治体の職員が等しくAIを活用できる環境をつくりたいと考えています。
職員の方々が日々の業務でストレスなくAIを使えることが、その先の市民の幸せにもつながると思います。

起業から今までの最大の壁を教えてください
伊藤氏:先ほどお話ししたプラットフォーム戦略に起因する課題があります。このビジネスモデルがまだ日本で定着していないこともあり、短期的な売上がほとんどない状態で事業の魅力やビジョンを説明してもなかなか理解されにくいのが現実です。
とはいえ、Googleといった世界的な企業も最初は赤字からスタートしていますし、誰もが日常的に使うプラットフォームになるまでには、一定の時間と忍耐が必要です。覚悟を持って、地道に取り組んでいます。
私たちに共感して資金を提供してくださる方々は、短期的な利益ではなく「この事業が社会全体にとってどんな意味を持つか」を重視する方々です。会社の方針やビジョンが、国全体の最適化や社会的意義につながることに共感してくださっています。
誰もが平等に意見を言える社会に
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
伊藤氏:一緒に働く仲間の存在が、とても大きいです。
リモートで働く副業のエンジニアの方々も20〜30人ほどおり、皆が「社会にとって有意義な仕事をしている」との思いを持って取り組んでいます。その姿は非常に励みで前に進む力になります。
谷口氏:プロダクトを実際に使っている方々からの期待や応援が、何よりのモチベーションです。
ベンチャーの良さは、現場との距離が近く、ユーザーの声を最速でプロダクトに反映できるところです。ある自治体の市長と「これをAIで自動化できたら便利だよね」とお話したことがきっかけで、約2カ月でリリースしたプロダクトもあります。
現場からの声を拾い、要望を形に落としこむ、このプロセスそのものに大きなやりがいを感じています。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
伊藤氏:私たちは「デジタル民主主義」を本気で推進したいと考えています。「声を出したいけど難しい」と感じる方がまだまだ多い世の中だからこそ、誰もが平等に意見を言えて、確実に政策に反映される仕組みをSurfvoteで実現したいと考えています。
谷口氏:コモンズAIについては、全国約1800の自治体すべてに導入し、行政が使う生成AIのスタンダードになることを目指します。
そのためにも情報の最適化やデータの取り扱いに関する基盤を整備し、自治体が安心して使える環境を構築していきます。行政ごとの効率化だけではなく、自治体全体の最適化につながるインフラを築きたいです。

失敗を恐れず、挑戦を
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
伊藤氏:日本はベンチャー企業に対してまだ発展途上の面があると感じています。起業に対する社会的な理解や仕組みがまだ十分に整っていないと思うのです。ただ、挑戦する人が一人でも増えれば、その文化は必ず変わります。
そうなれば、日本の未来はもっと面白く、豊かになると思います。
谷口氏:中学時代に起業した経験から強く感じるのは、「失敗すること」の大切さです。今の社会は失敗を恐れる空気がありますが、「失敗した」と実感できるくらい本気でやったかどうか、それを繰り返すことができたかどうかが、何よりも貴重な経験です。
それが良いソリューションやサービスを生み出す土台になります。やりたいと思ったことがあれば、失敗を恐れず、突き進んでほしいです。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:伊藤あやめ氏/谷口野乃花氏
企業情報
|
法人名 |
Polimill株式会社(ポリミル) |
|
HP |
|
|
設立 |
2021年2月 |
|
事業内容 |
この国の社会の全体最適化 |
関連記事