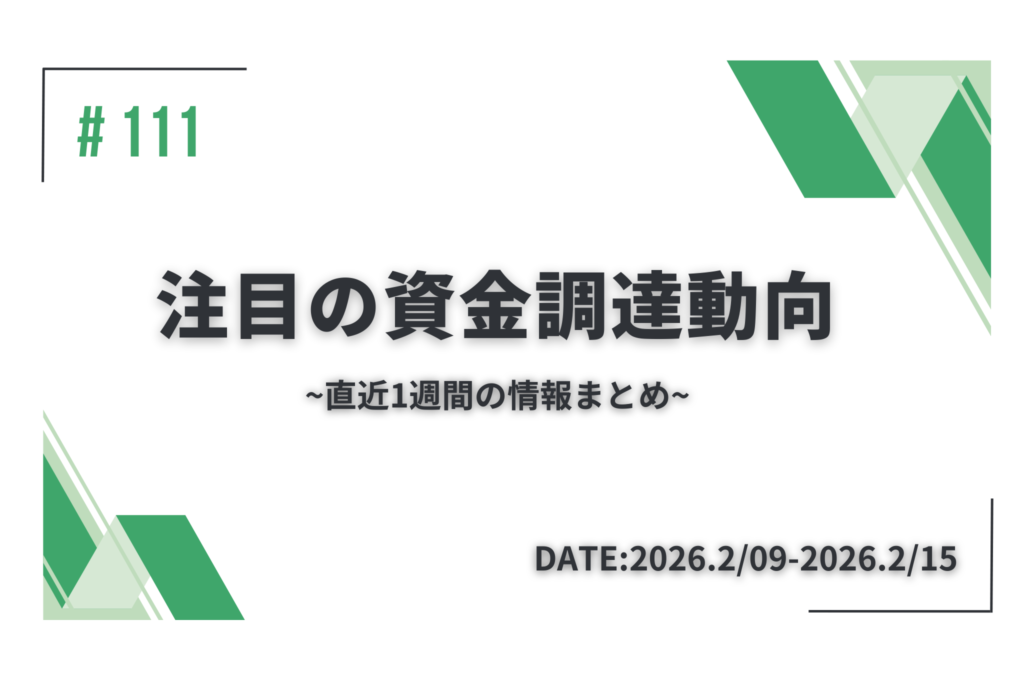【#484】バイオ技術のイノベーションが生む新しい価値を消費者に届ける|Co-Founder & President of Asia-Pacific 福永祐一(Taxa Technologies, Inc.)

Taxa Technologies, Inc. Co-Founder & President of Asia-Pacific 福永 祐一
Taxa Technologies, Inc.は組換え微生物による有効成分の研究開発と商品開発に取り組むアメリカ・サンフランシスコ発のバイオテックスタートアップです。独自の微生物に対するゲノム編集と移植技術で、ワキガのニオイを抑える効果が1週間持続する新しいタイプのデオドラント「Swap」を開発し、2026年の発売を目指して準備を進めています。今回は、共同創業者である福永祐一氏に、研究開発の裏側や事業戦略、アメリカで日本人が起業する難しさについて伺いました。
微生物の「ゲノム編集」と「移植技術」で新たな消費財を開発
事業の内容をお聞かせください
私たちは、皮膚に常在する微生物、いわゆる皮膚マイクロバイオームの研究開発と商品開発を行うバイオテックスタートアップです。
皮膚にはさまざまな微生物が存在しており、体臭やアトピー性皮膚炎などの皮膚トラブルに関与しています。肌の潤いを保つ「美肌菌」が有名になりましたが、ここ10年でこの領域の研究は飛躍的に進歩しました。
私たちは、独自の微生物に対するゲノム編集技術を持ち、特定の微生物に新たな機能を加えたり、逆に機能を取り除くことができます。また、微生物を皮膚に長期間定着させる技術を持つことが強みであり、これらの技術が画期的な製品の開発につながっています。
この「ゲノム編集」と「移植技術」を組み合わせることで、従来にない長期間効果が持続する化粧品や医薬品の開発が可能となります。この技術を活かして開発した製品が、一度の塗布で一週間ワキガのニオイを抑えるデオドラント「Swap」です。
「Swap」について詳しく教えていただけますか?
「Swap」は、ワキガ原因菌を無臭菌と置き換えるというTaxa独自の新しいメカニズムにより、わきのニオイを根本から長期間抑えることを実現した画期的なワキガケアアイテムです。
既存のデオドラントのメカニズムは、「制汗成分で汗を抑える」「ニオイの原因菌をアルコールなどで殺菌する」「香料によってニオイにマスクをする」という3パターンに分けられます。いずれもシャワーや汗で流れてしまうため、効果は一時的で、もって半日といったところです。
一方、私たちが開発した「Swap」はまったく違うアプローチを採っています。無臭菌がワキガ原因菌と置き換わることで、わきのニオイの発生を抑制するのです。無臭菌は皮膚にとどまり、ワキガ原因菌の絶対量を減らします。
皮膚の微生物そのものが変化しているため、シャワーを浴びても海に入っても、簡単には落ちません。

デオドラント商品に着目したのはどうしてですか?
体臭へアプローチするデオドラントを選んだ理由は、技術的に実現可能であったこと、そして市場規模の大きさです。
デオドラント市場は世界で約4兆円弱の規模があります。その市場の大半を占めるアメリカにおいてデオドラントは、季節や体臭の強さを問わず、生涯にわたって使い続けることが一般的です。商品の開発には技術的に可能であることに加え、どれだけ市場があるかも重要なのです。
当社はアメリカの会社なので、まずはアメリカでの販売を予定していますが、日本での展開も視野に入れています。
これは代表である私が日本人だから、という理由だけではありません。日本におけるわきのニオイに対する考え方や対処法が特殊だからです。
実は日本以外の国には「ワキガ」にあたる言葉がありません。体質としてはあるのですが、コンプレックスに紐づく言葉として存在しないのです。
一方で日本では、ワキガは大きな悩みとして認識され、ボトックス注射や外科的手術で治療する人も少なくありません。こうした受け止め方は、国際的に見てもかなり特殊です。
「Swap」は、アメリカでは「ちょっとハイレベルなデオドラント」として受け入れられると考えていますが、日本では、痛みがともなう治療や高額な施術の“代わり”として提案できる製品になります。
長年悩んできた方にとって、まさに「これを待っていた」と感じてもらえるようなプロダクトになりうる。そういう意味でも、日本市場での展開に可能性を感じています。
事業を始めた経緯をお伺いできますか?
起業を考えたのは高校1年生の時です。その頃から、「どんな業界で、どんな仕事が自分に向いているか」を20歳までに決めたいと考え、本を読んだり、いろんな人に話を聞きに行ったりしていました。
当時は、日本でもアメリカでもソフトウェア系のスタートアップがとても注目された時期で、自分も興味を持って情報を追っていました。そんな中で偶然、「天才高校生プログラマー」と呼ばれる人と出会い、率直に言って「これは勝てない」と感じました。また、自分はソフトウェア開発そのものに強い興味を持てなかったのです。
一方で、バイオテックやヘルスケアといった分野には少しずつ関心が出てきていて、ちょうど大学進学前のタイミングで、本格的に興味を持ち始めました。
バイオや研究の分野で何かに取り組もうとすると、大学のラボなどの設備が必要となります。この分野はこれからもっとおもしろくなる予感もあり、自然とそちらの道へと進むことになりました。その後、アメリカのウィリアムズ大学に進学し、学生寮のルームメイトだったのが、今の共同創業者です。
卒業を控えた頃、今の会社の基盤となる研究が順調に進み、特許出願の段階に入りました。そのタイミングで「一緒にやらないか」と彼から声をかけられたのが、起業の直接のきっかけです。
大学4年間ずっと生活を共にし、互いの研究内容や研究に向き合う姿勢、そして互いに「スタートアップをやりたい」と考えていることも知っていましたので、ごく自然な流れではありました。

イノベーションによって生まれた価値を消費者に「届ける」
仕事におけるこだわりを教えてください。
個人的に仕事を通して実現していきたいのは、サイエンスやテクノロジーのイノベーションから生まれた新しい価値をきちんと消費者に「届くもの」にすることです。
技術的なイノベーションはとても重要ですが、それを人々の生活に届けることも同じくらい大切だと考えています。そして、この2つを両立させることはじつは簡単ではありません。
どれだけ面白い技術や研究成果があっても、実際に人々が求めているものでなければ、事業として成立しません。ただ純粋に研究が好きなのであれば、大学に残ってアカデミアとして研究を続けていればいいでしょう。
しかし、私は面白い研究をして、社会や個人にとって実際に価値ある形で「届くもの」を生み出したいのです。
今取り組んでいる研究やプロジェクトが、この想いに沿っているか? これは自分にとって絶対に譲れない軸であり、大切にしているこだわりです。
起業から今までの最大の壁を教えてください
日本で生まれ育った日本人である私が、アメリカでバイオ領域のスタートアップをやっていること自体、壁を感じる瞬間があります。
言葉の壁については、大学からアメリカにいたので、ある程度は乗り越えられたと思っています。ですが、商習慣や価値観の違いなど、文化的な壁は確かにあり、それに馴染むことには苦労しました。
たとえば、自分の直感で「これは絶対にいける!」と思ったことでも、アメリカ人の共同創業者が言っていることのほうが正解なのではないか?と思ってしまうことがありました。そして、そう感じてしまう自分が悔しいのです。
そうした感覚のズレをどう受け止め、自分の中でどう咀嚼していくかは簡単ではありませんでした。

毎朝、「仕事したいな」と思って目覚める
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
モチベーションとなっているのは、イノベーションから生まれた新しい価値をきちんと消費者に「届くもの」にしたいという想いです。
ただそれだけでなく単純に、朝、目が覚めた時に「仕事したいな」と自然に思うのです。それを日々、純粋に感じられているのは、けっこうレアなことなのかもしれませんが、私は毎日ワクワクしながら仕事をしています。
今の会社で、今のポジションで働いていることが、自分のキャリアにとってベストであり、今の自分以上の選択肢は他に一切ないと論理的にも感情的にも思えている。それが、モチベーションになっているのかもしれません。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
日本での展開もできるだけ早く進めたいと考えていて、すでに現地法人の立ち上げに向けて動いています。
そのため、日本での採用活動もスタートしています。技術的なイノベーションの価値を正しく理解し、それを消費者や関係者にしっかり伝えられる人、一人でも物事をやりきれるだけの推進力と、それを支える明確な動機を持っている人を求めています。
会社としては「皮膚のマイクロバイオーム」の領域で、すでにかなり良いポジションを取れていると感じています。デオドラント市場は約4兆円の規模があるので、まずそこでポジションをしっかり取れたら、それだけでユニコーン企業になることができます。
皮膚の領域をしっかり押さえることができ、技術が成熟していけば、次は皮膚以外のマイクロバイオーム領域も視野に入るかもしれない。今後の展望にも、ワクワクしているところです。

失敗しても飲み会のネタには一生困らない
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
私たちの会社は、大学の学生寮からスタートし、規模が拡大するにつれてサンフランシスコに拠点を移し、大学院生だった頃には考えられないような優秀な仲間と働くことができています。
さらに、アメリカ国内だけでなく、グローバル展開を検討するフェーズにまできました。創業者として、こうした企業成長のすべての過程を間近で体験できるのは、何よりも楽しく、面白い経験です。
たとえ失敗したとしても、おそらく、飲み会のネタには一生困らないでしょう。そのくらいの気持ちで、気軽に始めてみてもいいのではないでしょうか。
本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:福永 祐一 氏
1999年生まれ大阪府出身。慶應義塾大学経済学部に1学期間ほど在籍したのち、1年程度のギャップイヤーを経てアメリカ・ウィリアムズ大学に進学。ギャップイヤー期間中に経験した日本のヘルスケア企業での長期インターンを通し、技術革新を用いたインパクトのある事業創出を志すようになる。ウィリアムズ大学では、マウスをモデル生物とした記憶の研究に取り組む。同大学でTaxa Technologies, Inc.の共同創業者であるシャビエル・セイゲル(Xavier Segel)と出会い、4年次から彼とともに、合成生物学・マイクロバイオームの研究と事業開発を開始。2023年1月、同大学在籍中にサンフランシスコにてTaxa Technologies, Inc.を共同創業。2023年5月にウィリアムズ大学を卒業後、ドイツ・マックスプランク研究所 博士課程に飛び級で進学。2023年10月、マックスプランク研究所 博士課程を中途退学し、Taxa Technologiesに専念することを決意。米日カウンシル・アソシエイトリーダー。
企業情報
|
法人名 |
Taxa Technologies, Inc. |
|
HP |
|
|
設立 |
2023年1月 |
|
事業内容 |
組換え微生物を用いた有効成分の研究開発、商品開発 |
関連記事
RANKING 注目記事ランキング
- 【#468】意見が政策につながる社会へ。市民参加型SNSと自治体向けAIで「デジタル民主主義」を推進|代表 伊藤あやめ/谷口野乃花(Polimill株式会社)起業家インタビューインタビュー

- 【#363】お金いらずで寄付ができるECサービス、世界を救う第一歩に|代表取締役 藤本 巴(株式会社ギバース)起業家インタビューインタビュー

- 【#544】保護犬・保護猫の命をつなぐ。福祉と仕組みづくりで、寄付に頼らず築く持続可能な社会|CEO / 代表取締役 伊東 大輝(株式会社ANELLA Group)起業家インタビューインタビュー

- 【#268】定年齢層向けイベントアプリ『シュミタイム』で、高齢者の社会的孤立を救う。|代表取締役CEO 樗澤 一樹(株式会社ジェイエルネス)起業家インタビューインタビュー

- 【#578】赤ちゃんの感情を可視化するAIアプリ『あわベビ』で、産後うつの課題を解決|代表取締役・CEO 中井 洸我(株式会社 クロスメディスン)起業家インタビューインタビュー