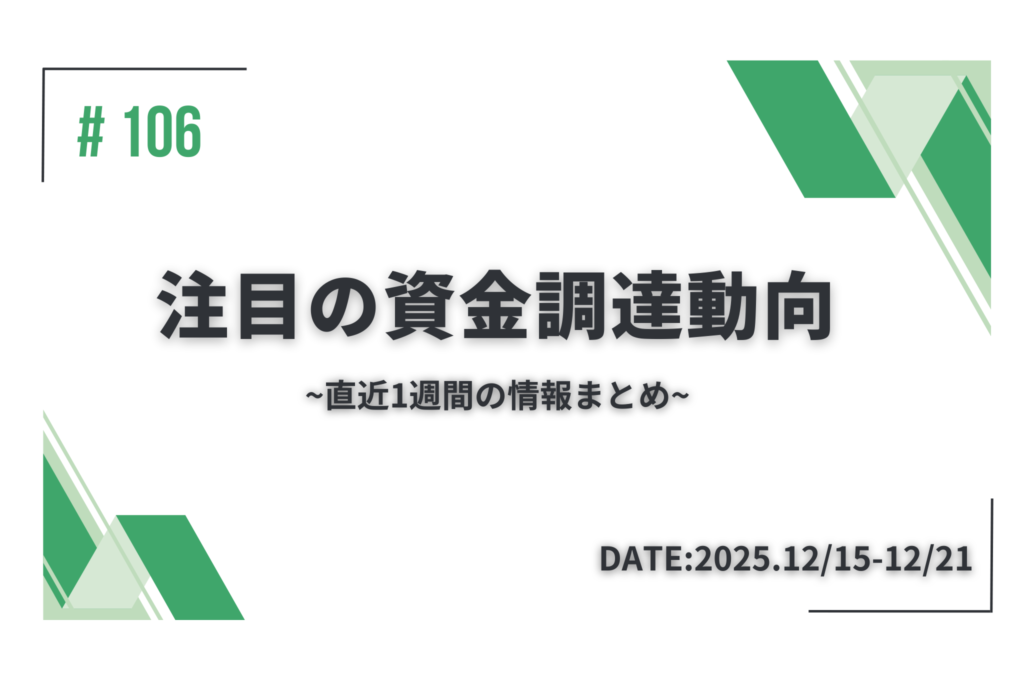【#385】企業の根幹を成すサプライチェーンマネジメントの常識を変え、“出来ない”を解決|代表取締役CEO 梅田 祥太朗(株式会社リチェルカ)
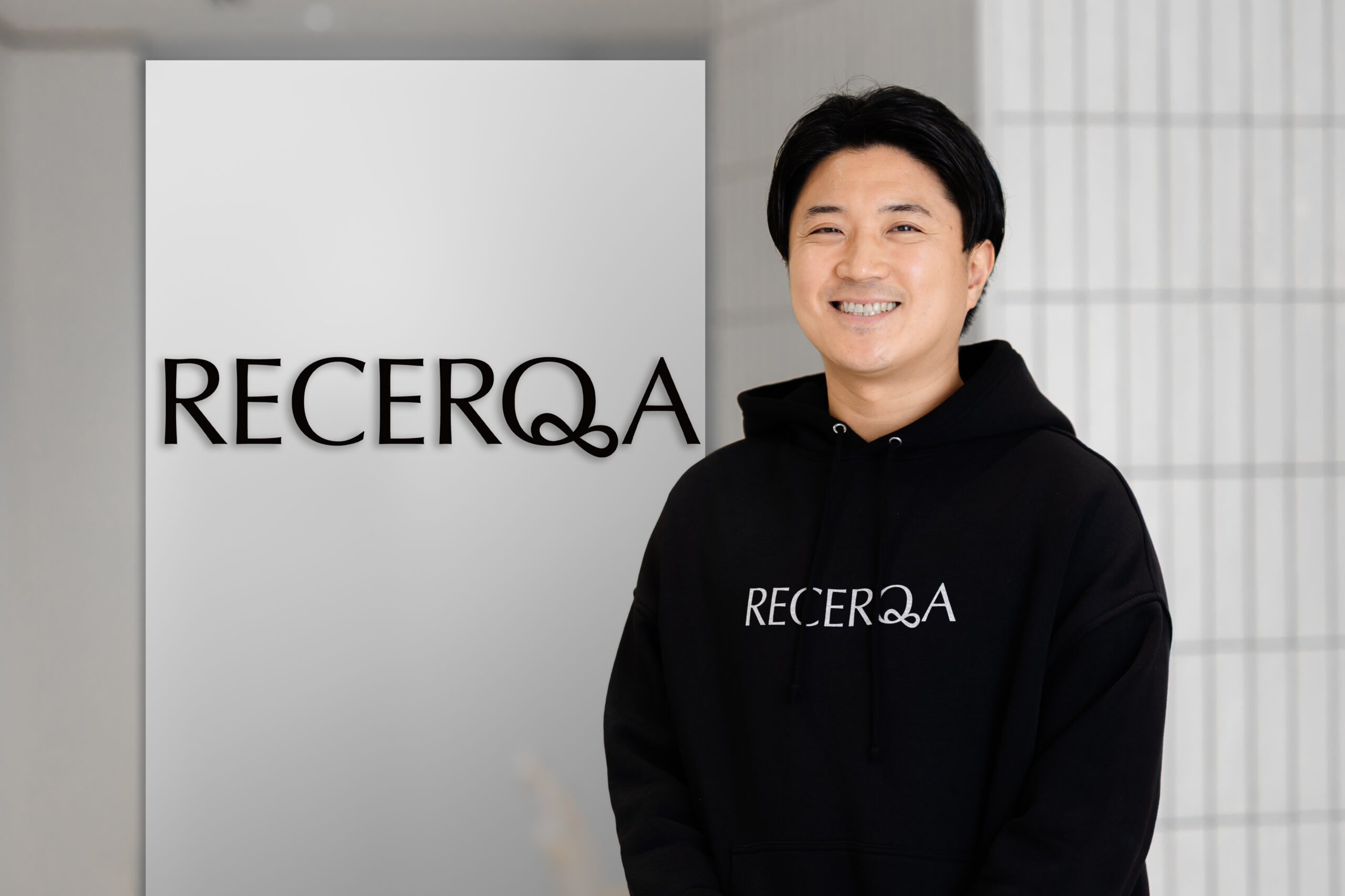
株式会社リチェルカ 代表取締役CEO 梅田 祥太朗
数十億から数百億円規模のプロジェクトになることも珍しくない、サプライチェーンマネジメント。この複雑で難易度の高い領域にあえて挑戦しているのが、株式会社リチェルカです。同社のシステム「RECERQA」には、代表取締役CEOである梅田祥太朗氏が多様な経歴の中で獲得してきた、業務管理やAI技術といったノウハウが生かされています。今回は梅田氏に、起業の経緯や詳しい事業内容についてお聞きしました。
圧倒的に操作性が高い!サプライチェーンマネジメントシステム
事業の内容をお聞かせください
弊社は主に大企業向けに、サプライチェーンマネジメントシステム「RECERQA(リチェルカ)」を提供しています。
仕入や在庫、販売管理といったサプライチェーンは企業活動の根幹を成す部分です。それゆえにそのマネジメントは煩雑を極め、業務の規模も負担も大きいために、これまでスタートアップが挑戦した事例はほとんどありませんでした。
弊社は事業会社での運営ノウハウ、そして生成AIを活用することができる人材という、自社が保有する力を掛け合わせることで、あえてこの困難な領域に挑んでいます。
「RECERQA」としての特徴の1つは、その圧倒的な操作性の高さです。現在、個人ユーザー向けアプリが分かりやすいデザインで誰でも直感的に操作しやすいのに対し、企業向けの業務システムはまだまだUI・UXにおいて課題が多いと言えます。システムを利用するためだけにマニュアルや知識が必要とされる現状を変えたいと思い、「RECERQA」では直感的に操作できるUI・UXにこだわりました。
そして2つ目の特徴は、あらゆる企業のニーズに標準装備の機能で応えられる点です。一般的に業務システムは、各企業のニーズに合わせたカスタマイズを前提として設計されます。しかし、発注からカスタマイズを経て、実装されるまでに年単位の時間がかかってしまうと、その時点ですでに企業側のニーズも変化しているケースが多いのです。
さらに、何億何十億と掛けたシステムを運用していくなかで、追加調整する手間とコストを考えると、必要な機能が標準装備されたパッケージ型サービスのニーズは高いと考えました。
既に業務システムの中でも、人事領域や会計領域ではその標準化が進んでいますが、標準化が難しい「サプライチェーンマネジメント」でも同じような標準化を目指しています。
3つ目の特徴は、パッケージの提供に留まらない伴走支援です。例えば、「RECERQA」ではデータ分析機能にも生成AIを活用していますが、このとき重要になるのが分析の基となるデータの精度です。例えば、管理しているデータの入力規則が統一されていない、アナログデータが多くデジタルデータストックが乏しい、このような課題があると分析結果も正確さに欠けるものになります。
導入に際しては、“システムを入れ替える”ということを主眼とするのではなく、生成AI時代に備えた運用や業務プロセスの整理、システムの設計を含め、お客様と伴走させていただいております。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
これまで様々な業種とポジションを経験してきて、そのすべてが今の「RECERQA」の事業に集約されていると言えます。それらすべての始まりは、以前勤めていた会社のサプライチェーンマネジメント事業で大きな挫折を経験したことです。
その会社でも、企業のサプライチェーンマネジメントに関するあらゆるニーズを網羅した画期的なシステムを構想していたのですが、技術的な問題で実現できなかったという経緯がありました。非常に悔しい思いをして、経営企画に参加したいと会社に申し出たのですが、力不足で叶うことはありませんでした。
そこで、まずは企業経営の知識を身に付けたいと考えて、小さなAI事業のスタートアップに転職しました。そこではCROとして事業規模を10倍までに拡大することにも成功しましたが、急激な成長を遂げたためにメンバー間に方向性の違いが生じて、結果的にまた会社を離れることになります。
その後はベンチャー立ち上げ支援の仕事を経て、ブロックチェーン関連の会社にBtoB事業の立ち上げを担うCOOポジションで入ったのですが、時代の流れに沿ってBtoC領域に力を入れていくことになりました。
BtoC領域では私の強みを活かせないと思いましたし、BtoB領域で挑戦したい気持ちがあり、再び離職を決めました。そのとき同じように考えるメンバーが一緒に会社を離れることになり、彼らの雇用を確保しなくてはと考えて起業を決意したのです。
私自身は、AI事業のスタートアップでIPOを経験していましたので、他のメンバーにも自分と同じような成功を経験してほしいと思っていました。誰もが仕事で精一杯力を尽くして、成果を出し、幸せに働ける会社を作りたいと感じたのです。
事業について試行錯誤を重ねるうちに、自身が別に経営をしているバイク輸入業での経験と以前サプライチェーンマネジメントに挑戦していた当時の熱い想いが重なりました。AIが急速に進化して開発に必要な技術が手に入った今、もう一度難易度が高くて複雑で、そして最高に面白いあの仕事に取り組もうという想いが強くなっていったのです。
そして、時代が追いついていなかったために道半ばで断念したサプライチェーンマネジメントの構想に、今こそ再挑戦するときだと考えて「RECERQA」を立ち上げました。

「社員の成長にどれだけ投資できるか」を考える
仕事におけるこだわりを教えてください。
目の前の収益や効率だけを追い求めないという姿勢は、自分の中に一貫してある部分です。その1つとして、社員の成長にどれだけ投資できるかには非常にこだわっています。
やはり人の成長なくして、会社の成長はあり得ません。今はインサイドセールスなどを外注するケースも多いと思いますが、そういう仕事ばかりを請け負って、何年もずっと電話営業だけに取り組んでいる人材が“営業”として成長できているかというと難しいでしょう。それは人材の消費に他ならないと私は思います。
社員にもっと本質的な力、思考力やタフさを身に付けて成長してほしいと願っています。先日は、一旦AIのアイデアに頼った仕事はストップするよう、一人の社員にアドバイスしました。AIを活用すると業務の効率化は実現するため積極的な活用も促してはいますが、その一方で社員の考える力が弱まるリスクもあります。
「頭の良さ」ということに関して、私は筋肉トレーニングと同じで日々のトレーニングが重要だと思っているので、とにかく自分の頭で考える過程を大切にしたいのです。
すでにAIは部分的に人間の能力を超えてきていますが、我々はAIをあくまでも道具として使いこなさなくてはなりません。AIの操作に限らず、マーケティングや営業やプログラミングなども仕事のための道具と考えると、人間に求められるのはそれらを使いこなす力です。
私は社員にどんなスキルが要求される職場でも通用する、人間としての基礎力を身に付けて欲しいし、今後もそういう視点で社員の成長にこだわっていきたいと思います。
起業から今までの最大の壁を教えてください
これから大きく成長するために、今ちょうど1つの壁を乗り越えようとしているところです。
これまで事業拡大に合わせて組織も広げていき、急ぎで人を採用する場面もあったのですが、今後はもっとカルチャーを重視した採用を徹底したいと思っています。弊社は現在、正社員が10名、業務委託の人が20名程といった組織構成ですが、この10名の社員のチームの中ですらカルチャーの違いを感じるところがあり、それが最近の悩みの種だったのです。
今後は皆が同じ気持ちで働ける組織にしたいと考え、話し合いを重ねていった結果、退職という結果になった人もいます。これは会社として試練の時ではありますが、ここから組織が生まれ変わっていくチャンスでもあると思いました。
今後は採用時からカルチャーフィットしているかどうかをしっかり確認して、より良い組織を作っていきたいと思います。

社員が頑張った分だけ報われるようにする責任
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
私を信じてくれたクライアントや投資してくれた方々、いわゆるステークホルダーからの期待を背負っていることが大きいと思います。「梅田の会社にしてよかった」「梅田に投資してよかった」と思ってもらわなくては、自分自身が生きている意味がないと思うのです。
そして、この会社で成長できると考えて頑張っている社員に対しても責任があります。皆遅くまで頑張って働いてくれていますし、中には会社の近くに引っ越してきてくれた社員もいます。彼らが頑張った分だけ報われるようにするのは、経営者としての私の責任です。
本質的には私も怠け者で、面倒なことや苦手なことはやりたくないんです。けれど、社員が皆覚悟を持ってこの会社で働いてくれているから、私も絶対に結果を出さなくてはならないと思っています。そうやって自分を追い込んでくれる環境が、今の私の原動力です。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
生成AIを社会実装することで、これまでの“出来ない”を解決するソリューションを提供し続けたいと思っています。それに加えて、やはり何か1点で突き抜けている会社でありたいと思っています。
他社を見回しても、起業家を多く輩出している企業やユニークな社風の企業などは、会社としてのカラーがはっきりしていて良いと思うのです。弊社も自分たちのアイデンティティをしっかりと持っていて、社員が胸を張って働けるような会社にしていきたいという想いがあります。

どんな領域でも本気でやればマネタイズできる
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
自身の経験から思うのは、自分が一番好きで熱狂できることをやったほうが良いということです。私は独立したときには特にやりたい事業があったわけではなく、今の時代に収益を上げやすいだろうと思ってNFTやブロックチェーン関連からスタートしましたが、やはり熱意がないと長く続けるのは大変です。
どんな領域だろうと本気でやればマネタイズできると考えているので、これから起業する人には好きな業界で挑戦して欲しいと思います。
それともう1つ、仕事は信頼できる人と一緒にやったほうがいいです。弊社も最初3人で立ち上げた会社ですが、この3人でなければここまで来れなかったと強く感じています。我々はよく「健全なコンフリクト(衝突)」という言葉を使うのですが、一緒に働く仲間とは何でも本音を言い合える関係性を大切にして欲しいと思います。
求める人物像について教えてください
素直で前向きな成長志向型であること、これに尽きると思います。この性質さえ持っていれば、試行錯誤しながら自分の型を自分で作っていけます。特に、生成AI時代においては素直に「アンラーニングしていく力」が大切だと思っています。
時代の進化が著しいなかで、過去に囚われず生成AIを道具としてうまく活用していく力が重要です。また、何か欠けているスキルがあると思っていても、成長志向の人であれば今から新しいことを無限に吸収していけるので大丈夫だと思っています。
成長したいという気持ちはあるけれど具体的に自分が何をしていいか分からないという人は、ぜひ一度弊社に応募してみてください。カルチャーが互いに似通っていて、皆が結果を出すために一生懸命真面目に働いている職場なので、人間関係のストレスも少ないと思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:梅田 祥太朗氏
中央大学卒業後、株式会社みずほ銀行に就職。その後に株式会社ワークスアプリケーションズにて会計・SCM領域の営業に従事。最年少マネージャーとして総合商社グループ、大手製造業などを支援。2019年にはAI inside株式会社の執行役員CROとして尽力し、同年にはIPOを実現。2021年までの4年間で売上100倍を達成した後、UTECで投資先の支援を行う。2021年、株式会社HashPortの取締役COOとして参画し、ビジネスの立ち上げやIPO準備など、組織拡大をリード。その後2022年に株式会社リチェルカを設立。
企業情報
|
法人名 |
株式会社リチェルカ |
|
HP |
|
|
設立 |
2022年4月 |
|
事業内容 |
SCM SaaS関連事業 |
関連記事