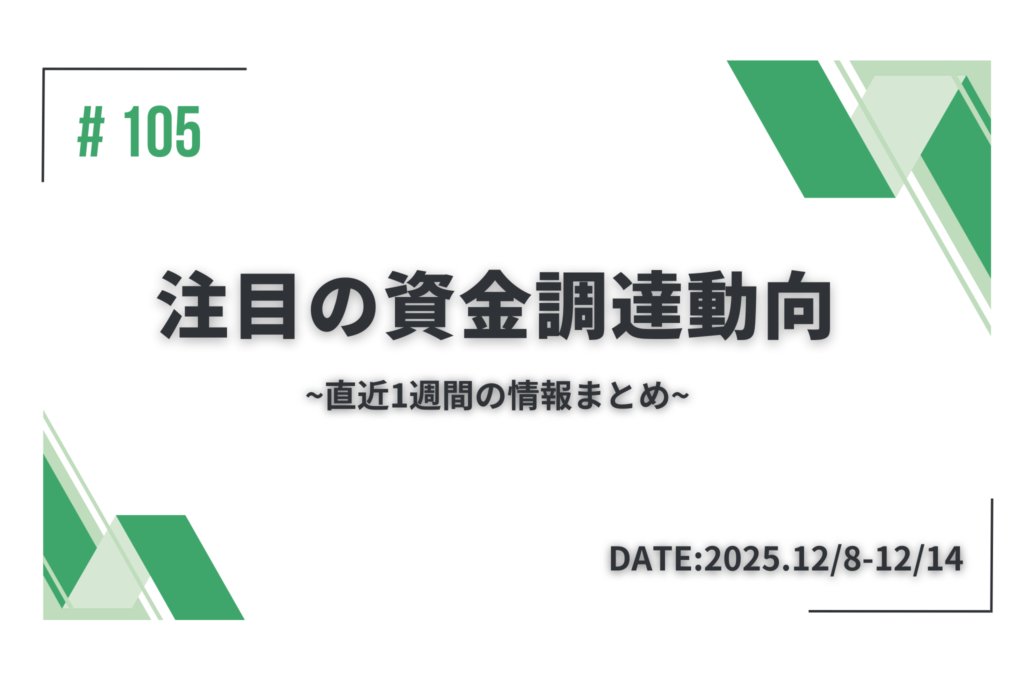株式会社霹靂社 代表取締役 本多 和幸
IT系ニュースメディア『CaseHUB.News』を運営する株式会社霹靂社。ビジネスITのユーザー実例情報に特化した『CaseHUB.News』は、業界情報が主流のIT系メディアの中で異彩を放っています。それは代表取締役の本多和幸氏の「読者を最優先に考えるメディアでありたい」という思いの表れにほかなりません。長くIT業界で取材・執筆を続けてきた本多氏に新たなメディアを立ち上げた思いを聞きました
ITユーザー事例に特化した『CaseHUB.News』を運営
事業の内容をお聞かせください
我々霹靂社は、IT系ニュースメディア『CaseHUB.News』の運営とコンテンツの企画・制作によるマーケティング支援、商業メディアへの記事執筆や企画提案・制作の3つの事業を柱としています。
なかでも、リソースをもっとも投入しているのが『CaseHUB.News』の運営です。
『CaseHUB.News』はBtoBのITソリューションの活用実例に特化しています。ユーザー事例というニッチな領域を専門に扱う独自性の高いメディアです。
もうひとつの特徴は記事の探しやすさです。多くのウェブメディアはトップページに注目記事があり、その他は新着順に並んでいます。テーマやカテゴリー別に分類されていたり、サイト内検索ができたりしても、求めていた情報にたどりつけないことも珍しくありません。
『CaseHUB.News』は、フリーワード検索はもちろん、「ユーザー組織の規模」「業種」「IT導入の対象」「ユーザーの課題」「IT製品/ソリューション」などを組み合わせて絞り込み検索ができるので、必要な情報を簡単に探すことができます。
同じ業種、同じような規模の企業が、どんなITソリューションを導入して、どう課題を解決したのかなどの情報はある一定のニーズがあり、それらに応えたメディアとなっています。
どうして、検索機能にこだわったのでしょうか?
『CaseHUB.News』は、私と弊社取締役の谷川耕一が立ち上げたメディアです。私たちはともにIT業界で長く取材活動を続ける中で、「あらゆる記事が短期的に消費されてしまう」という課題を感じてきました。
公開直後は注目を集めても、時間が経つと読まれなくなってしまいます。ですが、読者が必要とするタイミングで何度でも参照されるべき情報を含む記事も、本来はたくさんあるのです。
だからこそ私たちは、「蓄積された記事が情報資産としてきちんと活用される環境」を作る必要があると考え、検索方法に強くこだわりました。
読者が自身の課題や関心に応じて、最適な記事にたどり着ける検索UIを設計することで、記事本来の価値を最大限に引き出し、長く活用される仕組みを実現しています。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?
霹靂社を立ち上げる前は、株式会社BCNに在籍し、IT業界向け専門媒体「週刊BCN」で記者をしていました。独立する前の4年間は編集長の立場にありました。
私が辞める前年、「週刊BCN」が創刊40周年を迎え、編集長として創刊記念企画を進めていたのですが、その過程は、媒体が立ち上がったから40年間の歴史を追体験するようなものでした。
編集長として楽しく仕事をさせてもらいましたが、株式会社BCNの創業者や、「週刊BCN」の先輩たちが築き上げてきた価値を改めて実感する機会にもなりました。
ゼロから新しいものを作り、育てていくことのその価値が理解でき、自分でもやってみたいと考えるようになり独立を決めました。
読者を最優先に考えるメディアでありたい
仕事におけるこだわりを教えてください。
「読者を最優先に考えるメディア」の運営です。事例への特化や情報を探しやすい検索機能が『CaseHUB.News』の特徴ですが、これも、最優先に考えるべきは読者へ価値を提供するということの表れです。
読者を最優先の顧客と位置づけ、しっかりマネタイズしていけるかがビジネス系ウェブメディアとしての新しいチャレンジだと考えています。
多くのウェブメディアは、情報の対価を読者からもらうというビジネスモデルを採用していません。しかし、こうしたかたちでのウェブメディアの運営は、単なるマーケティングプラットフォームとしての色彩が過度に濃くなってしまうリスクをはらんでいると感じます。
メディアは本来中立公正であり、社会の公器たるべきだと思っています。保守的なメディア観かもしれませんが、「メディアの中立公正な価値」、正確には「中立公正であろうとする意思の価値」を私たちは信じていますし、大事にしたいと思っています。

起業から今までの最大の壁を教えてください
大変だったのはやはり、メディアの立ち上げです。会社の設立から約2年半後にメディアをたちあげました。しかも、最初の2年間はメディアが立ち上がる兆しもありませんでした。
志をもって独立したつもりだったものの、外部メディアへの原稿仕事や、企業からのコンテンツ制作の依頼でスケジュールが埋まってしまっていました。日々のサイクルに、最初の志が埋没してしまったのです。
その状況を打破できたのは、谷川が私の背中を押してくれたことや、東京都が運営するコンテンツ産業専門のインキュベーション施設に入居して、密にコミュニケーションを取りながら共同作業を進める「場」をつくれたことが大きかったです。
しかし、具体的にゼロからイチにもっていくまでの心理的、作業的なハードルは思っていた以上に高いものでした。
アーカイブした記事の価値をマネタイズ化する
進み続けるモチベーションは何でしょうか?
自分のやりたいことができていることが1番のモチベーションです。
かつて前職で感じていた課題に、いま実際に向き合えていること。そして、自分が「やってみたい」と思っていたことに挑戦できていることが、今の仕事への大きな原動力になっています。
今後やりたいことや展望をお聞かせください
いちばんは、『CaseHUB.News』の認知度を上げ、マネタイズして持続可能な形にしていくことです。
広告収入を増やしていくことも考えていますが、それだけでは旧来型のメディアのビジネスモデルにとどまってしまいます。
我々は事例に特化して記事コンテンツを蓄積してきました。事例だけの蓄積という意味では、もうすでに業界最大級のデータベースになりつつあります。
生成AIなどの先進テクノロジーを活用して、アーカイブされた記事から新たな価値を生み出し、メディアにおける新たなビジネスモデルの可能性を提示できるのではないかと考えています。
たとえば、蓄積した記事をデータソースとして、業種業態や企業規模別に 、ITソリューションを活用した具体的な課題解決のためのオーダーメイドのレポートを効率よくつくることも可能だと考えています。
記事の資産を使って2次的なコンテンツを生み出し、その対価を得るビジネスモデルで、マネタイズを模索していきます。

起業の理由が消極的であってもいい
起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします
起業はどうしてもやりたいことがあるからするもので、起業するには熱い思いが必要だという考え方もあるでしょうが、私自身は必ずしもそうでなくてもいいのではと思っています。
現在は、起業や経営を丁寧にサポートしてくれる安価なツールやサービスが充実してきていて、起業の実務的なハードルは決して高くありません。
組織で働くことの価値や意味、組織で働くからこそできることはもちろんたくさんあります。ただ、組織で働きながら実績と実力を蓄えた人が、自分の努力ではどうしようもない理由で行き詰まってしまうこともあるでしょう。
そういう場合に、次のキャリアの選択肢として起業を考えやすい環境になっていると感じます。起業の目的やかたちはいろいろありますし、場合によっては消極的な理由での起業だってあっていいと思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました!
起業家データ:本多 和幸氏
山形県酒田市出身。2003年、早稲田大学第一文学部を卒業し水インフラの専門紙を発行する水道産業新聞社に入社。関連省庁担当記者や企業ニュース面キャップなどを経験。2013年に株式会社BCN入社。「週刊BCN」の記者として法人向けITビジネス領域の取材に従事。国内外の大手ベンダーから有力スタートアップまで幅広く取材を担当。2018年1月から2021年12月まで、週刊BCN編集長を務める。2022年春に独立し、霹靂社を設立。2024年9月、谷川耕一とともにビジネスITのユーザー事例専門ニュースメディア『CaseHUB.News』を立ち上げ。
企業情報
|
法人名 |
株式会社霹靂社 |
|
HP |
|
|
設立 |
2022年3月 |
|
事業内容 |
|
関連記事